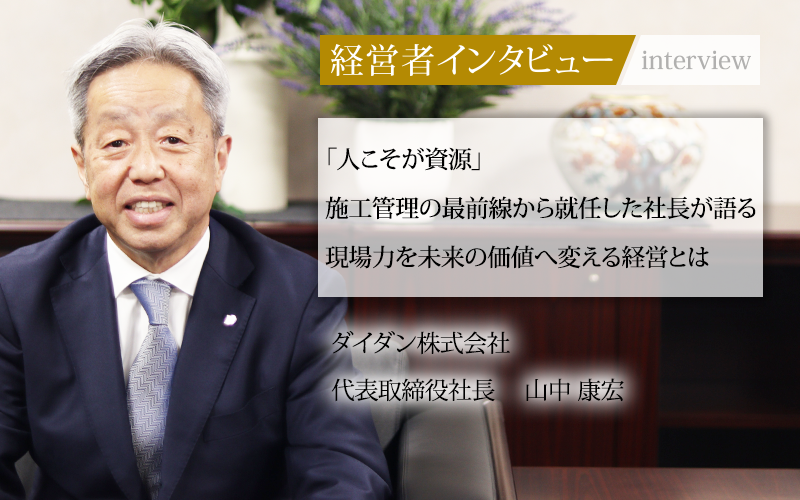
1903年創業、空調、電気、給排水衛生といった設備工事を手がける総合設備企業、ダイダン株式会社。大型産業施設や医療施設、さらには再生医療や海外展開にも事業を広げる中、2024年に代表取締役社長に就任したのが山中康宏氏だ。高専卒で現場からキャリアをスタートし、27年間にわたって施工管理の最前線に立ち続けた山中氏。「人こそが資源」という揺るぎない信念を抱く山中社長に、これまでの軌跡と今後の展望について聞いた。
地元志向から始まった技術者人生
ーーダイダンに入社されたきっかけは何でしたか。
山中康宏:
私が通っていた奈良工業高専は、地元志向の学生が多く、私もできれば地元で就職したいと考えていたため、地元に支店がある会社から調べ始めました。当時は今のようにインターネットがあるわけでもなく、学校に届く求人票や先生の推薦が中心で、その中で見つけたのがダイダンでした。
高専の機械工学科でレーザー光線での計測や鉄の加工について学んでいましたが、空調という分野については正直あまり理解していませんでした。ダイダンに入社するまで、空気調和がビルにどう生かされているのかすらピンと来ていませんでした。
ーーダイダンに入社されてからのことを教えてください。
山中康宏:
1983年4月に入社してから、半年間は大阪・千里にあった研修所で共同生活を送りながら研修を受けました。これは当時から続いている制度で、現在も新人研修として実施されています。参加していたのは、設備系の学科だけでなく、船舶や機械、建築、電気など多様なバックグラウンドを持つ仲間たち。それぞれが専門分野の基礎知識を持ちながら、「設備工事」という新しいフィールドに飛び込んでくる、その多様性がとても面白かったですね。
研修は座学に加え、実物の設備を使っての教育も多く、空調、電気、衛生といった各分野の基本構造を実際に見て、触れて、理解する、実践的な研修でした。そして、「会社とは何か」「この仕事とは何か」を身体で覚えるような時間でもありました。そこで感じたのは、「みんなで一緒に学ぶ」という会社の温かな雰囲気。ダイダンという会社の空気感や、人の良さがその半年間で自然と沁み込んできました。配属前の私にとって、それはとても大きな財産になりました。
現場での厳しさと楽しさ、図面が形になる喜びと手応え

ーー働き始めてから、どんなことを感じていましたか。
山中康宏:
初めて現場に出たとき、その厳しさに圧倒されました。「きつい・汚い・危険」のいわゆる「3K」という言葉が広まる前でしたが、当時はそれが当たり前の世界でした。
若い頃は、職人さんとのやりとりも厳しく、父親ほど年の離れた職人さんに怒鳴られながらも、工程や施工について学びました。今振り返ると、人と人のぶつかり合いの中で、信頼が生まれ、やがて共に建物をつくる仲間になる。その過程自体が私にとっては現場の楽しさでもあったと思います。
ーー仕事のどんな部分にやりがいを感じていましたか。
山中康宏:
自分の描いた施工図が、実際に建物の中で形になる。その瞬間に立ち会えるのがものづくりの醍醐味だと感じていました。施工図とは、設計図だけでは足りない詳細情報を盛り込んだ、現場にとって最も重要な図面のこと。たとえば、柱の位置や天井の高さ、扉の干渉などを考慮しながら、配管や配線を何メートル進んだら何センチ上げる、どこで曲がる、というように具体的に描かれています。そして、その図面がそのまま職人さんの手によって具現化され、風が通り、水が流れるという形になる。自分の設計が機能として立ち上がる瞬間は、本当に気持ちがいいものです。
仲間に支えられた27年の現場経験
ーー長い間、現場で仕事を続けたのにはどんな理由がありますか。
山中康宏:
私は入社から27年間、施工管理の現場で仕事をしてきました。そのうち約20年間は、大規模な建設現場に常駐して、現場のトップとして指揮を執るのが仕事。日々、目の前で状況が変化する中、工程管理や安全管理、協力会社との連携など、多くのことに気を配る必要がありました。大規模現場ではプレッシャーも大きく、正直、苦しいと思う場面も少なくなかったです。
その状況の中でも長く現場で働けたのは、工期の異なる現場を経験できたことが大きな理由です。リニューアル工事のように短期間で成果が見える現場と、長期にわたって粘り強く取り組む現場。その両方を経験できたことで、よいバランスでキャリアを重ねることができたと思っています。
ーー印象に残っているできごとはありますか。
山中康宏:
ランドマークタワーなどの大型プロジェクトに、ジョイントベンチャー(共同企業体)の一員として参加し、ダイダンの社員ではない他社の方々と長期間にわたって一緒に働く機会がありました。その期間中、ダイダンの社員とは離れて仕事をするのですが、会社のイベントや会議などで半年に一度は顔を合わせることがあり、そのたびに、「私の仲間はやっぱりダイダンにいるんだ」と実感。会社を離れて働いてみたからこそ、ダイダンの組織としての温かさや一体感を強く感じることができました。
私は若い頃から、人と接することが好きで、人間関係を大切にしてきました。現場でのコミュニケーションや、上司・部下・職人さんとの信頼関係が、仕事の成果を左右する世界でもあります。そうした日々のやりとりに支えられて、結果的に今の自分があるのだと感じています。
現場出身者だから築けた営業の信頼
ーー技術職から営業職へ移られた経緯について教えてください。
山中康宏:
私が長く所属していた横浜支店は、東京本社の傘下にある当時は小規模な組織で、一人が何役も担う必要がありました。私は人と接するのが好きだったこともあり、技術者としてお客様と直接やり取りをする中で、次第に営業的な役割を担うようになったわけです。
技術畑出身ではありましたが、現場の知識があるため、お客様の課題や要望を即座に理解できるという強みがありました。費用感や工期、必要な設備の種類といったことも現場目線で提案できるため、信頼していただけることが多かったと思います。その経験を活かし横浜支店長となり、その後、東京本社で営業部長を務め、さらに営業本部長として全国の営業を統括する立場になりました。
お客様にとって、現場を知っている人間の言葉には説得力がありますし、こちらの説明にも安心感を持っていただける。営業において、単に商品や工事を売るのではなく、信頼関係を築き、課題解決に寄り添うことが大切だと考えています。全国規模での大型案件や新規開拓にも関わる中で、その思いはより一層強くなりました。
医療・海外・産業へ広がる挑戦

ーー現在注力されている事業は何でしょうか。
山中康宏:
産業系の受注が急速に伸びており、半導体やデータセンター、EV用電池工場といった分野が主力です。全体の受注額に占める産業系の割合は約60%に達しており、弊社の受注高2800億円のうち約1600億円を占めています。クリーンルームやドライルームといった高精度な空調管理が求められる現場での施工力が、弊社の強みとして発揮されているのだと自負しています。
また、クリーンルーム施工の技術を活かして、再生医療や医薬分野への事業展開を進めています。そのために、2020年に子会社、セラボヘルスケアサービス株式会社を設立しました。この子会社では主に、手術室や医療機器の開発・販売など、医療空間の構築全般に取り組んでいます。これまでの病院施工の実績や、医師・研究者とのネットワークがあったからこそ、自然な流れで参入できた分野だと感じています。さらに、治験薬の受託製造を行う薬の受託事業も展開しており、厚生労働省からの認可も取得済みです。
ーー海外事業についての現状と今後の展望をお聞かせください。
山中康宏:
かつてはマレーシアやフィリピンなど幅広く展開していましたが、縮小を余儀なくされた時期もありました。しかし、現在は再成長フェーズにあり、シンガポールを中心に、タイ、ベトナム、台湾で事業展開を進めています。
特にシンガポールでは、M&Aによって100億円規模の企業をグループに迎え入れ、海外全体で300〜400億円規模まで事業を拡大しました。国際事業本部には新たに専属の営業人員も配置し、受注の拡大を目指します。また、施工力強化の為に技術社員自らが希望して海外に挑戦できる体制も整えています。
人が資源、未来をつくる人材戦略
ーー管理職として、どのような課題に直面されましたか。
山中康宏:
現場で長く働く中で、最も苦労したのが人の配置です。職人さんの不足が叫ばれる昨今ですが、当時から技能者・管理者の両方が足りず、人をどう割り当てるかは常に大きな悩みでした。とにかく目の前の工事を納めることに手一杯という状況が長く続いていました。
そして、人の能力を高めたくても、教える側の余裕もなく、教育にかける時間が取れない。仕組みとしても十分とは言えませんでした。「もっと余裕をもって人を育てられていれば」という思いは、ずっと抱え続けてきた後悔のひとつです。
ーー当時の現場での人材課題は、今どのように生かされていますか。
山中康宏:
社長就任にあたり、「採用計画」「教育」「ローテーション」の3本柱を人材戦略の核とすることを打ち出しました。まずは採用母数を増やすこと、そして確実に育てること。さらに地域や部署を越えて人を循環させ、経験と人脈の幅を広げること。この3つを軸に、企業価値の向上を図ろうと考えたのです。
私は長く現場にいたからこそ、人材不足が組織のボトルネックになり得ると痛感しています。そして、人を適切に配置できる会社こそが、安全で、品質の高い仕事を持続的に提供できる会社だとも思っています。だからこそ、人的資源に本気で向き合い、未来を担う世代にしっかりと託せる組織づくりを進めていきたいと考えています。
こうした考えのもとで実施しているのが、冒頭でもお伝えした半年間の新入社員研修制度です。共同生活の中で業務の基礎を学ぶこの研修は、仕事の理解を深めると同時に、同期との連帯感を育む場にもなっています。また、若手社員には早期に責任あるポジションを任せ、小規模現場のリーダーとして育てるOJTも積極的に行っています。
ーー今後の展望や、採用に対するお考えをお聞かせください。
山中康宏:
私たちは現在、長期ビジョン「Stage2030」の実現に向けて取り組んでおり、その中で3000億円という売上高の目標を掲げています。本来は2030年を目標としていますが、ここ数年の成長を受け、少しでも前倒しでの達成を目指しています。
この成長を実現する上で、最も重要なのがやはり「人」です。私たちのような総合設備工事の業界では、扱う資源はほとんどが人。現場の品質も、安全も、ひいては企業としての競争力も、すべては人材の数と質にかかっています。そのため、私は「経営資源は人しかない」と繰り返し訴えてきました。
採用面では積極的な拡大を進めており、近年は100人規模の新卒採用を継続しています。人材の層を厚くしながら、育成にも注力しており、成果配分制度の導入や、エンゲージメントスコアの向上もその一環です。社員の貢献に報い、組織全体の士気を高めることが、持続的な成長につながると考えています。
編集後記
施工現場でのやりがいや葛藤を語る姿には、現場で長く培われたリアリティがにじんでいた。社員の温かさを語る眼差しも印象的で、「人が資源」という理念が単なるスローガンでないことを強く感じた。現場、営業、経営を知る山中氏が、次代のダイダンをどう導くのか、今後も注目したい。

山中康宏/1962年奈良県生まれ。奈良工業高専機械工学科卒。1983年にダイダン株式会社へ入社。施工管理職を長年務めた後、横浜支店長、営業本部長などを歴任し、2024年4月に代表取締役社長に就任。














