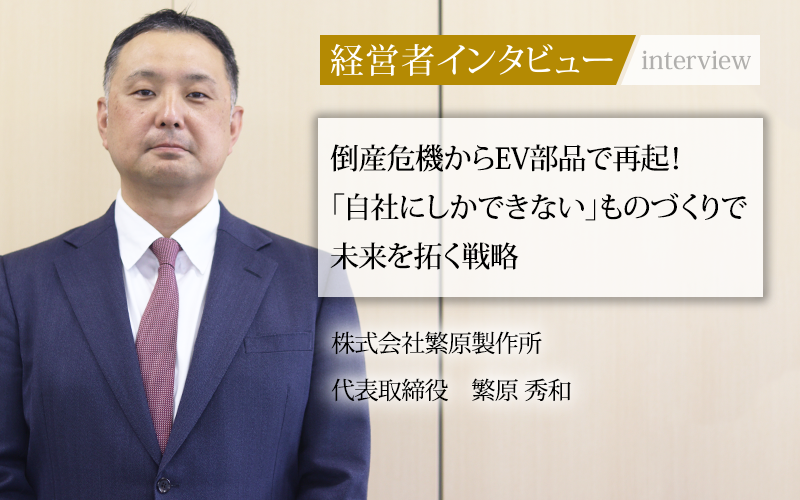
株式会社繁原製作所は、歯車を始め様々な部品の精密加工を得意とする製造会社だ。幾多の危機を乗り越え、独自の技術で日本のものづくりを支えている。代表取締役の繁原氏は、幼少期よりものづくりに触れ、家業承継後はリーマンショックという逆境にあいながら、「自社だからこそ作れる製品」という自負を胸に、試行錯誤を重ねながらもV字回復を成し遂げた。本記事では、進化を続ける同社の軌跡と、人材育成、組織改革、そしてグローバルな未来への挑戦に迫る。
ものづくりの原点と継承への道
ーー社長の幼少期や、ものづくりとの最初の接点についてお聞かせください。
繁原秀和:
大阪生まれで、父が経営する繁原製作所の現場が身近な環境で育ちました。小学校の頃から工場をうろうろし、新しい工作機械が毎年入ってくるのを見ては、その機械やそれらを扱う社員の方々が格好いいと感じていました。この体験が、ものづくりへの興味の原点です。
ーー家業を継ぐことはいつ頃から意識されていたのでしょうか。
繁原秀和:
私は3人の姉と妹がおり、男性は私一人でした。そのため、漠然とですが「いずれ自分が家業を継ぐのだろう」という意識は学生時代からありましたね。大学時代も工場でアルバイトとして深く関わり、マシニングセンターなども扱えるようになっていました。大学卒業後は、一度外の世界を見るために三菱商事テクノス株式会社でお世話になり、大手企業の生産ライン構築などに携わった後、繁原製作所に戻りました。
試練と変革。リーマンショックを乗り越えた自負と製品の進化

ーー繁原製作所に戻ってから、リーマンショックという大きな試練にあったそうですね。
繁原秀和:
家業が非常に好調で人手が足りないというタイミングで戻ったのですが、入社直後にリーマンショックが起こりました。工場拡張のための大きな設備投資をした矢先の出来事で、売上が急減し、債務超過に陥るなど経営は非常に厳しい状況でした。しかし、当社には、自社だからこそ作れる製品があるという強い自負がありました。特に、複数の工程を社内で一貫して行い、高精度な部品を小ロット・短納期で提供できる体制は、他社にはないと信じています。この自負を胸に、必死で営業活動を続けました。
ーー改めて、繁原製作所の事業内容について教えてください。
繁原秀和:
創業当初は歯車部品などの量産品が中心でしたが、価格競争の激化に伴い、より付加価値の高い試作品や治工具などの小ロット生産へシフトしました。それが功を奏して、バブル崩壊後には、高難度・高精密加工の部品が活路を開き、徐々に事業内容が転換していきます。
その後はモータースポーツに出走する車の部品の比重が高まり、リーマンショック前には売上の半分以上を占めるほどになりました。たとえば、「クロスドグミッション」は競技などでスムーズなギアチェンジを可能にするもので、その性能を追求すると、摩擦を減らすように磨きをかける必要があり、結果的に機能美と造形美が融合したものになります。それが結果的に、弊社が誇る唯一無二の匠の技、工芸品ともいえる境地に達したことで、万博での展示につながりました。(※展示名:「饗宴!匠が演じる日本美の世界」)
しかし、リーマンショックと主要取引先の事業変化で一社依存のリスクを痛感することになりました。そこから関西圏の大手企業との取引を広げ、EV(電気自動車)用減速機の開発・製造など、新たな分野へも挑戦してきました。部品加工の競争が一層厳しくなる中、弊社はEV用の試作部品と減速機にフィールドを移し、より専門性の高い製品の設計・開発に注力しています。
未来への挑戦。人材育成・組織改革とグローバル展開
ーー事業領域がより高度化する中で、人材の採用や育成に関する課題はありますか。
繁原秀和:
はい、非常に重要な課題です。より難しいものを扱える専門的な人材は限られており、ベテラン社員の高齢化も進んでいます。そのため、中途採用だけに頼るのではなく、新卒採用を含め、社内で一から人材を育てる体制づくりが急務です。近年では、女性社員の活躍も推進しています。また、外国人人材も、技能実習生ではなく社員として、ベトナム人技術者の採用や育成、技能検定取得支援など、体系的な教育プログラムの導入を進めています。
ーー組織が成長する上で、経営体制の変化も必要になってくるのでしょうか。
繁原秀和:
その通りです。社員数が増え、事業規模が拡大する中で、これまでの「社長とその仲間たち」といった家族的な経営スタイルから、指揮命令系統が確立された組織的な経営へと移行する必要性を強く感じています。各部門に責任と権限を委譲し、それぞれのマネージャーが自律的に動けるような体制を構築しなければ、変化の速い時代に対応できません。
また、仕事の進め方についても変革が必要です。これまでは、お客様も我々も「やったことがないことに挑戦する」というスタンスで、納期や品質条件についても、ある程度の柔軟性の中で協力して進めてきました。しかし、近年は大手企業との取引が増え、厳格な納期管理や品質保証が求められる案件が増加しています。これに対応するためには、しっかりとした計画立案と進捗管理ができる能力を組織全体で高めていく必要があります。
ーー最後に、今後の展開についてお聞かせください。
繁原秀和:
既に評価を得ている分野での実績を足掛かりに、まずはモータースポーツの世界で当社のブランド認知度を高めたいと思っています。そしてゆくゆくは、アメリカやヨーロッパ、そして成長著しいアジア市場など、グローバルな顧客に当社の高度な技術や製品を提供していきたいと考えています。
編集後記
幼少期から家業の工場を遊び場とし、製造のプロセスを肌で感じてきた繁原社長。その言葉には、ものづくりへの情熱と、自社の技術に対する揺るぎない自信が満ちていた。リーマンショックという逆境をバネに、取扱い品を時代のニーズに合わせて進化させ、常に「自社にしかできないこと」を追求し続ける姿勢は、多くの中小企業にとって大きな示唆を与えるだろう。人材育成、組織改革、そしてグローバルな視点。未来を見据えた繁原製作所の挑戦は、これからも飛躍を続ける。

繁原秀和/1978年、大阪府出身。同志社大学商学部卒業後、三菱商事テクノス株式会社に入社し、工作機械販売と営業活動に従事。2008年、繁原製作所に入社。営業力強化や技術革新を推進し、2020年4月、同社5代目の代表取締役に就任。














