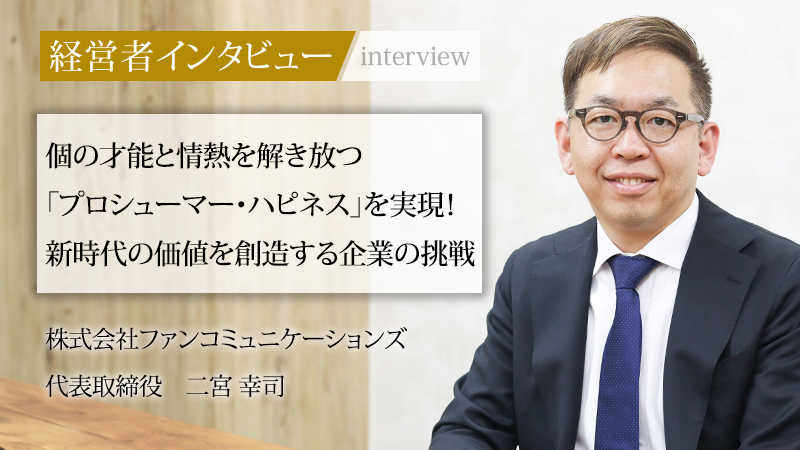
技術力やサービスを駆使して差別化を図ることが企業の生存と成長の鍵とされるネット広告市場で、1999年の創業以来、25年にわたり業界をリードしてきた株式会社ファンコミュニケーションズ。市場が成熟期へ移行する中で、国内有数のアフィリエイトサービスプロバイダーとしての地位を確立した会社だ。
2024年に代表取締役社長に就任した二宮幸司氏は、組織の挑戦と変革の文化を根づかせるべく積極的に舵をとっている。就任から1年を迎えた今、その思いと今後の展望について、話をうかがった。
営業現場で鍛えた基礎と挑戦の歩み
ーーファンコミュニケーションズに入社した経緯についてお聞かせください。
二宮幸司:
私はもともと広告業界に興味があり、学生時代はCM制作のアシスタントディレクターのアルバイトを経験しました。当時、テレビや新聞などのマスメディア広告は圧倒的な存在感がありましたが、インターネットの急速な普及とともに、新たな広告手法としてバナー広告が登場し、注目を集め始めたころでした。
そして、「インターネット広告はまだ発展途上の段階だからこそ、今後新しい価値を創出する機会が得られる」と考え、大学卒業後、ファンコミュニケーションズにアルバイトとして入社しました。
ーー入社後、どのような仕事に携わったのか教えてください。
二宮幸司:
入社後2か月で正社員に登用され、最初はアフィリエイトサービス「A8.net」の営業を担当しました。新人のころは、連日アポイントメントを取り、クライアントのもとに足しげく通い、まさに泥臭い営業を経験。それぞれが抱える課題に寄り添いながら提案を重ね、解決していくという、粘り強く地道な取り組みの連続でしたが、ビジネスの基礎が身につきました。
入社して数年が経ち、営業から管理職となったころ、周囲の仲間も独立を目指す人が多く、「自分も会社を率いる立場になりたい」と考えるようになっていました。そのことを当時の上司に相談したところ、経営に関する知識不足を指摘され、「独立を目指すなら、まず新規事業へのチャレンジをすべき」と助言を受けました。
入社当時から、弊社は主力事業「A8.net」の安定の裏で、新規事業をいくつか立ち上げ、継続的な成長を模索していました。上司からのアドバイスも後押しとなり、それまで経験のなかった事業開発部に異動。スマートフォン向け広告ネットワーク「nend」の立ち上げの責任者を務めました。
ーー新しい事業に関わる中で、苦労されたことや印象的だったことを教えてください。
二宮幸司:
新規事業を進める中で感じたのは、これまで培った営業の経験や実績が通用しないということ。「使う脳みそが違う」という感覚です。
弊社は営業力に強みを持っており、全社一丸となって目標達成に向けて役割をしっかりと分けて動くという企業風土があります。営業部も決められた役割やルールをもとに行動することで、組織的な顧客拡大の仕組みを確立していました。しかし、事業開発部は、既存のルールや仕組みに疑問を持ち、自由な発想を活かしてゼロから新しい価値を創造するのが仕事。メンバーの価値観もさまざまで、社内でも異質な存在でした。
新規事業の成功には、メンバーと意見が食い違ったとしても、同じ目標に向かって互いの価値観を受け入れ、協力し合う体制構築が不可欠です。そのバランスを保ちながらチームをまとめ、事業を軌道に乗せる過程には多くの苦労がありましたが、その分、期待以上の成果を得たときの喜びは格別でした。
多様な価値観を持つ人材と方向性を合わせるというマネジメント手法は、現在進めている組織改革の推進においても重要な礎となっています。私自身の成長にも欠かせない経験となりました。
「第2創業期」として組織改革に着手

ーー社長に就任されたときの心境や目標についてお聞かせください。
二宮幸司:
私が社長に就任した2024年は、会社として大きな転換点を迎えていました。主力事業の安定した成長に加え、2010年に開始したスマートフォン向けアドネットワーク事業の成功により、2014年の東証一部上場時の収益基盤は強固。時価総額は最大で約2000億円近くまで上昇し、営業利益も短期間で4倍ほどに伸びました。
その後、スマートフォンがコモディティ化し、誰もが保有する成熟期に入ると、一転して事業の売上に影響が及び始めました。アドテクノロジーの領域は大手グローバル企業の影響力が大きいうえ、Appleのプライバシー規制強化などの外部要因も重なり、会社全体が停滞している状況でした。
こうした中、私がなすべきことは「会社を変えること」でした。このミッションを胸に、2024年を「第2創業期」と位置づけ、実態の改善とこれから先の25年を見据えた持続可能な成長を目指すことになります。
――就任されて1年ほど経過しましたが、どのような取り組みをされていますか。
二宮幸司:
最初に取り組んだのは組織の改革です。25年の歴史の中で変化に弱くなっていた組織は、硬直化が進み、経営層と現場との間に距離が生じていました。
そこで、トップダウンで決めるべきことを明確化し、新しい挑戦へのリソースを拡大するため、人材の移動を行い組織の流動性を高めています。また、自ら積極的に発信し、社員との対話の機会を増やすよう努めています。
特に意識しているのは、組織として共有すべきビジョンや行動指針といった重要なメッセージを、伝えることです。職種に関係なく「目標達成にこだわる」「対話する」「挑戦する」という会社にしたいと明確に伝えています。これを繰り返し伝えることで、会社全体の意識が少しづつ変化していくことを目指しています。
特に、第2創業期においては、挑戦を奨励し、失敗を恐れず学びに変える環境づくりが組織の成長には欠かせません。その一環として、小さな取り組みではありますが、社内チャットツール「Slack」に「ナイスチャレンジ」スタンプを導入しました。これは、新しいことに挑戦した社員に対して、上司や仲間たちが、この「ナイスチャレンジ」スタンプを押すことで、その挑戦がみんなに共有される仕組みです。こうした個々の挑戦を見える化し、挑戦しやすい環境を整えることで、たとえ失敗しても前向きに振り返られる文化づくりを進めています。
また、私を含め経営陣自らが新しいことに挑戦する姿勢を示すために、担当役員の変更も行いました。経営陣が率先して挑戦することで会社全体で挑戦の機運を高めていきたいと考えています。
こうした組織改革を着実に進めることで、企業の基盤を再び強固なものにし、同時に新規事業への挑戦も継続しながら、持続的な成長へとつなげていきたいと考えています。
インフルエンサーマーケティングに見る戦略的洞察

ーー貴社の主力事業と、特に力を入れている点について教えてください。
二宮幸司:
主力事業「A8.net」は、広告主である企業とアフィリエイターと呼ばれる広告掲載者をつなぐサービスです。広告主は自社の商品やサービスを紹介してくれるアフィリエイターに成果報酬を支払い、アフィリエイターは自身のSNSやウェブサイトに広告を掲載し、成果に応じて報酬を得ます。
アフィリエイト広告は、プログラムや報酬設定、管理業務などの仕組みが非常に複雑ですが、弊社は業界トップの地位を長く維持しています。法律が変化していくなかでも、私たちは業界のリーディングカンパニーとして、「健全なアフィリエイト広告運営」に強い自負を持っています。ただ、長年の実績は現状維持への甘えを生み、変化を起こす際の障害となる可能性もあるため、全社的に現状に疑問を持ち、自ら変わることの重要性を共有しています。
また、現在力を入れているのが、急速に伸びているインフルエンサーマーケティングです。特定の分野で影響力を持つ人物(インフルエンサー)に、広告主の商品やサービスを紹介してもらい、認知拡大や売り上げ向上につなげるマーケティング手法です。
この分野は、フォロワー数や1投稿あたりの課金が主流です。これは従来の広告でいう期間保障や広告表示回数に応じた課金(インプレッション課金)と同様の仕組みです。後にクリック課金型が広まりましたが、弊社では成果報酬型に勝機があると考えています。弊社はインフルエンサーマーケティングへの参入は後発ではありますが、市場が成熟化すると成果報酬型にシフトしていくという予想のもと、長年のアフィリエイト事業で培った独自の視点をベースに、競合他社との明確な差別化を図っていこうと思っています。
弊社のインフルエンサーマーケティングの強みは、エンゲージメント(行動につながる信頼の強さ)の質にあります。たとえば、数十万人のフォロワーがいても、エンゲージメントが低いと効果は限定的です。一方で、数万人のフォロワーでも熱心なファンを持つインフルエンサーは、エンゲージメントの質が高く、その分成果報酬も大きくなります。このエンゲージメントに基づく綿密な分析力を武器に、広告主に向けて高い効果を提供しています。
「プロシューマー・ハピネス」が示す企業理念の本質
ーー成長につなげるための今後の方針や展望についてご意見を聞かせください。
二宮幸司:
「第2創業期」と位置づけた今、変革と挑戦を続け、新しい成長サイクルを創出し、再び市場価値を高めることを目指しています。その中核にあるのが「プロシューマー・ハピネス」というビジョンです。
「プロシューマー」は、生産者(プロデューサー)と消費者(コンシューマー)を組み合わせた造語です。新しい価値をつくる個人であり、自ら考え、創造し、熱量を持って世界に発信する人を指します。
弊社はアフィリエイト広告を主軸に事業を展開しているため、単なる広告代理店と思われがちですが、インターネットの本質的な力を信じ、「エンパワーメント(いかに個人に力を与えるか)」に重きを置いています。プロシューマーが情報発信を行い、新たな価値を創造しながら経済活動に参加し、幸福感や充実感を得られる社会の実現を支援する。このビジョンを掲げ、創業以来、一貫して追求しています。
中長期的には、デジタルマーケティング領域での仕組みの複雑さを解消し、誰でも利用できるサービスへと進化させる取り組みを継続しながら、プロシューマーがさらに成長できるような革新的なツールを提供したいと考えています。デジタルマーケティング領域において一気通貫で顧客に価値提供することを目指し、そこに全社のリソースを集中し、持続可能な成長を実現するための基盤を整えているところです。
ーーどのような人材を求めていますか。
二宮幸司:
変化の激しい不確実な時代においては、どこに行っても通用する人材が求められています。私はその鍵となるのが仮説思考と実行力、そして柔軟性だと考えています。
新規事業はもちろん既存事業でも、正解が明確でない状況では、仮説を立てて行動し、その結果を検証するプロセスが重要です。机上の空論ではなく、実際にお客様と接し、現場での経験を通じて学ぶ姿勢が求められます。AIの活用など新技術による生産性向上の波も訪れており、柔軟性をもって挑戦することもスキルアップになるはずです。
採用においては需要と供給のバランスもありますが、働く側も企業側も対等であり、互いに選ばれる努力を続けること。これらが互いの持続的な成長へつながると考えます。
私自身もアルバイトからキャリアをスタートし、挑戦したいという思いに機会が与えられ、うまく時流に乗り、今日に至っています。若い皆さんにも、ぜひ自律的に考え、行動し、挑戦し続ける姿勢を持ち続けてほしいと願っています。そして、そのような方々と一緒に、未来を切り拓いていきたいと思っています。
編集後記
長年にわたり業界をリードしてきたファンコミュニケーションズ。社長のリーダーシップにより変革期にある組織に新たな息吹を吹き込み、挑戦を推奨する文化を醸成している。デジタル広告の最前線で成果を追求しながらも、人を大切にする姿勢が企業の成長の原動力となっているようだ。インフルエンサーマーケティングという新たな成長エンジンと、「プロシューマー・ハピネス」という創業以来のビジョンを礎として、再び大きな飛躍を目指している。

二宮幸司/1979年、福岡県生まれ。法政大学卒業後、株式会社ファンコミュニケーションズに新卒入社。スマートフォン向け運用型アドネットワーク「nend」の立ち上げなどに従事し、2024年に同社代表取締役社長に就任。新規事業領域やIR活動にも積極的に取り組んでいる。














