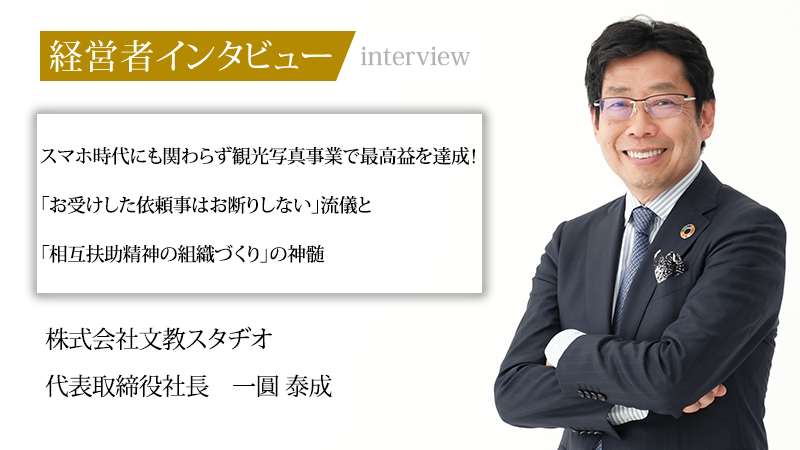
全国70カ所以上の観光施設で来場客の想い出づくりを支える、株式会社文教スタヂオ。誰もがスマートフォンで気軽に写真を撮る時代に、「想い出創造企業」を掲げ、過去最高益を更新し続けている。その強さの源泉は、顧客の要望に徹底して応える社員の姿勢と、社員一人ひとりが経営者視点を持ち互いに助け合うホラクラシー組織にあった。今回、代表取締役の一圓泰成氏に、大きな転機となった出来事や未来を見据えた社内改革について話をうかがった。
技術だけでは生き残れないと知った経営の神髄
ーーまず、社長のご経歴についておうかがいできますか。
一圓泰成:
株式会社文教スタヂオが創業期、家の中に会社があったため、幼い頃から家業を継ぐことに大きな疑問はありませんでした。大学で写真の持つ芸術性と社会性を学んだ後、将来経営に役立つ簿記経理を専門学校で学び、簿記資格を取得しました。
卒業後は阪急系の名門ホテル「宝塚ホテル」の写真室などを経営する老舗写真館で、2年間修業しました。当時は、写真館の子息が学ぶ徒弟制度が残っていて、レベルの高い技術とさまざまな社会を学ばせてもらいました。
当時は、撮影から修正技術のすべてを習得するには10年はかかると言われていましたが、わずか2年で帰ることになりました。新本社ビル建設と毎年多くの博覧会事業が目白押しで事業拡大が目覚ましいので父から要請があったからです。
ーー家業に戻られて、なにか気づきなどはありましたか。
一圓泰成:
修業先では一つの仕事に複数人で丁寧にあたるのに対し、弊社では一人ですべてをこなします。学んだ技術は素晴らしいものでしたが、ビジネスとして考えた時、いくら手間暇をかけても料金は同じ。最高の技術を持っているだけでは、利益は上がらないということを痛感しました。
また修業先では、仕事を選び、面倒な仕事は引き受けない風潮がありました。しかし、写真業界を取り巻く環境が厳しくなる中で変革を図れず、徐々に経営危機に陥っていました。その経験から、弊社では、「できない理由を探すのではなく、どうすればできるか」を考えるようにしています。この「お断りしない姿勢」こそが、当時から変わらない弊社の流儀です。
会社の未来を賭けたUSJ事業への挑戦

ーー社長へ就任された後、どのような改革を進めましたか。
一圓泰成:
当時は大手旅行会社が企画する団体バス旅行が減少をし始め、大型旅館も経営の岐路に立たされている現実を目の当たりにして、弊社も団体写真事業は同じ運命をたどることが見えていたため、「お客様の概念を個人客にシフトしよう」と考えたのです。しかし、団体専門でやってきた社員たちは、今更個々のお客様への声かけに抵抗がありましたが、挨拶や電話応対のマナーなどを再教育し、会社としての基礎固めを整えることから始めました。
事業転換の大きなきっかけは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の開業です。「このテーマパークが全ての近畿圏の遊園地の在り方を変えることが明確なため、何としても取らなければ」と考えました。そして大手感材メーカー様のお力添えをいただき、フロリダの本部にて分厚い提案書でプレゼンする機会を得ました。しかし、写真好きで団体旅行が多い日本との意識の違いもあり、売上予測数値に対し最初に言われた言葉は「foolish(馬鹿げてる)」や「クレイジー」でした。それでも日本との文化の違いなどを粘り強く訴え、契約にこぎつけました。
USJのプロジェクトは、団体写真にこだわっていたベテランではなく、あえて若いスタッフを中心にチームを組みました。ここでゲストサービスの神髄を学んだことにより、全国に波及を及ぼし、実践できたことは大きな財産です。この成功体験が、その後の海遊館を皮切りに全国の動物園や水族館への展開につながりました。
最高益を生み出す現場主役の「ホラクラシー組織」
ーー事業の強みについて、どうお考えですか。
一圓泰成:
「スマートフォンで写真が撮れるのに仕事があるのですか?」とよく言われます。しかし、弊社は昨年、過去最高益を達成しました。スマートフォンが普及したことで写真撮影の機会は何十倍にも増え、撮ること、撮られることへの意識が非常に高まりました。これが弊社にとって追い風となったのです。
もちろん、ただ撮るだけでなく、お客様のニーズに合わせて商品構成を増やしたことも大きな要因です。たとえば、以前は写真を専用の額縁型のフォルダーに入れて販売するだけでしたが、今はアクリル製品が増え、可愛いアクリルスタンドやキーホルダーにするなど、付加価値の高い商品を整えたことで選択肢が増えて同時に売上が伸びています。
ーー組織づくりで注力されていることはありますか。
一圓泰成:
弊社では、トップダウンではなく「ホラクラシー組織」という考え方で、社員一人ひとりが自発的に創意工夫し、経営理念に基づいて行動できる組織を目指しています。これを基に、現場一つひとつが独立した組織のように運営されています。たとえば、日次決算で収支を確認できるため、社員一人ひとりにコスト意識と経営者視点が生まれます。また、撮影セットの装飾も、以前は高額な広告代理店に依頼していましたが、今では「もっと安くつくれないか」と社員が自分たちで業者を探し、工夫するようになりました。あまりに現場の裁量が大きいので、取引先からいつも驚かれます。
「文教スタヂオがいてくれてよかった」と評される存在へ

ーー今後の事業展開についてはどうお考えですか。
一圓泰成:
個人観光客向けの記念写真撮影を弊社ほどの大きな規模で行っている同業他社はいません。そのため、イノベーションは社内で起こすしかないと考えています。年に二度、全国の現場リーダー70人を本社に集め、新しい挑戦の成功事例を共有し、互いに競い合わせる場を設け、「すごいな、うちでもやってみよう」と成功事例がすぐに他の現場に伝播していきます。その内容は従業員満足を高める手法やゲストサービスの仕組みを変えた例など様々です。先ずは模範になる現場を視察、一緒に体験しノウハウをそのまま移植し、のちに先駆者が指導することもあります。この循環が、会社全体の成長を促しているのです。
ーー会社の目指す姿を象徴するようなエピソードがあれば教えてください。
一圓泰成:
沖縄のテーマパーク「おきなわワールド」の創業者である大城会長の言葉が忘れられません。ある日、「なぜ、施設の玄関という一番大事な場所を君たちに貸しているか分かるか」と問われました。そして、「君たちが玄関で励む姿が模範であり、当社の社員も負けないで努力して欲しいからだ」と言われました。
大城会長は、「沖縄では、その日の売上目標を達成すると早くに店を片付け始める県民性があるが、文教はそこから更に前へ前へと進む気概がある」「近江商人の魂だと思うが、何時も文教に負けるな!と言えるようにしておいてくれ」と言われた。つまり社員を鼓舞するために言われたのだが、他の施設で「文教スタヂオがいてくれてよかった」と言われる存在になること、それがこの会社の社風であり、目指すべき姿なのだと改めて感じました。
編集後記
スマートフォンが普及し、誰もが気軽に写真が撮れる時代。写真館事業の縮小が叫ばれる中、文教スタヂオは「想い出創造企業」として過去最高益を更新し続けている。その根幹には、どんな状況でも顧客の要望に応えようとする「お断わりしない」姿勢と、社員一人ひとりが当事者意識を持つ「アメーバ経営」があった。おきなわワールドの会長が語った「文教に負けるな」という言葉は、同社が単なるテナントではなく、施設全体の価値を高めるパートナーであることを証明している。これからも同社は、全国の観光地で最高の思い出を演出し続けていくだろう。

一圓泰成/1962年2月22日生まれ。1984年に大阪芸術大学芸術学部写真学科を卒業。大阪の株式会社工藤写真館で写真の技術を学び、1987年に文教スタヂオへ入社。1991年より同社取締役副社長を務め、1997年に代表取締役社長に就任。社員一人ひとりの主体性を尊重し、人を大切にする経営方針を掲げている。また2013年より公益社団法人彦根観光協会会長を10年した後に2024年より滋賀経済同友会の代表幹事を務めている。














