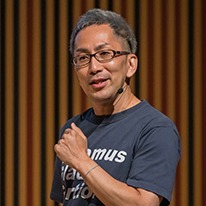教育施設や文化施設、庁舎建築など、社会の基盤となる多様な建築物を手掛ける株式会社石本建築事務所。創立からまもなく100年の同社を率いるのは、代表取締役社長の長尾昌高氏だ。設計者として、また経営者として、数々の大規模プロジェクトを成功に導いてきた。その原動力にあるのは「建築の設計は、面白い」という純粋な思いだ。組織を改革し、未来の人材に会社の舵取りを託そうとする長尾氏に、建築の奥深さと会社の未来像について話を聞いた。
最初の一歩は“消去法” 忘れられた文集に記された夢
ーー建築の道に進まれたきっかけについてお聞かせください。
長尾昌高:
大学で建築を選んだのは、実は“消去法”でした。もともと理系に進もうとは決めていたのですが、かといって電気や化学、数学といった分野に強い興味があったわけでもありません。理系の選択肢の中から自分に向いていないものを一つずつ消していった結果、最後に残ったのが建築だったのです。しかし、後年、小学校の同窓会で恩師が持ってきてくれた当時の文集を見ると、そこには「設計士になりたい」と書いてありました。自分ではすっかり忘れていたのですが、無意識のうちに幼い頃の夢を追いかけていたのかもしれません。
ーー入社後、特に思い入れのあるプロジェクトは何でしょうか。
長尾昌高:
札幌で手掛けた「札幌市立大学」は印象深いですね。この大学は、当時札幌の芸術の森にあった札幌市立高等専門学校と看護系の学校を統合して開学されたのですが、その高等専門学校の学長が著名な建築家の清家清先生で、直接打ち合わせる機会に恵まれました。全長400mにもなる直線的なアプローチと施設群のデザインが特徴で、敷地内に丘が立ちはだかっていたのですが、「トンネルで真っすぐ行けばいい」という清家先生の一言で解決に至りました。先生の発想力・説得力に感銘を受けたことを覚えています。
また、「ナショナルトレーニングセンター」も忘れられません。トップアスリートの練習拠点として、各種球技場やバドミントン・体操・柔道場などの柱のない大空間を何層も重ねるという非常に難度の高い設計でした。西側の共有ラウンジからは富士山が見えるように工夫し、わが国を代表して世界へ挑む選手たちの気持ちを高める仕掛けも施しています。
「One ISHIMOTO」が起こした革命 目指すは“金太郎飴”の品質

ーー「One ISHIMOTO」というスローガンを掲げた組織改革について、その背景と目的をお聞かせください。
長尾昌高:
以前は東京の本社と地方の支所という上下関係の強い組織でしたが、この体制では、現場が本社の指示を待つばかりで主体的な判断が生まれにくく、「本社の指示通りにやったが失敗した」というような責任転嫁につながりかねません。こうした状況をなくし、実際のプロジェクトが動いている現場でメンバー一人ひとりが主体的に考え、判断できる組織にしたかったのが、改革の大きな動機です。
そこで、まず本社・支所という形をやめ、全拠点を対等な「オフィス」としました。同時に、建築設計に関わる各種専門分野や営業、総務といった専門性に応じた全社横断の「部門」を立ち上げたのです。場所の軸と機能の軸が交差する、いわゆるマトリクス型の組織ですね。各拠点の独立性を保ちながら、全社的な専門知識を結集してプロジェクトを推進するという目標を達成しようと考えました。
私がこの改革で目指しているのは、どこを切っても断面に同じ顔が現れる“金太郎飴”のように、提供するアウトプットの品質を、常に高いレベルで均質にすることです。どのオフィスに依頼をいただいても、石本建築事務所として常に高いレベルの成果を達成すること、言わば「石本クオリティ」をお約束する。そのための組織改革でした。
ーー貴社の顧客にはどのような特徴がありますか。また、顧客と接する際に気をつけていることはありますか?
長尾昌高:
現在は官公庁と民間のお客様がほぼ半々です。民間では、本田技研工業様とは創業者・本田宗一郎氏の時代から60年以上のお付き合いになります。また、箱根駅伝に出場する大学法人様の多くも、私たちの長年のお客様です。一度きりの関係で終わるのではなく、お客様に「次も石本さんに頼みたい」と言っていただけるような、継続的な信頼関係を築くことを大切にしています。
万博、そして100周年の先へ。未来を創る挑戦

黒い膜材による外壁の表面を水が伝い落ちるデザインが、鮮烈な個性を放つ
ーー近年の代表的なプロジェクトや取り組みについてお聞かせください。
長尾昌高:
直近では、2025年の大阪・関西万博に参画し、アンドロイド研究の第一人者である大阪大学石黒浩先生のパビリオンの設計を手掛けています。「人間の命が電子情報として引き継がれるなら、どうするか」という深遠かつ未来的なテーマを建築で表現する、非常にやりがいのある挑戦でした。
ーー組織づくりや人材については、どのようなお考えをお持ちですか。
長尾昌高:
現在、会社のあり方を見直す中で、人事制度の改革にも力を入れています。私自身が新卒入社だからこそ、社外の視点や多様な考え方を取り入れることが、組織の成長に不可欠であると痛感しています。そのため、新卒入社の社員とキャリア採用の社員を全く区別していません。役員にもキャリア入社のメンバーがおり、今後も多様な経験を持つ方に活躍してほしいと願っています。
ーーまもなく創立100周年を迎えられますが、その先の未来をどう描いていますか?
長尾昌高:
100周年は決してゴールではありません。むしろ、それを一つのきっかけとして、会社の未来を担う若い世代が「これから石本をどうしていきたいか」を本気で考える機会にしてもらいたいです。上の世代が何かを押し付けるのではなく、彼らが自由に発想して、挑戦できる環境を自ら整えること。それが、次の100年を創る上で最も大切なことだと考えています。
編集後記
「設計は面白い」。長尾社長の言葉は、キャリアの原点から現在に至るまで、一貫した情熱に裏打ちされていた。組織の壁を壊し、社員一人ひとりが主役となる「One ISHIMOTO」の理念。それは、最高の品質を追求するプロとしての矜持と、未来を担う世代への深い信頼の表れである。100周年を通過点と捉え、その先の未来を次世代の社員に託そうとする姿勢に、進化を止めない企業の力強さを感じた。
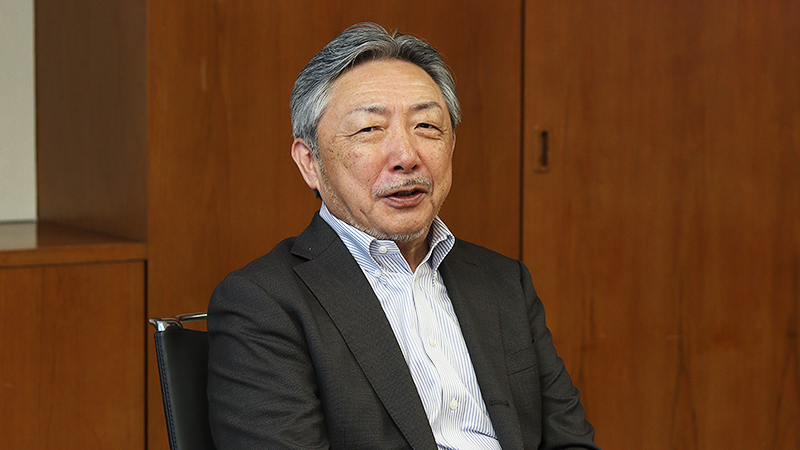
長尾昌高/1957年東京都生まれ、京都大学大学院を卒業。1983年4月株式会社石本建築事務所に入社。執行役員・常務取締役を経て、2017年4月に同社代表取締役社長に就任。