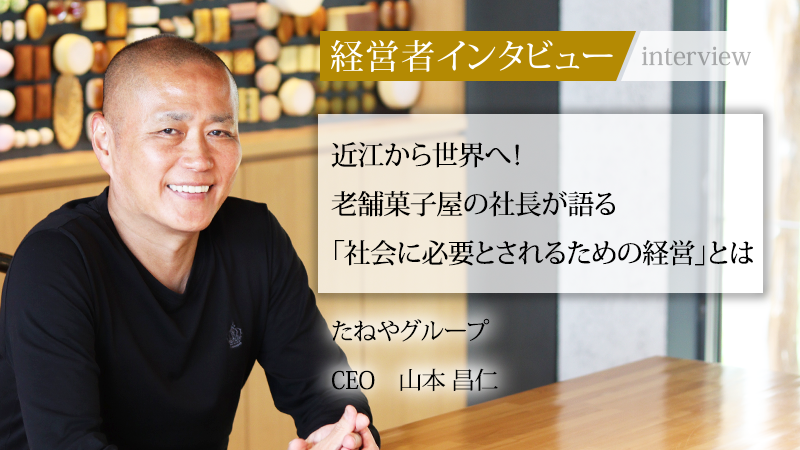
滋賀県近江八幡市に根差し、和菓子の「たねや」と洋菓子の「クラブハリエ」を展開するたねやグループ。同社の象徴といえるのが、商品を販売するだけでなく、店舗敷地の中心に田んぼを据えるなど「自然に学ぶ」という哲学を体現した「ラ コリーナ近江八幡」である。この独創的な菓子店を構想から実現させたのが、グループCEOの山本昌仁氏だ。創業者である父の背中を見て育ち、10年間の厳しい修行を経て家業を継いだ同氏に、菓子づくりへの揺るぎない信念と、近江の地から世界を見据える今後の展望を聞いた。
父の背中と10年の修業が生んだ「菓子店の道」
ーー家業を継ぐ決心をされた経緯についてお聞かせください。
山本昌仁:
私が幼い頃、父は菓子作りや東京への出店準備などで多忙を極め、ほとんど家にいませんでした。そんな父がたまに帰ってくると、いつも仕事の話を熱く語っていたのですが、私はその熱意に憧れ、「自分もこの仕事をやってみたい」と自然に思うようになり、中学生のときに会社を継ごうと決心したのです。
その思いを胸に、高校卒業後は大学へ進学せず専門学校に進み、同時に10年間のお菓子作りの修業に入りました。東京と姫路の先生に5年ずつ師事し、お菓子のイロハを徹底的に学びましたが、修業は朝から晩まで続き、想像を絶するほど厳しいものでした。
ーー修業時代、特に印象に残っている教えは何でしょうか。
山本昌仁:
「材料を無駄にするな」という教えです。お菓子を餡(あん)で包む「包餡」の練習では、失敗して材料を無駄にしないよう、クルミやピンポン玉を渡され、常に手の中で丸める練習をさせられました。生地を掬う練習も、本物の生地ではなく水で行い、一滴もこぼさない技術を習得。こうした経験から、「私たちの商売は米一粒、小豆一粒といった材料があってこそ成り立つ」ということを、骨の髄まで叩き込まれました。この学びが、今も私の菓子づくりの根幹を成しています。
ーー会社の指針となっている『末廣正統苑』には、どのような思いが込められているのでしょうか。
山本昌仁:
その根幹には、ある先生からいただいた忘れられない教えがあります。先生のお宅へうかがった際、庭の木を指してこうおっしゃいました。「この木が今日これほど美しいのは、君たちが来るからと急に頑張ったからではない。雨の日も風の日も、毎日ここで根を張り、懸命に生きてきた日々の積み重ねが、この美しい姿をつくっているんだ」と。この言葉から、特別な日に向けて取り繕うのではなく、日々の地道な努力こそが大切だと学びました。お客様の心を惹きつけるのも、こうした日々の妥協ない営みの先にある。「あるがままの姿」を追求し続けることこそ、商売の本質だと考えています。
「自然に学ぶ」ラ コリーナ構想と世界へ挑む未来
ーーその後は、どのような業務を経験されたのでしょうか。
山本昌仁:
私が入社した頃、従業員は150人ほどで、特別な役職はなく、まずは現場で餡を炊くことから始めました。その後は企画や工芸菓子の製作など、父である会長から言われたことは何でもやる「何でも屋」として、5、6年社内のあらゆる業務を経験しました。
ーー2011年に社長に就任された際、どのような思いでスタートを切られましたか。
山本昌仁:
社長になったからといって特別なことを始めるのではなく、「10年前から準備しておけ」という先代の教えを守りました。ただ一つ言われたのは「菓子店なのだから、まずはお菓子の味を自分の味に変えろ」ということです。そこで、社長交代と同時に全ての商品を見直し、パッケージから中身まで、これからの時代を見据えたものへと刷新することから始めました。
ーー社長に就任されてから、特に力を入れた取り組みについて教えてください。
山本昌仁:
社長就任時に、先代が購入していたこの土地をどう活用するかが課題としてありました。しかし、すぐに建物の設計に入るのではなく、まずこの場所の精神となるコンセプトづくりから始めたのです。
お菓子とは直接関係のない、さまざまな分野の大学の先生方を北海道から九州まで訪ね歩きました。そして3年の歳月を経てたどり着いたのが、「自然を利用する時代から、自然を師として学ぶ時代へ」というテーマです。もっとも、構想を練っていた間、地元の方々からは「土地を買い取って何もしない」と厳しい言葉をいただくこともありました。それでも、時間をかけたからこそ見つけた、このテーマに対する確信だけは揺らぎませんでした。
ーー「ラ コリーナ」という名前の由来を教えてください。
山本昌仁:
この名前は、イタリアの建築家ミケーレ・デ・ルッキさんが、「ラ コリーナ近江八幡が建つこの土地は、緩やかな丘だ」と現地に訪れた際に名付けてくれたものです。「ラ コリーナ」とはイタリア語で「丘」という意味です。そして、その土地の記憶を大切にしたいという思いから、店舗敷地の真ん中には田んぼを置きました。土こそが生命の源であり、私たち菓子屋の原点です。その土の価値をお客様に感じてほしかったからです。
銀行からは「一番売れる施設のど真ん中に田んぼを作ってどうするのか」と反対されましたが、田んぼや緑を眺めて心からほっとできる空間をつくることこそが、これからの時代に求められると考え、説得を続けました。
社会に必要とされるために、たねやが果たす社会的使命

ーー会社として最も大切にされている経営哲学は何ですか。
山本昌仁:
「社会に必要とされる企業であり続けること」です。私たち菓子屋にとって、それは何よりもまず「美味しい」お菓子をつくり続けることにほかなりません。その上で、ラ コリーナのような場を通じて自然との共生を示し、地域の方々と共に近江という土地を盛り上げていく。そうした活動を通じて、社会にとって価値ある存在でありたいと考えています。
この思いの根底にあるのが、「私たちは地球からこの場所をお借りしている」という謙虚な気持ちです。借りている以上、いつかお返しする際には、より良い状態にして返さねばならない。この考え方が、私たちの全ての事業活動の原点となっています。
ーー今後のビジョンについてお聞かせください。
山本昌仁:
二つの大きなビジョンがあります。一つは「世界へのチャレンジ」です。「日本のたねや」から「世界のたねや」を目指し、海外での出店や、現地のパートナーと組んで新たな原料開発にも挑戦したいと考えています。もう一つは「近江に来てもらうための取り組み」です。大津市で始めた「LAGO 大津(ラーゴ おおつ)」という店舗では、行政や地域の方々、学生など、多くの人を巻き込み「みんなで作る」をコンセプトにしています。ラ コリーナで得たものを独り占めせず、近江全体を盛り上げ、旅の目的地にしてもらうための活動に力を入れていきます。
編集後記
「地球からお借りしている」。取材中、山本社長が繰り返し語ったこの言葉に、同社の哲学が集約されていると感じた。目先の利益ではなく、10年、20年先を見据える謙虚な視点があるからこそ、「一番売れる場所」に田んぼをつくるという常識を覆す経営判断が生まれたのだろう。ラ コリーナは、菓子づくりの原点への感謝と、自然への敬意、そして未来への責任を体現する場所である。近江の地から世界へ、そして次代へ。たねやの挑戦は、本質的な豊かさとは何かを、私たちに問いかけ続けている。

山本昌仁/1969年、滋賀県近江八幡市生まれ。1990年に株式会社たねやへ入社し、全国菓子大博覧会での最年少受賞などを経て、2002年に株式会社クラブハリエ代表取締役社長に就任。その後、2011年に株式会社たねや代表取締役社長、2013年にたねやグループ(株式会社たねや、株式会社クラブハリエ、株式会社キャンディーファーム)のCEOに就任、現在に至る。














