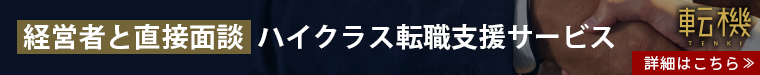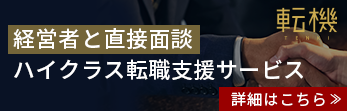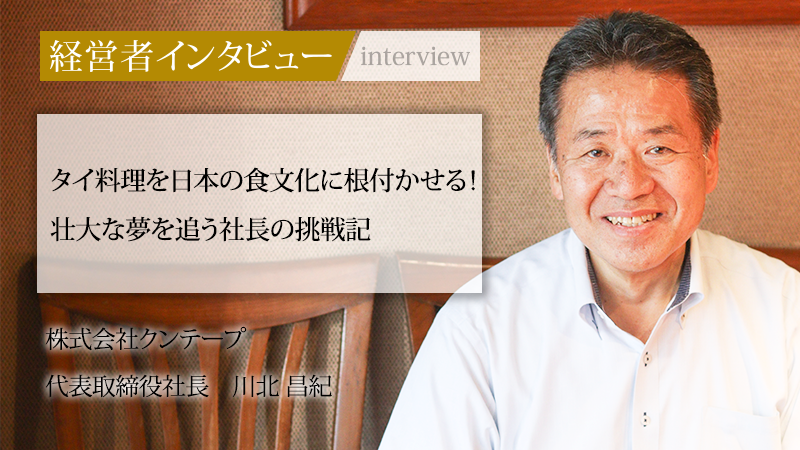
大阪・道頓堀などに関西最大級のタイ料理レストランを展開する株式会社クンテープ。生のハーブにこだわった本場の味を提供し、多くのファンを魅了している。その原動力は「タイ料理を中華料理を超える存在にしたい」という壮大な夢を掲げる代表取締役社長、川北昌紀氏の情熱である。タイでの事業に挑戦し、大阪での創業に至るまで、その道は常に波乱万丈であった。その軌跡と、タイ料理に懸ける熱い思いに迫る。
社長になる夢とナンバーワンへの決意
ーー社長を目指すようになった原点についてお聞かせください。
川北昌紀:
高校1年生の時から社長になろうと決めていました。もともと中学時代はプロ野球選手を目指していましたが、体が小さかったこともあり断念したのです。「打席に立つなら勝負したい」という気持ちが常にありました。その思いを胸に、大学時代は赤坂のクラブで働き、マネージャーも経験しました。
しかし、その世界の裏側も見る中で、性格的に自分には合わないと感じ始めていました。辞める決定的なきっかけは、私を評価してくれていた専務からのひと言です。「俺の右腕で生きていけば、苦労させへんから」。
ナンバー2の右腕、つまりナンバー3になる自分の姿が想像できませんでした。「お金に苦労してもいいから、ナンバー1を目指したい」。その思いが明確になり、その世界から完全に足を洗う決心がつきました。
人生を変えた運命のタイ料理との出会い
ーータイ料理に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか。
川北昌紀:
友人から「ヨーロッパ行くなら、タイを経由した方が安い」と教えてもらったことがきっかけです。もともとアメリカに憧れていて、アジアには全く興味がありませんでした。5年間も友人からの誘いを断り続けていたのですが、航空券が安いという理由だけで、初めてタイの地を踏むことになったのです。
最初の訪問では現地の食事に馴染めず、ホテルのチャーハンばかり食べていました。しかし、日本に帰国すると、不思議と街の活気が忘れられず「次はいつ行こうか」と考えている自分がいました。2回目の訪問で、意を決してデパートのフードコートで「ラープ」を食べました。それが衝撃的なおいしさで、そこから一気にタイ料理の魅力にのめり込んだのです。食わず嫌いだったことに気づいた瞬間です。
大阪での再起とタイ料理店のランチで行列をつくるという挑戦

ーー大阪出店までの経緯をおうかがいできますか。
川北昌紀:
最初はタイのデパートで店を借りました。しかし、現地の従業員との働き方の違いに馴染めず、わずか1か月で「このまま続けるのは無理だ」と感じました。次にタイのホテルへの出店を計画していたのですが、そのホテルの工事が突然中止になり、計画は白紙に。それを聞いて「これで日本に帰る理由ができた」と内心大喜びしました。その工事が止まらなければ、日本に帰っていなかったかもしれません。
1992年10月に大阪日本橋にクンテープをオープンしました。1999年には大阪の道頓堀にも出店しました。多くの人にタイ料理を知ってもらうには、まずお昼に選んでもらう必要があると考え、「ランチタイムに行列をつくる」と決意し、980円のランチバイキングを始めたのです。最初は客足が伸び悩みましたが、社員と二人で店の前でチラシを配り続けました。その結果、3か月目あたりからお客様が増え始め、2年後には土日に行列ができるようになりました。
「中華料理を超える存在に」タイ料理の魅力と未来
ーー現在の事業について教えてください。
川北昌紀:
タイ料理レストランを4店舗、タイ食材専門店を1店舗運営しています。そのほか、サッカースタジアムでの売店やキッチンカー、イベント出店も行っています。特に食材店では、「家庭でも本物のタイ料理を味わってほしい」という思いから、生のハーブの品揃えにこだわっています。15年前は生のタイハーブが手に入る店はほとんどありませんでした。
タイ料理は、ただ辛いだけではありません。辛さ、甘さ、酸っぱさ、そしてナンプラーの塩味。これらの味が複雑に混ざり合うことで、奥深い味わいが生まれます。また、ハーブをふんだんに使うため、健康的な料理でもあります。この奥深さこそが、多くの人を惹きつける魅力だと思います。
ーー今後の目標についてお聞かせください。
川北昌紀:
創業以来ずっと変わらず、「タイ料理を中華料理を超える存在にすること」が目標です。誰もが食べたことのある中華料理のように、タイ料理を日本の食文化に根付かせたい。そのために、お店だけでなく、イベント出店や開業支援、そしてSNSでの発信にも力を入れています。家庭でタイ料理をつくることが当たり前になれば、この目標は実現できると信じています。
編集後記
高校時代に抱いた「社長になる」という夢。その根底には、常に「自分の力で勝負したい」という強い思いがあった。食わず嫌いだったタイ料理に魅せられ、今では「中華料理を超える」という壮大な夢を追いかける。その挑戦は、単なるビジネスではない。愛するタイ料理を日本の文化として根付かせたいという、純粋な情熱に他ならないのだ。

川北昌紀/