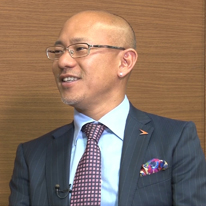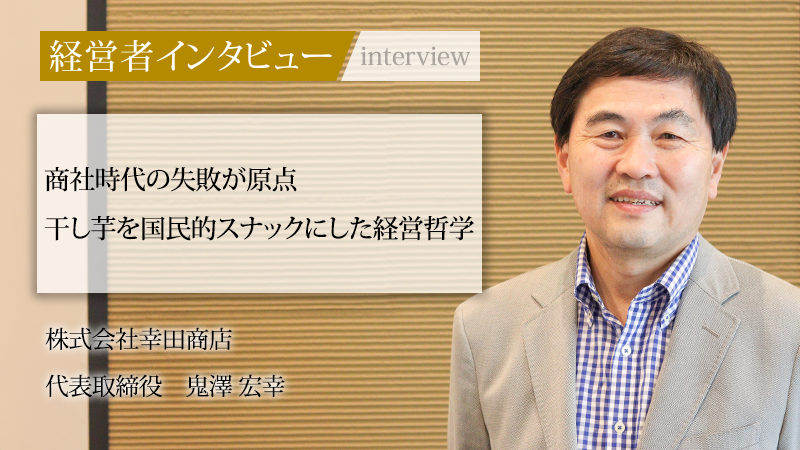
茨城県ひたちなか市を拠点に、干し芋やきな粉で日本の食卓を支える株式会社幸田商店。かつてニッチな商品であった干し芋を、若者向けの健康スナックとして再定義し市場に革命をもたらした。現在は「干し芋カンパニーから、さつまいもカンパニーへ」という新たなビジョンを掲げ、さらなる成長を目指している。その変革を牽引する代表取締役の鬼澤宏幸氏に、変化を恐れない情熱と、その根底にある経営哲学を伺った。
商社経験から見出した干し芋のポテンシャル
ーーまず、貴社を継がれる前のキャリアについてお聞かせいただけますか。
鬼澤宏幸:
大学卒業後、食品卸売業を営む国分グループ株式会社に10年間在籍し、主に海外事業に携わりました。特にサンフランシスコの合弁会社に駐在した2年間は、まさに「ミニ商社」と呼べる環境でした。カリフォルニア産のチェリーやオレンジを日本へ輸出したり、タイで製造したツナ缶をアメリカのスーパーへ販売したりしました。少人数で多岐にわたる事業を手がけた経験は、私の視野を大きく広げてくれたと感じています。
教科書からは得られない実践的な学びも数多くありました。その最たる例が、メキシコでのカボチャ栽培事業です。カリフォルニアの農業事業者と提携し、日本のカボチャの種を持ち込んで大規模な栽培に挑戦しました。しかし、想定外の大雨で収穫が間に合わず、日本へ輸送した作物をすべて腐らせてしまうという手痛い失敗を経験しました。この経験から、海外ビジネスには予期せぬリスクが潜んでいること、そして、共に事業を進めるパートナーの見極めがいかに重要かを痛感しました。
こうした成功も失敗も含めた経験のすべてが、現在の力になっています。干し芋と向き合った時に本質的な価値を見抜き、新たな可能性を切り拓く力です。
ーー当時の干し芋に、どのような可能性を感じていましたか。
鬼澤宏幸:
私が30年前に家業へ入ったとき、干し芋は非常に地味で、主に年配の方向けの商品という印象でした。冬場のスーパーマーケットで、赤い袋に入れられて細々と売られているような、ニッチな存在だったのです。しかし、世界中の食品開発に携わってきた私の目には、その常識がむしろ大きなチャンスに映りました。
干し芋は、無添加でありながら食物繊維やビタミン、鉄分などが豊富な、非常に機能性の高い食品です。この隠れた価値を最大限に引き出し、若い女性にも「健康的なおやつ」として手に取ってもらえるような見せ方ができれば、必ず新しい市場を創造できる。その仮説を証明することが、私の挑戦の始まりでした。
産地の反発を乗り越え、切り拓いた干し芋の新たな道

ーー貴社に入社されてから、どのような取り組みをされましたか。
鬼澤宏幸:
「若い世代に向けた健康食品」というコンセプト商品を実現するため、まず、海外での商品開発に着手しました。自身の商社経験が活かせると考えたからです。世界のさつまいも生産量の約7割を占める中国・山東省に渡り、1年がかりで干し芋に最適な品種を探し出しました。次に、従来の平たい形から食べやすいスティック状に変え、パッケージでも健康価値を前面に押し出しました。そして何よりこだわったのが品質です。「安かろう悪かろう」では未来がないと考え、2003年には衛生管理を徹底した自社工場を現地に設立しました。
もちろん、この挑戦は決して平坦な道ではありませんでした。日本一の産地であるここ茨城からすれば、私のやり方は「産地を潰す行為だ」と映ったようです。そのため、強い反発を受けました。しかし私には、地元だけの視点に留まっていては、干し芋産業そのものが先細りになってしまうという強い危機感がありました。目指したのは、若い世代が健康のために食べるような、全く新しい市場の創造です。それは既存の市場と競合するものではなく、干し芋という文化全体の裾野を広げる挑戦だという確信があったからこそ、迷わず突き進むことができました。
ーー事業が拡大する上で、特に大きな変化のきっかけは何でしたか。
鬼澤宏幸:
無印良品との出合いは、まさに目から鱗が落ちる体験でした。彼らが「健康食品なのだから」と、夏場に商品を展開してくれたのです。これは業界の常識ではあり得なかったことでした。「なぜ夏に売ってはいけないのか」という彼らのシンプルな視点には、頭を殴られるような衝撃を受けました。知らず知らずのうちに、私たちは固定観念に縛られていたのです。
この経験から、業界の常識を疑うこと、そして外部の新しい視点を取り入れることの重要性を改めて痛感しました。彼らのおかげで、私がずっと描いていた「一年中食べてもらう健康スナック」という世界が現実のものとなり、事業は大きく前進しました。また、東日本大震災を機にコンビニエンスストアの利用者が広がり、そこで多くの方が干し芋を手に取ってくれたことも、市場拡大の追い風になったと感じています。
中国での経験が生んだ、産地の未来を拓く両輪戦略
ーー中国で事業を展開されたことで、何か新たな発見はありましたか。
鬼澤宏幸:
改めて日本一の産地である茨城のすごさに気づきました。その価値を突き詰める中で、「人を感動させるようなブランドをつくりたい」という思いが生まれ、自ら農業にも参入したのです。幅広いお客様に向けた中国産の商品で市場の裾野を広げます。一方、茨城では「べっ甲ほしいも」のような高級品を手がけ、ブランドの頂点を高めています。この「両輪戦略」が幸田商店の強みです。
特に嬉しいのは、中国産をきっかけに干し芋を知ったお客様が、次に茨城産へと興味を広げてくれること。まさに裾野が広がるからこそ頂点も引き上げられる、という好循環が生まれています。
干し芋の枠を超える挑戦 100億円企業が描く未来
ーー会社の新たなビジョンについてお聞かせください。
鬼澤宏幸:
弊社の企業理念の1つに「健康と食の豊かさをお客様に」があります。この理念を追求し、売上100億円企業を目指すには、干し芋の枠を超える必要があると考えています。そこで「干し芋カンパニーから、さつまいもカンパニーへ」というビジョンを掲げました。原料の強みを活かし、チップスや冷凍焼き芋などにも事業を広げます。そして健康と食の領域で、新しいマーケットを創造し続けます。
ーー社長が常に新しい挑戦を続ける、その原動力は何でしょうか。
鬼澤宏幸:
「人生を楽しむ」ということに尽きます。これは私個人の信条であると同時に、会社が掲げる大切なバリューの一つでもあります。何もしないでじっとしているのではなく、常に新しい市場へ挑戦し、何かを創り上げる。その結果としてお客様に健康や美味しさといった喜びを届け、それが自己実現にもつながっていく。そのプロセス全体が、最終的に人生を豊かにしてくれるのだと考えています。変化の激しい時代ですが、それは私たちにとってピンチではなく、むしろ新しい何かを生み出すチャンスだと捉えています。
ーー最後に、社長として最も大切にされていることを教えてください。
鬼澤宏幸:
「うまくいっている時こそ、その変化に気づきにくくなる」という危機感を常に持つことです。だからこそ、「このままではいけない」と、あえて言い続けます。それが会社の未来を考え、変化を導く社長の最も重要な役割だと考えています。自ら変化を起こし続けられるかどうか、それが全てだと思って会社を経営しています。
編集後記
鬼澤氏の言葉から伝わるのは、冷静な分析力と、それを上回る熱い情熱だ。「うまくいっている時こそ危機感を持つ」という哲学は、変化の激しい現代を生きる全てのビジネスパーソンに深く響く。伝統的な商品に新たな価値を見出し、常識を覆して市場そのものを創り上げた幸田商店の挑戦は、未来を切り拓くための力強いヒントを与えてくれる。

鬼澤宏幸/1962年茨城県生まれ。1984年、明治大学卒業後、国分グループ株式会社に入社。1994年、家業である株式会社幸田商店に入社。1999年より同社代表取締役社長に就任。「ほしいも学校」を通じて干し芋の魅力発信を行っている。