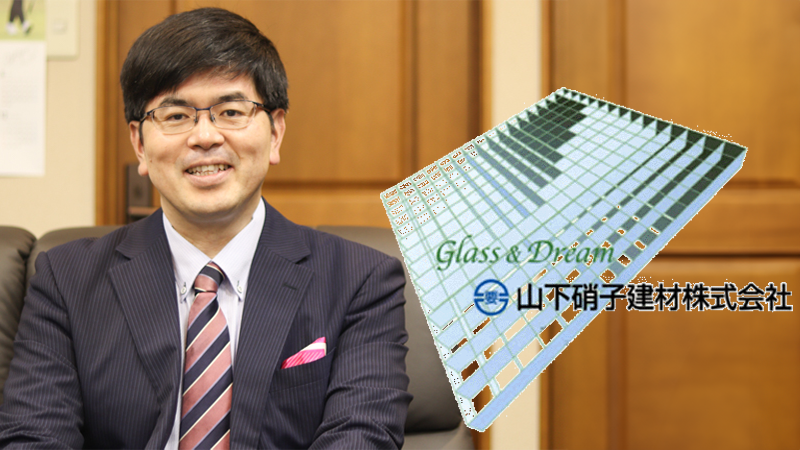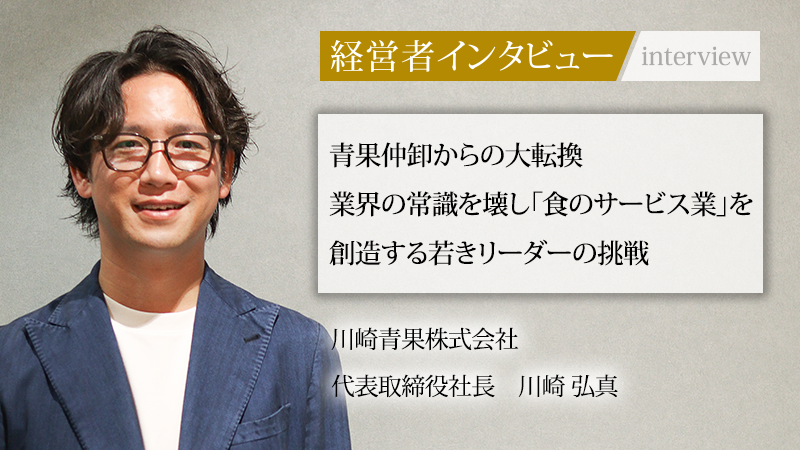
1926年の創業から長い歴史を刻む、川崎青果株式会社。同社は青果卸売業の革新を続けている。従来の市場流通に依存した仲卸の枠を超え、生産者との直接連携や食育事業、船舶への食材供給といった多角的なサービスを展開する。当初、家業を継ぐ意思は無かったという代表取締役社長の川崎弘真氏は、28歳で社長に就任。逆境を乗り越えV字回復を成し遂げた。若きリーダーの覚悟と、社員の挑戦を育む独自の組織づくりの秘密に迫った。
大人たちの決まり文句を覆した父の言葉
ーー貴社に入社することになった経緯を教えてください。
川崎弘真:
もともと家業を継ぐことは、全く意識していませんでした。私が物心ついた頃には父は経営の一線から退いていたため、家業をほとんど知らずに、ごく普通の就職活動をしていました。その際に、周囲の大人たちが「学生は良いよな、今のうちに遊んでおけ」と口をそろえて言う中で、父だけは「大人は最高におもしろいぞ」と笑いながら言い放ったことが、とても衝撃的で、この会社で働こうと決めました。
ーー入社後は、どのようなご経験をされましたか。
川崎弘真:
最初は、早朝3時から荷物運びや配送を行い、9時になったらスーツに着替えてお客様のところに飛び込む。若さと体力があったからできた働き方ですが、週末に学生時代の友人と食事をするときには、いつも座ったまま寝ちゃってましたね。
ーー社長就任のきっかけは何だったのでしょうか。
川崎弘真:
27歳のとき、会社の業績は良かったのですが「会社はどこに向かっていくのか」や「社会にどんな価値を提供できているのだろう」という、今でいえばPurposeやVisionが社内の共通認識として見えないことに危機感を覚えて、それは誰かが与えてくれるものじゃなく「自分が引き受けよう」と。すぐに会長であった父に電話して「社長をやらせてほしい」と伝えました。「いいね、では来期から社長ね」と軽い返事で決まりました(笑)。
3期連続赤字からのV字回復 若き社長の覚悟と構造改革

ーー社長就任後、どのようなことに苦労されましたか。
川崎弘真:
社会人経験5年で営業係長でしたので、経営の何も分からず、肩書だけ社長になったものですから、就任1期目にして会社は赤字に転落し、それから苦労の連続でした。2期連続で赤字になったときは精神的に追い詰められ、プレッシャーで食べ物が喉を通らなくなったこともあります。社長という立場から逃げられない重圧に苦しみました。
その苦しい状況を乗り越えられたのは、社員たちの存在があったからです。社長就任当初は年上の社員からの反発もありましたが、私が3年間もがきながら手探りでも前進しようとする姿をメンバーは見てくれていたのだと思います。そこから徐々に共感が生まれ、チームの一体感が育まれていきました。
黒字化のため、3年目に構造改革を断行しました。あらゆる経費を洗い出して削減し、私自身の給与も引き下げました。幹部や昔からの社員にも頭を下げて回り、報酬の引き下げに同意してもらいました。何もできない社長の私の、初めての経営者としての仕事でした。そのかいあって、4年目に本当にわずかな黒字を出せたときの喜びは、今でも忘れられません。
ーーV字回復後の会社の進化において、ターニングポイントは何でしたか。
川崎弘真:
今では当時の売上の3倍以上まで拡大しましたが、オープンイノベーション(※1)の考え方を取り入れ、閉鎖的な業界の固定観念を捨てたことです。従来の流通、従来の販売チャネル、仲卸業という枠組みからの脱却を進めました。今では生産者の方々と直接組の取り組みも広がり、独自の流通を持つ「専門商社」として事業展開しています。
(※1)オープンイノベーション:企業が新たな価値を創出する際に、自社の資源だけでなく、社外の組織や機関が持つ技術やアイデア、ノウハウなどを積極的に活用するイノベーション手法
青果仲卸から食のサービス業へ 業界の常識を覆す多角化戦略
ーー多角化戦略について、具体的な事業内容を教えてください。
川崎弘真:
弊社ではいくつかの事業(ブランド)を展開しています。まず、外食産業や給食産業を中心に総合食材納入を行う「Sain Vivre(サン・ビブレ)」。食材を活かしたメニュー提案や、神戸市の食育サポーターとして保育園などでの食育活動も担っています。
次に「HAIND(ハインド)」は、人手不足に悩む農業産地の作業負担を軽減するため、野菜の選別やパック詰め、一次加工を代行しています。この事業は就労支援事業所ともタッグを組み、働く場の提供にも繋がっています。「マリンサプライ事業部」もあり、港町である神戸の立地を活かし、世界の船舶に食糧品を供給しています。
これらに加え、今後は良質な商品をストーリーと共に届ける個人消費者向けブランドも立ち上げる計画です。
挑戦と失敗がキャリアになる 成長を止めないための組織づくり
ーー貴社の人事制度について教えてください。
川崎弘真:
社員の挑戦を後押しするため、「単年度制」を導入しています。これは評価が翌年に影響しない制度で、失敗を恐れず挑戦できる環境です。また、本人の意欲を尊重しています。社長の私しか見ない人事アンケートでは「総務に興味がある」や「こんな新しいビジネスをしてみたい」と書けば、社歴や経験を問わずチャレンジを推奨することもあります。
2026年春からは、新卒社員が入社当日から経営者として活動するチームをつくる予定です。上司もルールもない環境で、ゼロからイチを生み出すスタートアップを経験してもらうのが狙いです。与えられたことをこなすより、答えのない問いに取り組む方が仕事は面白いと考えているからです。
事業の数だけ社長が生まれる 「個」が輝く次の100年の組織図
ーー貴社が掲げる「100年目のベンチャー企業」とは、どのような意味ですか。
川崎弘真:
弊社は創業100年を迎えますが、その風土やカルチャーは老舗企業というよりベンチャー企業に近いと思います。今でも若いメンバー中心に、新しい挑戦や実験を繰り返しながら進化していますし、メンバーの成長こそが会社の成長であるという考え方から自燃し自走できる組織運営に注力しています。
ーー5年後、10年後について、どのような展望をお持ちですか。
川崎弘真:
将来的には、今の事業部をそれぞれ独立させることが理想です。そして、事業部長たちがそれぞれ社長になる。私はホールディングス会社の立場で彼らを支えたいと考えています。もっと世の中に、「経営者」というキャリアの選択肢を増やしたいのです。
会社は私のものではなく、社員みんなのものです。だからこそ、社員には会社を大いに活用して、お金や経験を得て、それぞれの人生を充実させてほしいと願っています。実際に、社内スタートアップした事業を社員に譲って独立させた実例もすでにあります。社長は特別な存在ではなく、誰もが目指せる選択肢だと証明していきたいです。
編集後記
自ら「地獄だった」と語る社長就任後3年間の赤字経営。その壮絶な経験が、川崎氏の血肉となり、会社の羅針盤を形づくっていることが伝わってくる。特筆すべきは、その経験を、社員が同じ轍を踏まぬよう挑戦を歓迎する「制度」に昇華させている点である。「会社は自己実現のためのツールである」と語る同氏の下で、次代を担う経営者が続々と生まれるに違いない。

川崎弘真/1984年神戸生まれ。2007年、立命館大学経済学部を卒業後、新卒で家業である川崎青果株式会社に入社。28歳の若さで代表取締役社長に就任。グループ会社の立ち上げや新規事業を次々と展開し、創業100年企業ならではのイノベーションを大切にしている。現在は3社の代表取締役を務める傍ら、一般社団法人神戸青年会議所の副理事長、神戸中央青果卸売組合で理事なども経験し、青果業界のみならず、神戸の発展にも寄与している。