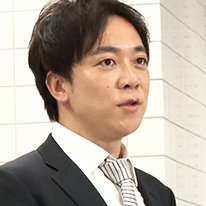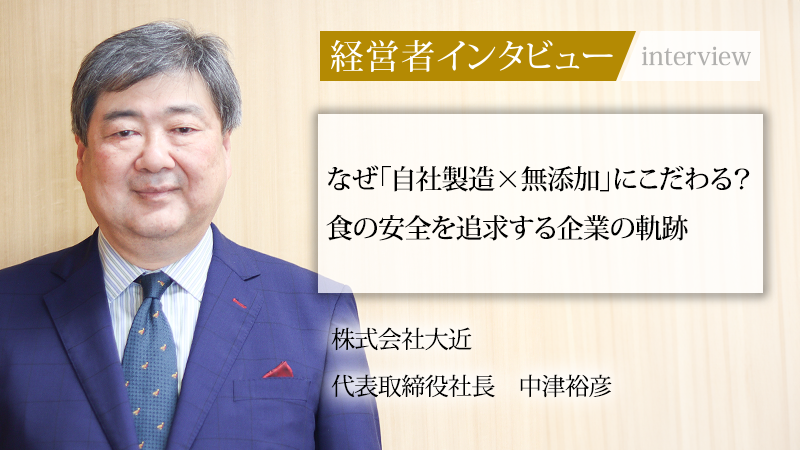
現代社会において「食の安全」への関心はますます高まっている。そんな中、スーパーマーケットを主業務としながらも、食品添加物を極力使用しない商品の開発を徹底し、自社工場での製造にまで踏み込む企業がある。株式会社大近だ。「最愛の家族、子どもに安全安心な食品を」という強い信念のもと、高級スーパーよりも高品質なスーパーを追求してきた。
本記事では、役員として入社してから行った管理改革から社長就任後の戦略などの中津社長のこれまでの歩みと、新規事業の立ち上げや次世代の育成、外販への挑戦といった未来への展望に迫る。
「食の安全」への揺るがぬ原点と自社製造への道
ーー貴社の食品添加物を極力使わない方針はどのような経緯で確立されたのですか?
中津裕彦:
創業者の代から、添加物を使わない商品づくりへの意識はありました。しかし、戦後の大量生産が主流の時代で、添加物を使わない安全な食品を製造するメーカーは非常に少なかった。ならば「自社でつくろう」という精神で、工場を立ち上げ、様々な商品を開発してきたと聞いています。
添加物を使わない商品づくりに力を入れるきっかけになった出来事があります。1978年、当時の副社長が、完成したばかりのうどん工場を視察した際、うどんづくりに使うpH調整剤がこぼれたことで、床や側溝が黒く変色しているのを目にしたそうです。
副社長が工場長に対し、「この工場でつくったうどんを、自分の子どもや家族に食べさせたいか?」と問いかけたところ、返ってきたのは「正直、毎日は食べさせたくはありません」という答えでした。
副社長は「家族に食べさせたくないものを作って、お客様に売るとは何事か!」と激怒し、ここから、添加物を使わない食品製造に注力することになったのです。
(※)食品添加物不使用への挑戦について
ーー取り扱う商品に関して、具体的なこだわりを教えていただけますか。
中津裕彦:
私たちは高級スーパーを目指しているわけではありません。目指すのは、どこよりも品質の高いスーパーです。私たちのこだわりは、お客様、とりわけ未来を担うお子さんたちに、本当に体に良いものを届けたいという一点に尽きます。添加物を極力排除し、素材本来の味を活かした商品を提供することが、真の高品質だと考えています。

変革を恐れず挑んだリーダーシップの軌跡と信念
ーー大近へ入社されてからの取り組みについておうかがいできますか。
中津裕彦:
役員になったのは社長就任の3年ほど前で、その期間に管理面の改革に注力しました。人事制度で目指したのは、頑張った人が正当に評価されステップアップしやすく、失敗しても再チャレンジしやすいような、柔軟性のある制度づくりです。また、評価基準を明確にし、昇降格の透明性を高めることを重視しました。
この人事改革は、努力が報われる仕組みが構築でき、社員のモチベーション向上に良い影響を与えたと思います。目標が明確になり、仕事へ真剣に取り組む社員が増えたと感じています。さらに、失敗を恐れず挑戦できる風土が醸成され、組織全体の活性化にも貢献しました。
販管費削減については、取引先との条件見直しや相見積もりの徹底など、多岐にわたる施策を実行しました。これらの実績が、徐々に社員からの信頼を得ることに繋がったと感じています。
ーー社長就任後、どのような取り組みに注力されましたか。
中津裕彦:
社長に就任してからは、営業面により力を入れ、私たちが最も大切にしている「添加物を極力使わない商品」のコンセプトを一層ブラッシュアップしました。自社製品はもちろん、仕入れ商品についても、原材料の細部にまで目を配っています。また、キャリーオーバー(※1)にも注意を払うようになりました。
こうした目に見えない部分までこだわり、お客様に安心してお選びいただける商品を増やす努力を続けています。また、プライベートブランドのロゴを分かりやすいものにするなど、お客様への訴求力も高めています。
(※1)キャリーオーバー:食品の製造に使用する原材料に含まれていた食品添加物が最終製品にもそのまま微量に存在する場合のこと
新規事業「KINARIYA」始動と次世代への襷

ーー「最愛の家族、子どもに安全安心な食品を」という思いについて、詳しく教えてください。
中津裕彦:
添加物が多く含まれる食事を続けていると、アレルギーや様々な不調の原因になり得ると言われています。特に成長期のお子さんへの影響は無視できません。病気になってから医療費をかけるよりも、日々の食事に少し気を使うことで健康を維持する、「予防としての食」という考え方が非常に大切だと考えています。
私たちの商品を通じて、お客様が医者いらずの健康な食生活を送るお手伝いができれば、それに勝る喜びはありません。
ーー新規事業「KINARIYA」がスタートした経緯をうかがえますか。
中津裕彦:
既存のスーパーマーケット事業とは異なる新しい柱を育てたいという思いから、新規事業として「KINARIYA(きなりや)」というブランドを立ち上げました。「KINARIYA」は店内で丁寧にとった「おだし」、心とからだを整える「発酵調味料」、自然のめぐみを感じる「四季」、この三つを大切にしている惣菜店です。
「KINARIYA」の立ち上げは若手が担っており、新しいことへチャレンジしてほしいという思いからスタートしました。部署の垣根を越えて若手社員が集まり、ブランド名や商品企画から主体的に取り組んでいます。彼らの柔軟な発想と行動力に大いに期待しています。

ーー今後の展望について、お聞かせいただけますか。
中津裕彦:
今後、注力したいのは、次世代育成と商品力の向上です。次世代育成については、私が社長に就任する前から現在まで継続的に取り組んでいます。例えば、以前「青年塾」という志を持った人間を育てる塾に社員を派遣したり、月一回の部署長会議で「致知」という雑誌を用いた人間学を学ぶ勉強会「木鶏会」を実施したりしています。これらは人間教育に重きを置いた取り組みです。今後は、こうした学びの機会をさらに広げていきたいと考えています。
商品力の向上については、まず調味料などに力を入れ、内向きだけでなく外にも売れるレベルに引き上げていく方針です。
現在、工場で生産している商品は、お客様にお届けできる賞味期間が短いものもありますが、これを改善し、日持ちする商品を増やすことで外販の可能性を広げたい。自社で企画したプライベートブランド商品を他のスーパーなどにも展開することで、私たちのこだわりをより多くの方に知っていただき、会社の認知度向上にも繋げていく所存です。
編集後記
中津社長がインタビュー中に語った「損得より善悪で物事を判断する」という言葉は、会津藩の「什の掟」にある「卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ」という教えに通じる。そのぶれない経営哲学こそが、株式会社大近の信頼の礎となっているのだろう。添加物フリーにこだわりつつ外販可能な商品開発を目指すという新たな挑戦は、同社の理念をさらに社会へと広げていくに違いない。その実直な歩みに、今後も注目していきたい。

中津裕彦/1962年京都市生まれ。学習院大学法学部卒業。1987年、ユニバーサル証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)に入社。1991年に共栄火災海上保険入社。その後、2000年に株式会社大近へ入社し、2013年に代表取締役社長に就任。現在に至る。