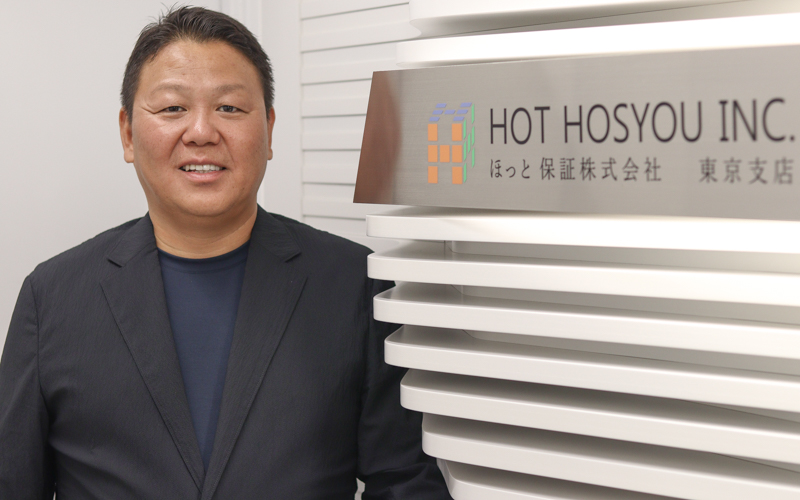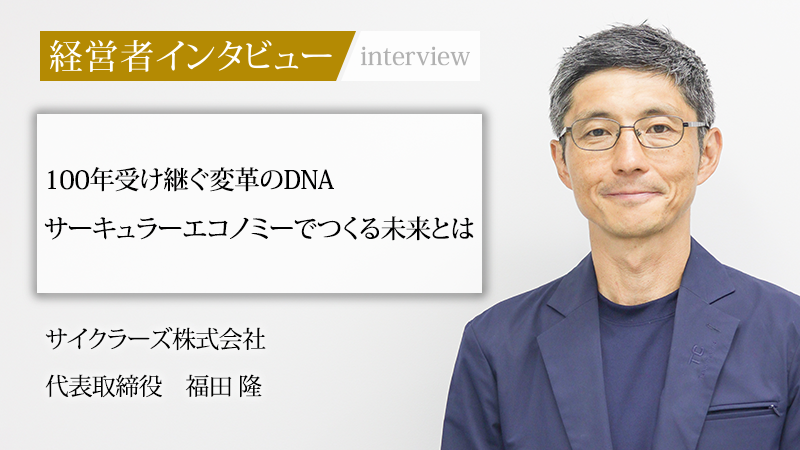
1902年創業の東港金属を中核企業とするサイクラーズグループは、資源リサイクルと循環型経済の実現に向けたソリューションを軸としてきた。時代の変化に応じて挑戦を続けてきた企業である。祖父、父から受け継いだ「変革のDNA」を胸に、福田隆代表取締役は父の急逝を受け、28歳という若さで事業を継承した。就任直後の赤字から、果敢な改革により、会社をV字回復させた。その軌跡と未来への展望を、サイクラーズ株式会社代表取締役、福田隆氏に聞いた。
飛び込み営業から大型投資へ 会社の未来を切り拓いた決断
ーー貴社に入社される前までのご経歴についておうかがいできますか。
福田隆:
まず、総合精密部品メーカーのミネベア(現・ミネベアミツミ)で、営業部門に配属となり、大手製造メーカーへの営業活動を行う中で、顧客と共に工場のオペレーションや品質管理、海外でのビジネスをつぶさに見ることができました。その後、シビアな実力主義の世界を求め、外資系のEMCジャパン(現・デル・テクノロジーズ)に転職し、合理的な営業手法などを身につけました。
これらの経験を通して気づいたのは、基本的なことが意外と徹底されていない人が多いということです。だからこそ、当たり前のことを徹底的に、そして確実にやり抜くだけで評価され、活躍できる。お客様や社内から依頼されたことは絶対にやりきる、というこの単純なことが、仕事で成果を出す上でとても重要だと実感しました。
ーー貴社入社後、まずどのようなことから始められたのですか。
福田隆:
当初は現場作業から全て経験する予定でしたが、大手顧客との取引がなくなる事態が発生し、急遽、営業として新規開拓をすることになりました。当時はまだインターネットも普及していなかったので、飛び込み営業を重ね、少しずつ会社の売上を回復させていきました。
そんな中、父が急逝し、他に引き受け手もいなかったので「私がやります」と、突然社長就任が決まりました。私が28歳のときです。
そして、社長に就任して初めて会社の損益計算書(※1)を見て愕然としました。父が亡くなった翌月の営業利益が、マイナス1500万円だったのです。これを知ったときは正直、生きた心地がしませんでした。
しかし原因は根本的な売上不足だとはっきり分かっていたため、自ら先頭に立って営業活動にさらに注力しました。その結果、翌月には黒字化を達成し、そこから約5年間、連続で黒字を達成することができました。
(※1)損益計算書:1年間の経営成績を示す決算書
ーーその後の会社の拡大において、ターニングポイントとなった出来事は何でしょうか。
福田隆:
2008年の千葉工場の立ち上げです。会社の未来を考えた時、拡大のためには広い土地と大きな設備が不可欠だと確信していました。リーマン・ショックの時期と重なりましたが、自動車を丸ごと破砕できるほどの能力を持つ大型プラントを導入するという大きな投資に踏み切りました。この決断によって、弊社の処理能力とリサイクルの品質は飛躍的に向上し、成長の大きな礎となりました。
祖業の進化と新たな挑戦を支える「変化を受け入れる力」

ーー現在のグループ事業内容について詳しく教えていただけますか。
福田隆:
弊社の事業は、大きく二つの軸で成り立っています。一つは、祖業でもある金属スクラップのリサイクルや産業廃棄物の処理を行う「資源リサイクル事業」。もう一つは、サーキュラーエコノミー(※1)を実現するためのツールやアプリケーションを提供する「サーキュラーソリューション事業」です。
グループ会社は現在10社あり、多角的に事業展開しています。たとえば、クレディセゾンとの合弁会社ではOA機器のリユース事業を、また別の会社では業界向けの電子契約サービス、企業向けのリユースプラットフォームサービスなどを開発・提供しています。
ーー貴社が「サーキュラーエコノミー」を追求する背景について教えてください。
福田隆:
「サーキュラーエコノミー」という言葉が社会で聞かれるようになったのは比較的最近ですが、私たちはこの概念に大きな可能性を感じています。単なる道徳観念としてのリサイクルは、なかなか社会に広がりません。しかし、「エコノミー(経済)」とあるように、経済的な合理性を持って循環の仕組みが成り立てば、一気に普及が進みます。私たちは、そうした経済合理性のある循環モデルを追求することが、持続可能な社会の実現につながると考えています。
ーー創業から100年以上続く原動力となっている企業文化や強みは何でしょうか。
福田隆:
変化を恐れない、ということです。弊社は1902年の創業ですが、歴史があるからといって特定の社是や家風に縛られることはありません。曽祖父から父、そして私に至るまで、それぞれの代がその時代に必要だと信じることに取り組んできました。祖父が工場の移転を決断し、父が産業廃棄物事業を始めたように、常に変わり続けてきた。この「変化を受け入れる力」こそが、弊社の最大の強みだと考えています。
(※1)サーキュラーエコノミー:全世界で提唱されている、製品や素材、資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物を可能な限り資源転換することで、資源利用に伴う環境負荷を低減する経済システム。
「選ばれるリサイクラー」として描く未来
ーー今後のビジョンと、注力していく取り組みについて教えてください。
福田隆:
今、国は「資源循環経済への転換」を国家戦略として掲げ、リサイクルの質がかつてないほどに問われています。たとえば、自動車に使われた鉄やプラスチックを、再び自動車に利用する「水平リサイクル」のような極めて高度な技術が求められる時代です。この要求に応えるためには、私たち自身が技術力、品質管理能力、そして企業規模を向上させていかなければなりません。大手製造業のお客様とのアライアンスを強化し、「選ばれるリサイクラー(※2)」になることが不可欠です。
(※2)リサイクラー:再資源化事業者
ーー最後に、サイクラーズが目指す理想の循環の形についてお聞かせください。
福田隆:
弊社では、環境負荷が最も低い方法から順に循環させていく「カスケード式」という考え方を大切にしています。まずはそのまま再利用する「リユース」。デザインの力で廃棄されたものの価値をさらに高める「リメイク」、次に部品を取って活用する「パーツリユース」。それがだめなら素材として再生する「マテリアルリサイクル」、最終的にはエネルギーとして回収する「サーマルリカバリー」。このカスケード式の考え方に基づき、グループ全体であらゆる循環の形を追求し、残存価値を最大化することで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献していく。それが私たちの使命です。
編集後記
1世紀以上にわたり、時代の要請に応え、事業を変革し続けてきたサイクラーズ。その歴史は、未来を見据えた『決断の歴史』でもある。父の急逝、28歳での社長就任、月1500万円の赤字という逆境を乗り越えた経験は、福田氏の言葉に揺るぎない説得力を与える。「変化を恐れない」というDNAは、今や「サーキュラーエコノミーを追求し、持続可能な社会をつくる」という明確なパーパスと結びついた。そして、社会をより良い方向へ導くための羅針盤となっている。同社が描く循環の未来に、大きな期待を寄せたい。

福田隆/東京都出身。1996年、成城大学経営学部卒業後、ミネベア株式会社(現・ミネベアミツミ株式会社)に入社。その後外資系コンピュータ企業の株式会社EMCジャパン(現・デル・テクノロジーズ株式会社)に勤務。2002年、家業を継ぐために東港金属株式会社(現・サイクラーズのグループ会社)入社。先代社長の急逝に伴い、半年後、同社代表取締役に就任。現在は、事業会社を統括するサイクラーズの代表を務める。ビジネスによるサーキュラーエコノミーへの貢献を目指し、事業展開を行う。