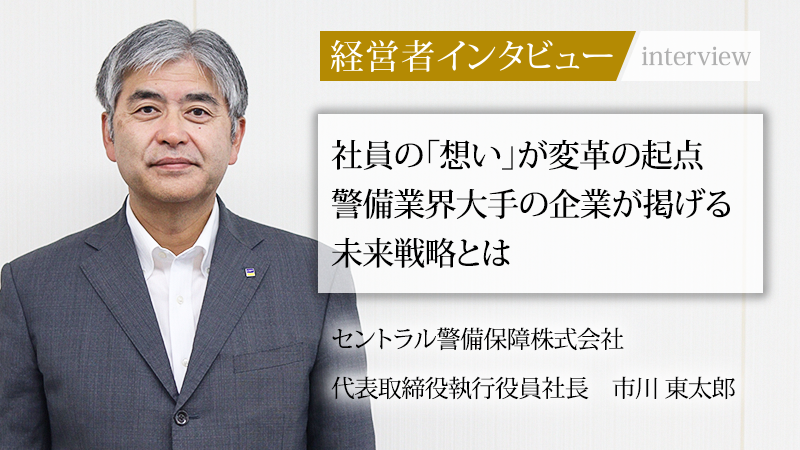
労働人口の減少やテクノロジーの進化など、警備業界が大きな変革期を迎える中、業界大手のセントラル警備保障株式会社(CSP)は、新たな成長戦略を力強く推進している。その舵取りを担うのが、2024年に代表取締役執行役員社長に就任した市川東太郎氏だ。東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)で副社長まで務め上げた同氏は、鉄道という巨大インフラの現場で一貫した哲学を培ってきた。本記事では、市川氏のキャリアの原点から、CSPで目指す未来像、そしてその羅針盤となる中期経営計画の核心に至るまでうかがった。
巨大インフラで培った「正しさ」を貫く仕事の哲学
ーーまずは、キャリアの原点についてお聞かせください。
市川東太郎:
もともと鉄道が好きで、列車のダイヤ作成や運行管理といった仕事に憧れてJR東日本に入社しました。計画部門に進むことが前提でしたが、まずは現場に出て経験を積ませていただきました。私自身、現場の温度感や肌感覚を知らずして良い計画は立てられないという想いが強くありました。そのため、キャリアの最初に車掌や運転士としてお客様と直接触れ合い、実務を経験できたことは非常にありがたかったです。この経験が、その後のあらゆる業務の礎となっています。
現場での実務経験を経てから管理職になりましたが、部下や同僚と接する際は、相手への敬意を忘れないことを常に意識していました。指示や伝えるべきことは、相手の年齢や役職にかかわらず、誰に対しても同じ内容を公平に伝えます。そうした関わりの中で、より良い方向を見い出せたり、社員が成長したりする変化を感じられる瞬間に、何よりの喜びを感じていました。
ーーこれまでの大きなターニングポイントについてお聞かせください。
市川東太郎:
現在の「高輪ゲートウェイシティ」の用地生み出しのための、線路配置の見直しの仕事は印象深いものがありました。ここはかつて広大な車両基地でしたが、上野東京ラインの開業やブルートレインの廃止という環境の変化に適切に対応させるとともに、鉄道のためには必要がなくなった土地を捻出するという仕事でした。私は、最終チェックの前にこの仕事を引き継いだのですが、その案では現場の運用上、将来にわたって大きな負担を残すことが明白だったため、そのまま進めることはできないと感じていました。すでに最終決定間近でしたが、100年先まで使われる施設だからこそ、ここで妥協はできませんでした。
会社の幹部をはじめ関係者など、さまざまな立場の方から意見が出ます。その中で会社として進むべき正しい道を見極めなければなりません。その場しのぎの判断は、後で必ず大きな問題になります。20年近くにも及ぶ現場第一線と企画・計画の実務の経験を通して「誰が言ったか」ではなく「何が正しいか」という価値基準で物事を判断し、対応する姿勢が徹底的に鍛えられていたことが、私にとっては非常に大きな力になっていました。常に「何が正しいのか」を自問自答し、社員にも納得できる理由を丁寧に説明することを大切にしてきました。
理想的な線路配置案を描き、多くの関係者に協力を得ながら上司に説明をしたところ上司も理解してくれて、役員の皆さんを説得していただき、最終的に計画を良い姿に変更することができました。より良いものであれば、たとえ一定程度決まったことであっても変更を受け入れてくれる、そういう会社の価値観に深く感謝するとともに、自分もそういう会社運営をしたいと強く思ったターニングポイントとも言える経験です。
ーー役員を歴任される中で、大切にしていた仕事への価値観はどんなものですか。
市川東太郎:
特定の役職に就きたいという目標を持ったことはありません。ただ、目の前の仕事に対して「理想の形はこうあるべきだ」「このレベルまで到達させたい」という想いは常に持ち続けてきました。その時々の立場で、どうすれば物事をより良い方向に導けるかを考え、実行してきた結果が、今につながっているのだと思います。
新たな挑戦の舞台で見出した成長への絶対的な確信

ーー貴社の社長に就任された経緯をおうかがいできますか。
市川東太郎:
JR東日本は弊社の株式を保有しており、これまでも経営層を輩出してきました。社長就任の話を受けた際に、私自身は「まだまだ仕事を通じて社会に貢献したい」という想いがありましたので、ありがたくお受けしました。鉄道と警備は、現場第一線の社員がそれぞれ自分の役割をしっかりと果たすことでサービスが完結するという点で事業構造が似ています。その共通点が、今回の就任につながったのではないかと考えています。
ーー社長に就任されて、貴社の将来性についてどう感じられましたか。
市川東太郎:
まず感じたのは、社員が非常に真面目に仕事に取り組んでいることです。これは大変心強く感じました。そして、CSPには決まったことを確実にやり遂げる驚くほど高い「遂行力」があります。これは長い歴史の中で培われた素晴らしい強みです。一方で、今後はITやAIなどの最新技術と、この強力な現場力をいかに連携させていくかが成長の鍵となります。この二つをうまく融合させることができれば、CSPはさらに強い会社になれると確信しました。
「カスタムメイド」思想で実現する独自の価値提供
ーー貴社事業の特色と、競合他社との違いについて教えてください。
市川東太郎:
弊社の強みは「カスタムメイドシステム」という考え方にあります。これは、お客様のニーズに合わせ、最適な技術や製品を外部から柔軟に組み合わせて独自の警備システムを構築するものです。自社ですべてを開発するのではなく、世の中にある最高のものを組み合わせます。そうすることで、お客様にとって真に価値のあるサービスを提供できるのです。これは、技術の目利きと、それらを統合する力が内在する弊社ならではの強みです。
ーー警備業界が直面している課題と、それに対する貴社の取り組みをお聞かせください。
市川東太郎:
労働人口の減少は業界全体の差し迫った課題です。これに対し、弊社はAIを活用した画像解析技術などを積極的に導入しています。従来は人が行っていた定型的な監視業務などをシステムに代替させます。それにより、人は人にしかできない、より付加価値の高い業務やお客様とのコミュニケーションに集中できる環境をつくり、サービスの質を落とすことなく、効率的な警備体制を構築することを目指しています。
ーー貴社独自の取り組みやサービスはありますか。
市川東太郎:
「高輪ゲートウェイシティ」では、エリア内に立つ4棟の大規模ビルを含めエリア全体の警備を弊社が一元的に担っています。弊社独自に開発したセキュリティプラットフォーム「梯」を導入し、各ビルの防災センターや監視カメラの情報を「梯」に集約させ、エリア全体を俯瞰して管理します。これが「エリアマネジメント」という新しい警備の形です。この仕組みにより、何か事案が発生した際に最も近くにいる警備員を自動で選定・指示を行い、迅速に派遣するなど、効率的かつ効果的な対応が可能です。この大規模なエリア警備の実績は、今後の弊社の大きな武器になると考えています。
社員の「想い」を起点とするボトムアップ型の経営変革
ーー中期経営計画について詳しくお聞かせください。
市川東太郎:
社員一人ひとりの「こうしたい」「こうなりたい」という想いを起点に、従来の警備の在り方そのものを変革していきます。それが中期経営計画「想い 2030 〜連携して実現する〜」の核心です。計画名に「想い」を掲げたのは、全ての変革は社員の「想い」から始まると考えているからです。この計画は、各部署からボトムアップで集めたアイデアと私が現場で直接聞いた声、そして経営としてのビジョンを融合させて策定しました。皆の想いが詰まった約束事でもあります。
そんな想いを結集して取り組む中心的なテーマが「基盤事業の変革」です。もはや「常駐警備」や「機械警備」といった旧来のカテゴリーで分けて考える時代ではありません。AIやクラウドなどの新しいツールを駆使し、それぞれの長所を組み合わせることで、お客様と私たち双方にとって最適で効率的なサービスが生まれるはずです。高輪の事例のように、常駐と機械の概念が融合した警備の形が、これからのスタンダードになっていくでしょう。
そしてもう一つの大きな柱が、「ソリューションの提供」へのシフトです。これまではお客様から発注をいただく、いわば下請けの立場が中心でした。しかし、それでは価格競争から抜け出せません。これからは、私たちが持つ知見や技術を基に、お客様の課題を解決する「ソリューション」を自ら提案していきます。より上流の立場で価値を提供できる存在へと進化していくことも、この計画の大きな目標の一つです。
ーー具体的にはどのような社員のアイデアが反映されているのですか。
市川東太郎:
たとえば、現金などを輸送する「輸送警備」の部門では、将来的にキャッシュレス化で物量が減少していくことが予想されます。そこで、部門のメンバーに「自分たちの持つノウハウで、他に何ができるか」という問いを投げかけ、アイデアを出してもらいました。
その中から、今までの枠組みを超えて考えることで、お客様の業務全体の負担を軽減する新しいサービスの構想が生まれました。それをそのまま計画の絵として採用したのです。自分たちの未来は自分たちで考える。その姿勢を尊重し、後押しすることが重要だと考えています。
ーー計画を推進する上で、技術面ではどのような取り組みを重視されていますか。
市川東太郎:
技術面では、AI時代を見据えたシステム全体の再構築が急務です。これまで社内のシステムは、各部署がそれぞれの課題に応じて個別最適で導入してきた側面がありました。しかし、それでは場当たり的な対応になりがちです。今後は会社全体のデータを連携させ、有効活用できる基盤を整えなければなりません。正しいデータがなければ、AIも正しい答えは導き出せないからです。このデータ基盤の整備は、今後数年間で最も重要な課題の一つです。
創業の理念の継承 「すべての人々の幸福」を追求する経営

ーー人材育成や組織づくりにおいて、特に注力されていることは何ですか。
市川東太郎:
「働きがい」と「働きやすさ」の両立です。「働きがい」の面では、社員が自信を持ってキャリアを歩めるよう、教育研修やメンター制度、キャリアパスの明示などを進めています。一方、「働きやすさ」の面では、待遇改善はもちろん、誰もが安心してのびのびと挑戦できる職場環境づくりに注力しています。挑戦する人を皆で応援し、その成果を組織に還元する。そんな好循環を生み出すことが理想です。
ーー経営の軸とされている理念についてお聞かせください。
市川東太郎:
弊社の創業の理念である「仕事を通じ社会に寄与する」「会社に関係するすべての人々の幸福を追求する」という言葉を常に胸に刻んでいます。この「すべての人々」には、お客様や従業員だけでなく、株主様、一緒に仕事をする会社の方々、そしてまだ見ぬ未来の人々も含まれると私は理解しています。何かを判断する際にこの理念に立ち返ることで、目先の利益にとらわれず、長期的で偏りのない決断ができます。この素晴らしい創業の理念を羅針盤として、これからも会社の舵取りを担っていきます。
ーー最後に、今後の事業に対するご自身の意気込みをお聞かせください。
市川東太郎:
社員から中期経営計画「想い2030」を「絵に描いた餅で終わらせないでほしい」という声も届いています。私自身は、これを必ず実現させるという強い想いがあります。私はJR東日本時代、列車ダイヤという計画の実現のために必要な、車両・乗務員・駅員・設備・メンテナンスなどを準備して、実際に列車を運行させる、という仕事をしてきました。いわば「絵に描いた餅を美味しく食べられるようにする」専門家です。
今回の「想い 2030 〜連携して実現する〜」も全く同じです。壮大な絵を描きましたが、これを具体的なアクションに落とし込み、一つひとつ着実に実行していきます。それこそが社長である私の最大の責務だと考えています。
編集後記
JR東日本という巨大組織で培われた「何が正しいか」を貫く強い意志と、現場で働く人々への温かい眼差し。市川氏の言葉からは、その両方を併せ持つリーダーの姿が浮かび上がってきた。CSPが推進する中期経営計画「想い 2030 〜連携して実現する〜」は、単なる数値目標ではなく、社員一人ひとりの「想い」から生まれた変革のシナリオである。テクノロジーと人の力を融合させ、同社が描く安全・安心の未来。その実現に向けた挑戦から、今後も目が離せない。

市川東太郎/1964年群馬県生まれ。早稲田大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社に入社。2021年に同社の代表取締役副社長に就任。2023年5月からセントラル警備保障株式会社取締役、2024年5月より同社代表取締役執行役員社長を務める。新しく中期経営計画「想い 2030 〜連携して実現する〜」を策定し、事業を推進している。














