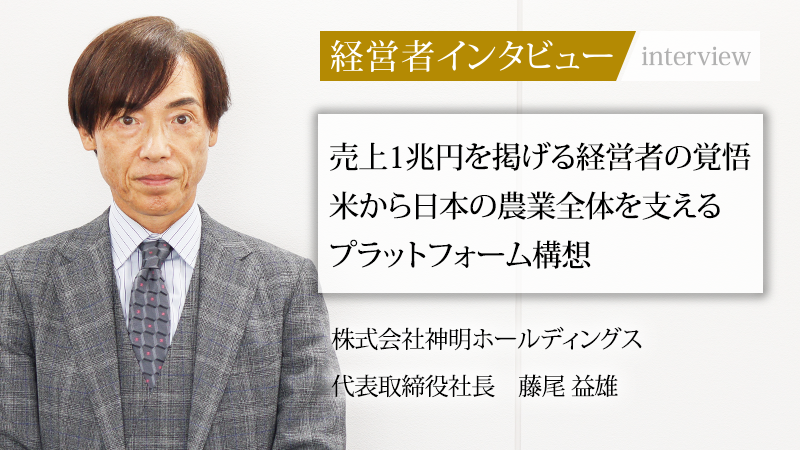
国内トップの米穀商社から、日本の農業全体を支える「農業のプラットフォーマー」へ。株式会社神明ホールディングスは、米事業を核としながら野菜や水産、外食までを手掛け、生産から販売までをつなぐ「アグリフードバリューチェーン」を推進する企業だ。担い手不足という課題に直面する日本の農業の未来を見据え、4代目として会社を率いるのが代表取締役社長、藤尾益雄氏である。祖父から受け継いだ帝王学を胸に、次なる売上目標1兆円を掲げる同氏の、日本の食と農業を守り抜くという熱い使命感に迫る。
創業者である祖父から受け継いだ経営の原点
ーー家業を継がれるまでの経緯を教えてください。
藤尾益雄:
子どもの頃から祖父に「お前は4代目だから、私が教育する」と言われ、経営者としての心構えを教え込まれて育ちました。祖父は「一日でも早く商売を覚えなければいけない」という考えの持ち主で、大学進学の際には猛反対されたほどです。最終的に「会社の精米工場で働きながら大学に通う」という条件を提示し、なんとか認めてもらうことができました。この大学時代の4年間は非常に良い経験でした。入社前から米の知識が身につき、工場で共に汗を流した仲間たちとの人間関係は、今でも私の財産です。
ーーお祖父様はどのような方だったのでしょうか。
藤尾益雄:
仕事には非常に厳しい人でした。「人の3倍働け。そうすれば必ず成功する」が口癖で、自らもそれを実践し会社を大きくしたという自負があったのでしょう。バブル崩壊を予見するなど、鋭い先見の明も持っていました。あれだけ社内で恐れられていた祖父ですが、亡くなった後に悪く言う人は一人もいません。「会長についていけば飯が食える」という絶対的な安心感を社員に与えていたからだと思います。社員とその家族が安心して生活できる会社をつくること。これが会社経営で最も大切だと祖父の背中から学びました。
事業拡大の礎となった二つの大きな経営危機

ーー入社後はどのようなことに取り組まれましたか。
藤尾益雄:
入社後すぐに神戸の営業部に配属され、約110軒の米穀店を担当しました。当時、弊社はスーパーマーケットとの取引を積極的に進めており、多くの米穀店から厳しい視線を向けられていました。「どの面下げてきたんだ」と怒鳴られることも日常茶飯事。ときには「君たちのせいで、私の妻は夜に働きに出なければならなくなった」とまで言われたりしました。この厳しい状況を打開しようと、「藤尾君が来てくれてよかった」と思っていただけるような関係づくりに必死で取り組みました。
ーーどのようにして、逆境を乗り越えられたのでしょうか。
藤尾益雄:
まず、「お客様の懐にどのようにして入っていくか」を考え抜きました。例えば、担当エリアの皆さんをバスツアーにお連れするなど、地道なコミュニケーションを重ね、少しずつ信頼を得ていきました。祖父からは「一流の営業マンは『通訳』にならなければいけない」と言われていましたが、この経験を通してその意味を体感した気がします。
ーーキャリアにおける転機となった出来事はありますか。
藤尾益雄:
大きな転機が2つあります。1つは1993年の米騒動を機に食糧管理法が改正され、県外での商売が可能になったことです。弊社は大阪市場へ進出しましたが、そこには当時、日本最大手の米卸がありました。業界では「桶狭間の戦い」と言われましたが、私たちは寝る間も惜しんで働き、1年足らずで勝利を収めています。
もう1つは、2000年に関東へ進出した際に起こった大規模なクレームです。大手スーパーへオリジナルのブレンド米を納品する契約を取り付けたのですが、初回納品で大きなミスを犯してしまいました。袋に印刷されているバーコードが間違っている商品を納品してしまったのです。その結果、間違えた商品を1万袋も出荷してしまいます。これは大きな失態でした。先方の担当部長は激怒され、面会もしていただけない状況が続きました。しかし、誠心誠意お詫びを続けた結果、最終的には許していただくことができました。この経験を乗り越え、今では最も大きな取引先の一つとなるほどの信頼関係を築いています。
ーー社長就任前後のことをおうかがいできますか。
藤尾益雄:
社長に就任したのは2007年です。当時は米の消費が減り、農業が衰退していく状況を目の当たりにし、強い危機感を抱いていました。そこで会社の進むべき道を示すために新たな理念を掲げ、パックご飯事業や外食業界への参入といった事業の多角化を進めたのです。
生産から食卓までをつなぐアグリフードバリューチェーン構想
ーー改めて、貴社の事業内容をお聞かせください。
藤尾益雄:
現在は米事業を中心に、青果流通、青果生産、食品流通、外食・中食の5つの事業領域で事業を展開しています。米加工品の分野では、富山県入善町の天然水と無添加にこだわったパックご飯が好調です。ベビー用品メーカーのピジョン株式会社と共同開発した赤ちゃん向けのパックご飯は、特に大きなヒット商品となりました。
青果事業では全国の主要な中央卸売市場にネットワークを広げ、水産や乾麺などの食品流通も手掛けています。また、外食事業も展開しており、回転寿司の「魚べい」や、東京駅で月商2000万円以上を売り上げるおにぎり専門店「TARO TOKYO ONIGIRI」などを展開し、米の新たな可能性を追求しています。
ーー現在の核となる「アグリフードバリューチェーン」構想について教えてください。
藤尾益雄:
2016年頃から、米だけでは日本の農業は守れないと痛感し、野菜や果物、水産にも本格的に進出しました。これが、生産から販売までを一貫してつなぐ「アグリフードバリューチェーン」の始まりです。2025年の売上目標5000億円を1年前倒しで達成し、次なる目標は1兆円を掲げています。私たちが成長し発信力を持つことで、日本の農業と食を守り続けることができると信じています。
株式上場見送りに込めた日本の食への覚悟
ーー日本の農業が抱える課題を、どのように捉えていますか。
藤尾益雄:
農業従事者はこの30年で300万人も減少し、平均年齢は69歳と危機的な状況です。このままでは将来的な米不足も懸念されます。また、世界の食料危機は目前に迫っており、食料自給率が低い日本にとって決して他人事ではありません。
弊社は農業のプラットフォームを構築し、生産者を多方面からサポートすることを目指しています。未来の農業モデルを研究し、収量性の高い品種を開発しました。コーポレートベンチャーキャピタルによる若手経営者への出資もその一つです。さらに、若者が農業経営を学べるプロジェクトを立ち上げるなど、人材育成にも力を入れています。
この取り組みへの本気度を示すため、短期的な利益よりも日本の農業支援を優先し、一度は予定していた株式上場も見送りました。農業を、若者が夢と希望を持てる魅力的な産業に変えていく。食は生命に直結するからこそ、日本の食の安定供給に貢献するという私たちの挑戦は続きます。
編集後記
祖父から受け継いだ帝王学は、「社員とその家族の生活を守る」という覚悟そのものであった。幾多の逆境を人間力で乗り越えたエピソードは、藤尾氏のリーダーシップの源泉を物語る。株主の短期的な利益より日本の農業の未来を優先し、上場を見送った決断。それは、同氏の使命感の強さを何よりも雄弁に語っている。「米」という一領域から、日本の農業全体を支える「プラットフォーマー」へ。その壮大な挑戦の先に、若者が夢を持って集う農業の新しい未来が期待される。

藤尾益雄/1965年兵庫県生まれ。1902年創業の米卸問屋の4代目として、幼少期から創業者である祖父より帝王学を学び、大学在学中から家業に関わる。1989年に大学卒業後、株式会社神明(現・株式会社神明ホールディングス)に入社。常務取締役、専務取締役を経て、2007年、代表取締役社長に就任。基幹事業である米穀卸売業から外食産業、青果事業などグループ拡大を推進し、現在は農業の衰退スピードに歯止めをかけるべく「農業のプラットフォーマ―」を目指し、生産支援にも注力している。














