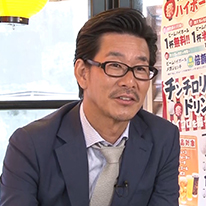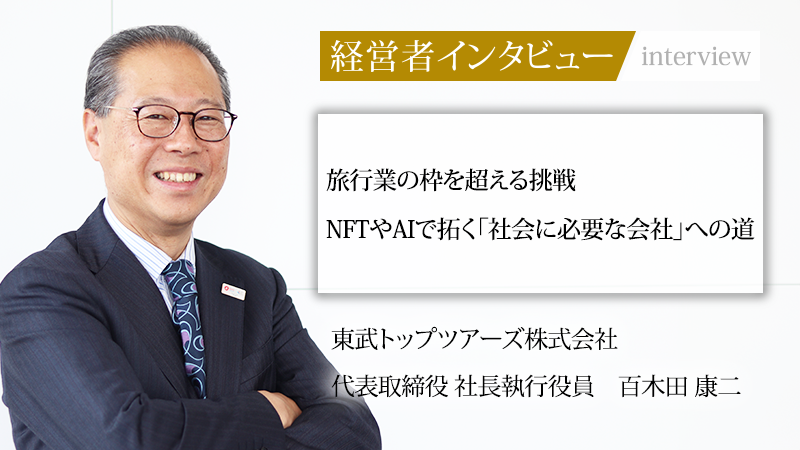
東武グループレジャー部門の中核として旅行事業を展開する、東武トップツアーズ株式会社。同社は法人向けソリューションや地域創生にも力を入れている。その舵を取る代表取締役社長執行役員、百木田康二社長のキャリアは平坦な道ではなかった。希望によらない本社経理部への配属から始まり、テロや戦争が頻発した「暗黒の時代」の海外赴任、帰国後の不遇の時代。数々の逆境を乗り越えてきたリーダーが語る独自の価値観と、未来への展望についてうかがった。
「暗黒の時代」が磨いた経営哲学
ーーこれまでのご経歴をお聞かせください。
百木田康二:
私の社会人としてのキャリアは、東急観光(現・東武トップツアーズ)の本社経理部から始まりました。サービス業を志望していたため、正直に言うと希望によらない配属です。しかし、そこでは通常、新人に任されないような責任の重い仕事を経験しました。2年目から外国為替の先物予約やグループ連結決算などを担当し、経営の根幹である「お金」の流れを徹底的に叩き込まれたのです。
大きな転機となったのは、1997年から約6年間駐在したハワイです。私が赴任した時期は、当時2社が合併した会社を解散・清算すると同時に、新たな会社を設立するという非常に多忙を極めた時でありました。さらにアメリカ同時多発テロやイラク戦争が勃発した、まさにハワイという観光地にとって「暗黒の時代」でした。観光客が激減する中、会社の清算や従業員の人員整理といった、誰もがやりたがらない厳しい決断を下す必要がありました。当時は本当に心身ともに大変な日々でしたが、企業の生命線である資金繰りと人の問題を同時に経験できたことは、後々の経営における大きな財産となっています。
ーー危機的状況を乗り越えられた後、日本でのキャリアはいかがでしたか。
百木田康二:
帰国後は、おそらく戦力にならないと思われていたのか(笑)、仕事を任せてもらえずにやることのない不遇の時代も経験し、本気で退職を考えたこともあります。しかし、今振り返れば、それも「物事を深く考えるための時間だった」と前向きに捉えています。
そうした不遇の時代を乗り越えた後も試練は続き、会社が投資ファンドの傘下に入った9年間は、コストカットや事業の選択と集中など厳しい要求の連続でした。しかし、その経験は決して悪いことばかりではなく、それまでの自分たちがいかに甘かったかを痛感させられ、経営の厳しさを肌で学ぶ貴重な機会となったのです。
こうした経験を通じて、私の根幹には「無駄な経験は何一つない」という確信が生まれました。そして、どんな困難な状況でも「この先に良いことが必ず待っている」と信じる楽観性を持つこと。これが、私が仕事をする上で最も大切にしている価値観です。
企業の真価は「人」にあり 逆境で輝く結束力

ーー数ある同業他社の中で、貴社ならではの強みや特徴はどのような点にあるとお考えですか。
百木田康二:
私たちの最大の強みは、何よりも「人」の力です。特に、予期せぬ困難に見舞われた際に発揮される逆境への強さと結束力は、この会社の大きな特徴だと思っています。
その力の源泉は、旅行業で培われた2つの要素に集約されます。一つは、お客様が本当に求めていることを深く感じ取り、寄り添う「ホスピタリティ」。もう一つは、宿泊施設や交通機関などといった資産を持たないからこそ、多様なビジネスパートナーと協力して新たな価値を創り出す「コーディネート力」です。この「共創」の精神が、私たちの事業の根幹を成しています。我々だけでは何事も成し遂げることができないことを認識し、常にパートナーの皆さまと共に歩み続ける東武トップツアーズであることを自負しています。
ーーその強みが発揮された、象徴的なエピソードがあればお聞かせください。
百木田康二:
コロナ禍で旅行の仕事がゼロになった際の、ワクチン接種の運営サポート事業への取り組みがまさにそれです。「このままでは会社が危ない」という危機的状況下で、社員たちが自ら「私たちにできることは何か」を自発的に考え、提案してくれたのです。当時としては画期的であったと思いますが、1日で600名を超える全国の社員がリモートで参加し、真剣に議論してくれました。
当時、突然の事態に自治体の方々も運営に大変苦労されていました。その課題をいち早く察知し、旅行の手配や運行で培った経験を活かせると考えたのは、まさにお客様のニーズを汲み取る「ホスピタリティ」の発露でした。
そして、会場の設営から運営スタッフの確保、そして当日の誘導まで、さまざまな関係者をまとめあげて一大プロジェクトを遂行できたのは、私たちの「コーディネート力」があったからこそだと思います。社員一人ひとりの主体的な行動が会社を救ってくれたこの経験は、私たちの「人の力」を改めて証明してくれた出来事でした。
「社会に必要な会社」へ 旅行業の枠を超えた挑戦
ーー事業の今後の展望について、特に注力していきたい分野をお聞かせください。
百木田康二:
私たちが何よりもこだわっているのは、日本の「地域」を活性化させることです。私たちの旅行業は、魅力的な地域があって初めて成り立つ事業に他なりません。しかし、その大切な土台である地域が今、想定を超える人口減少や超高齢化によって存続の危機に瀕しています。
このままでは、旅行の目的地である地域が活力を失い、ひいては私たちのビジネスも立ち行かなくなる。だからこそ、事業の土台である地域を活性化させることが、旅行業に携わる私たちの重要な使命だと考えています。
その思いから、旅行という基盤は変えずに、そこから派生する形で多様なソリューションを提供しています。たとえば、ある自治体でNFT技術を活用した「デジタル住民票」を販売した際には、数分で完売し、新たな関係人口(※1)の創出につなげることができました。
また、各地域の住民サービスをわかりやすく円滑化し、多忙を極める自治体職員の方々の業務を効率化するAIツール「マサルくん」も開発しました。さらに、災害時の緊急輸送・宿泊を手配する防災協定も、地域に貢献したいという思いから生まれた事業です。東日本大震災では、障がいを持つ方の死亡率が健常者の倍でした。この事実を踏まえ、健常者のみならず障がいを持つ方をも対象としたデジタル避難マップ開発なども進めています。
(※1)関係人口:定住している人とは異なる、地域づくりに欠かせない流動的に関わる人達。
ーー社長として、ご自身の役割をどのようにお考えですか。
百木田康二:
大事なことは「決めること」と「次とその次を育てること」だと思っています。その場しのぎの決断ではなく、苦しいことも決めなければなりません。私は社長の仕事を「登山」にたとえています。頂上に登り詰めた後、安全に下山するためには、次の誰かを頂上へ引き上げる準備をしなければなりません。
具体的には、将来の幹部候補に多様な経験を積ませることに力を入れています。若いうちからグループ会社や新規事業の経営を実際に経験させ、実践的に育てるのです。私自身、幸運にも生え抜きの社員として社長を任せてもらいましたが、次の世代にもその道をつなぎたい。そのためには、意図的にキャリアの節目となる重要な経験を積ませることが不可欠です。
ーー最後に、会社の未来像についてお聞かせください。
百木田康二:
5年後、10年後も、私たちが目指すのは、社会にとって「なくてはならない存在」であり「選ばれる存在」であり続けることです。そして、社員が自分の仕事に誇りを持ち、家族に胸を張れる会社でありたいと強く願っています。
その未来を実現するために、私たちは単に価格の安い、お得感だけで選ばれるのではなく、「東武トップツアーズにしかできない独自の価値」を提供することで選ばれる会社を目指します。
これからは安易な価格競争から完全に脱却し、お客様や地域社会への貢献を通じて成長していく。それが、私たちの進むべき道だと確信しています。
編集後記
「暗黒の時代」と自ら語る、壮絶な経験。百木田氏の言葉の重みは、その経験に裏打ちされているからだろう。単なる利益追求ではなく、社員や地域、ひいては社会にとって「なくてはならない存在」を目指すという思いは、机上の空論ではない。逆境を知るリーダーが描く、人間味あふれる資本主義の未来に、大きな期待を寄せたい。
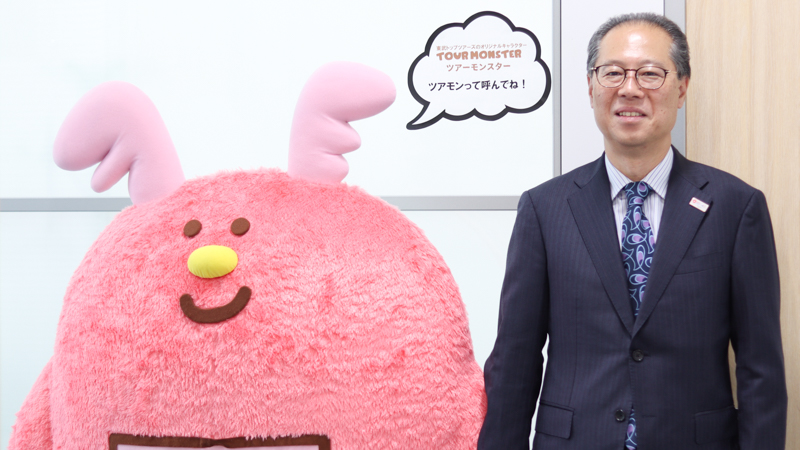
百木田康二/1964年生まれ、東京都出身。明治大学商学部を卒業後、1987年東急観光株式会社(現・東武トップツアーズ株式会社)入社。1997年ヴィータU.S.A.CO.HAWAIIに出向し、帰任後は2007年よりトップツアー株式会社(現・東武トップツアーズ株式会社)社長室長、経営企画部長を歴任。2014年取締役に就任。東武トップツアーズ発足後の2016年からは営業統括本部を管掌し、2020年取締役常務執行役員営業統括本部長を経て、2021年7月より現職。