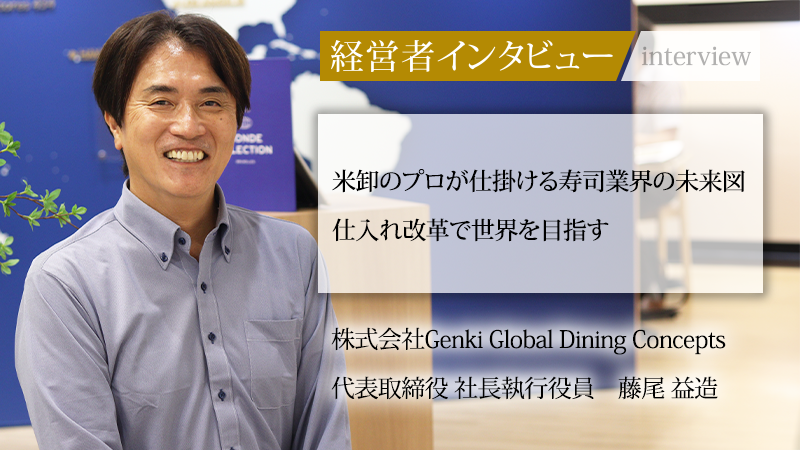
「魚べい」や「元気寿司」ブランドで、国内外に店舗を展開する株式会社 Genki Global Dining Concepts。業界に先駆けて導入した“回転しない寿司”は、できたての鮮度と圧倒的な提供スピードで顧客の心を掴み、同社の成長を牽引してきた。2025年3月、この歴史ある企業の新たなリーダーとして就任したのが、米卸最大手・株式会社神明ホールディングスで多彩なキャリアを積んできた藤尾益造氏である。商社、食品メーカー、海外事業開拓と、食のサプライチェーンを川上から川下まで知り尽くす“仕入れのプロ”は、寿司業界にどのような変革をもたらすのか。その軌跡と未来への展望を聞いた。
商社、米卸、海外開拓 すべての経験が“仕入れ”の力になる
ーーこれまでのご経歴について、お聞かせいただけますでしょうか。
藤尾益造:
学生時代にアメリカに滞在した経験から、いつか海外で事業を手掛けたいという思いがあり、卒業後は商社に入社しました。そこでは為替予約から原料の調達、販売、在庫管理まで担当し、まさに個人商店のように商売の全てを任せられました。自分の力でビジネスを動かす基礎を、ここで叩き込んでいただいたと感じています。
その後、株式会社神明ホールディングス(以下、神明)に入社して米の営業や仕入れを担当し、役員時代には富山県でパックご飯の会社をゼロから立ち上げるという貴重な経験をしました。土地の購入から工場の建設まで携わったこの事業も、当初は商品が全く売れず、大変な苦労をしました。しかし、東日本大震災の際に在庫をすべて被災地へ寄付させていただいたところ、召し上がった方々から味を評価いただき、それが口コミで広がって、ありがたいことにリピーターになってくださったのです。
そして40歳を過ぎ、念願だった海外事業に携わることになりました。神明として初となる海外部門を立ち上げ、「世界一の米卸」を目指してアメリカや中国で米の調達ビジネスを軌道に乗せました。商社からメーカー、そしてグローバルな調達まで、この一連の経験が、今の私の根幹を成しています。
ーー社長就任にあたり、貴社の最大の強みと課題をどのように分析されました
か。
藤尾益造:
2025年3月に社長に就任しましたが、まず、弊社に参画して素晴らしいと感じたのは、その組織文化です。アルバイトからキャリアをスタートし、役員として活躍している社員もいます。学歴などに関係なく、能力と情熱があれば正当に評価される土壌があるのです。また、心から会社のことが好きで、時間を忘れて仕事に打ち込んでいる社員が多い。これは何よりの強みだと確信しました。
その上で、私が貢献できる最大のポイントは、これまでの経験を活かした“仕入れの強化”だと考えています。近年の世界的な需要の高まりで、魚のネタは非常に手に入りにくくなりました。「注文すれば物が届く」という買い手市場の時代は、終わりを告げたのです。そこで、従来のやり方を見直し、より生産の領域に踏み込んだ調達の仕組みを構築することが急務だと考え、改革に着手しています。
業界の常識を覆した“回転しない寿司”という強み
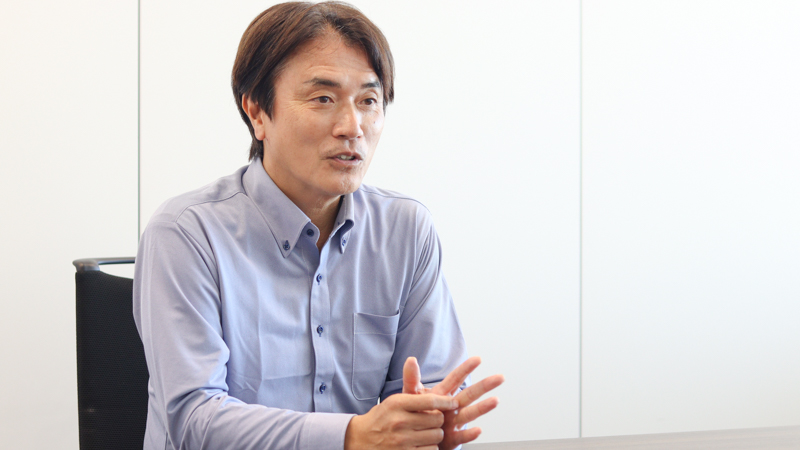
ーー“回転しない寿司”が生まれた背景について、お聞かせください。
藤尾益造:
弊社の大きな分岐点となったのは、2012年から本格的に導入した“回転しない寿司”への挑戦です。それまではレーンに寿司を流すのが当たり前でしたが、フードロスや鮮度の問題を解決するため、注文を受けてからつくり、専用レーンでお客様へお届けするオールオーダーシステムへと舵を切りました。
このシステムの最大の強みは、何よりもできたての新鮮な寿司を提供できる点にあります。シャリは握りたて、ネタも最高の状態でお届けできる。この発想は、実際に寿司を握ってきた現場の職人たちの「一番美味しいものをお客様にお出ししたい」という純粋な思いから生まれました。当時はオペレーションの負荷を懸念する声もありましたが、現場が見事に仕組みを構築し、お客様から絶大なご支持をいただくことができました。
ーー他の寿司チェーンと比べた際の、他にはない価値とは何でしょうか。
藤尾益造:
ご注文をいただいてから、いかに早く提供できるかという“スピード”が最大の差別化ポイントです。私たちは全社で提供時間の短縮を競い、そのデータを全て管理しています。
なぜスピードが重要かというと、一つは鮮度です。早く届けば届くほど、お客様は美味しいと感じてくださいます。もう一つは、お客様の食事のリズムを止めないこと。お待ちになる時間でお腹が満たされることなく、次々とご注文いただけるため、顧客満足度と客単価の向上に直結します。
友人たちからも「魚べいに行くと、つい食べ過ぎちゃうんだよ」と言われることがあるのですが、これこそが私たちの提供スピードが生み出す価値であり、最高の褒め言葉だと思っています。
調達難の時代を乗り越え、寿司の未来を創造する
ーー藤尾社長が描く、会社の未来図についてお聞かせください。
藤尾益造:
今後、私たちが目指す未来。その一つが、自ら生産の領域にまで踏み込む、“生産からかかわる寿司屋”への進化です。
今後、世界的にネタの調達がますます難しくなる時代が来ると予測しています。その中で勝ち残っていくためには、養殖事業に直接かかわるなど、生産者の方々と持続可能な関係を築くことが不可欠になります。生産者にとっては販路が確保でき、私たちは高品質なネタを安定して仕入れることができる。かつて米の調達で培ったノウハウを活かし、川上から食の未来を支えていきます。
また、寿司事業で培った強みを活かし、第二、第三の事業の柱をつくることも重要なビジョンです。国内外のパートナーからも、新しい業態への期待が寄せられています。
こうしたビジョンを実現するためには、何よりも「人材」が不可欠です。私たちが共に働きたいと願うのは、学歴や経歴で判断する人材ではありません。ただひたすらに、純粋に“寿司が好き”という情熱を持った人です。当社の役員には、今でも自ら寿司を握ることを誇りにしている者がいます。結局のところ、その愛情こそが、お客様を笑顔にする美味しい一皿を生み出す原動力なのです。そうした私たちの想いに共感してくれる仲間と共に、会社の未来を創造していきたいと考えています。
編集後記
商社、そして米卸のプロとして世界を相手にしてきた藤尾氏の視線は、常にグローバルで、かつサプライチェーン全体を貫いている。その経験から導き出された「仕入れ改革」と「生産への関与」というビジョンは、単なるコスト削減策ではない。食の未来を見据えた、持続可能な成長戦略そのものである。「会社が好き」と語る社員たちの情熱を力に変え、寿司業界の未来を切り拓く同社の挑戦に、今後も注目したい。

藤尾益造/1994年、甲南大学法学部卒業。商社での経験を経て、2007年6月、株式会社神明(現・神明ホールデイングス)取締役に就任する。同社東京支社の設立および海外事業(アメリカ・中国・香港)の立ち上げに携わり、海外における豊富な実務経験を有する。神明ホールディングス常務取締役などを経て、2017年4月に元気寿司(現・Genki Global Dining Concepts)の顧問となる。同年6月、同社取締役に就任。2025年4月より現職。














