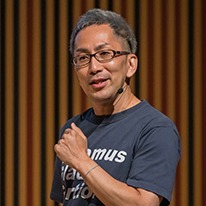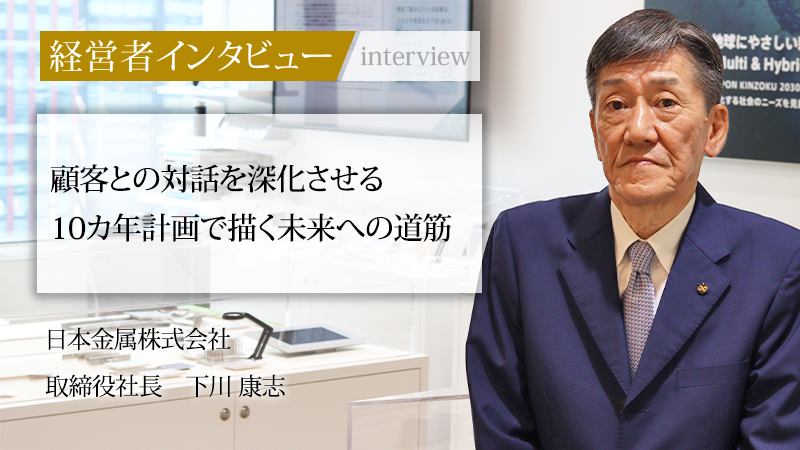
日本金属株式会社は、特殊鋼やマグネシウム合金などの圧延・加工事業を手がける企業だ。同社は顧客の個別ニーズに深く応える「受注生産方式」と、素材から二次加工までを一貫して手がける幅広い製品技術を強みとしている。30年にわたる営業経験と、その後の管理部門での改革実績を経て2017年に取締役社長へ就任したのが下川康志氏である。常に「どうすればできるか」を問い続け、事業構造の変革を掲げる同氏に、これまでのキャリアで得たもの、会社の強みと今後の展望、そして未来を支える人材育成について話を聞いた。
経営の礎を築いた営業一筋30年のキャリア
ーー社長に就任されるまでのキャリアについてお聞かせください。
下川康志:
1980年に入社し、最初の2年間は営業管理の部署で経験を積みました。その後2013年まで約30年間は営業一筋。大阪に6年間、名古屋に9年間赴任し、キャリアの半分は地方勤務で、東京での勤務は15年です。2017年に社長に就任するまでの4年間は管理部門へ移り、総務、人事、財務といった営業以外の業務を初めて経験しました。
ーー30年にわたる営業時代で、特に得られたことは何ですか。
下川康志:
国内の広範囲にわたって人脈を築けたことが、今振り返ると非常に大きいと感じています。当時お付き合いのあった方々とは今でもご挨拶する関係が続いており、人とのつながりやネットワークが私の財産です。また、東京、大阪、名古屋の三地区を経験しましたが、文化や営業スタイルが全く異なりました。それぞれの地域特性に応じた人付き合いや企業との向き合い方を実践の中で学べたのは大きな収穫でした。
国内だけでなく、特に大阪時代は中国を中心に、韓国や台湾へも頻繁に出張し、新規ユーザーの開拓に注力したことも貴重な経験です。
ーー管理部門でのご経験は、現在の経営にどう活かされていますか。
下川康志:
管理部門に移った当初は知識が全くなく、特に財務に関しては、PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)といった言葉は知っていても、それが何を意味するのかを深く理解していませんでした。そこで、入門書から読み始め、独学で経営に必要な財務資料を理解できるレベルまで知識を身につけました。
総務や人事についても知らないことばかりでしたが、その中でも会社に大きく貢献できたと考えているのが、企業年金制度の改革です。年金資産の運用リスクに対応するため、給付額を調整する新しい制度を導入しました。当時としては先進的な取り組みでしたが、この改革によって年金運営は非常に安定しています。
ーー仕事をするうえで、大切にされている価値観はありますか。
下川康志:
現状に甘んじることなく、常に改善や改革を心がけています。社員にも、経営課題に直面したときには「できない理由を探すのではなく、『どうすればできるか』を考えてほしい」と常に伝えています。この考え方は、ゼネラル・エレクトリック社のCEOを務め「伝説の経営者」とも称されたジャック・ウェルチ氏が遺した「Change before you have to.(変革せよ、変革を迫られる前に)」という言葉に集約されていると感じています。この言葉は、私自身が目指す姿勢を的確に表現した名言として大切にしています。
顧客との対話が生む技術と差別化という強み

ーー貴社の事業内容と、その特徴について教えていただけますか。
下川康志:
弊社は国内に3つの工場を持っています。東京都板橋区の板橋工場ではステンレスを中心とした特殊鋼や電磁鋼板などの圧延事業を、福島県白河市の福島工場では金属の成形加工を手がけています。そして、岐阜県可児市の岐阜工場では溶接引抜管(製品名「ファインパイプ」)を製造しています。このように、素材から二次加工まで幅広い製品技術を持っている点が、お客様に広く貢献できる強みです。
そして、全ての工場で、お客様の注文を受けてから生産する「受注生産方式」をとっていることが最大の特徴です。
「受注生産方式」では、注文を受けてから生産するため、直接対話を通じて具体的な要望を深く理解することができます。また、顧客の深いニーズに応えることで、結果的に、他社にはない差別化された技術や製品の創出につながっています。
お客様との取引においては、「点から面に広げ、さらに深く掘り下げて球へ」という考え方を基本にしています。これにより、より深く、そして広い関係性を築くことを心がけています。
ーー貴社は業界の中で、どのような立ち位置を目指していますか。
下川康志:
私たちが属するステンレスなどの鉄鋼業界は、国内需要が年々縮小しています。海外に市場を求めると、特に中国を中心とした激しい価格競争に直面します。そのため、コストで競争するのではなく、機能や品質といった価格以外の競争力で戦うことが基本戦略です。繰り返しになりますが、独自性や差別化が図れる技術・製品に徹底的に注力していく必要があります。
顧客と社員双方の成長を促す未来への投資
ーー現在、注力されていることはありますか。
下川康志:
2020年に第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」(10カ年計画)を策定しました。策定の背景には、製造業として事業構造を大きく変えなければならないという強い危機感があります。事業構造や製品構成の変革には、設備投資を含め長い年月がかかるため、2020年から「10年」という長期計画をスタートさせました。3年程度の短期計画では難しい、腰を据えた本質的な変革が狙いです。
実際に、省資源にも貢献する、精密異形圧延製品(製品名「ファイン・プロファイル」)のような新しい製品の量産が始まっています。このように、計画の前半5年で成果は着実に出始めています。
ーーお客様に対して、何か新しい取り組みはされていますか。
下川康志:
2025年6月に初めて、主要なお取引先64社を対象とした顧客アンケートを実施しました。品質や納期など10項目で評価をいただき、現在その結果を分析して個々のお客様への改善策を進めているところです。
また、2025年4月には「プロダクションプロセス・サポート部」という新部署を立ち上げました。これは、お客様のものづくりを全社的にサポートする体制です。弊社の製品を使っていただくだけでなく、お客様の課題解決そのものをお手伝いする姿勢で臨むものです。この取り組みが、結果的に私たちのビジネスチャンスにもつながると信じています。
ーー社員育成に関して、どのように取り組んでいますか。
下川康志:
社員一人ひとりのキャリア形成を支援するため、2つの制度を導入しています。希望部署へのローテーションを促す「キャリアパス制度」と、年功序列によらない「飛び級昇格制度」です。さらに、次世代リーダー育成を目的とした「リーダーシッププログラム」も実施しています。これは、客観的なアセスメント(※)で各自のスキルを可視化し、本人にフィードバックする仕組みです。そのうえで、必要な研修を受けてもらい、体系的に育成を図っています。
(※)アセスメント:対象となる物事や人を客観的なデータに基づき分析・評価するプロセスや手法。
ーー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
下川康志:
「プロダクションプロセス・サポート部」の設立は、私たちの思いの象徴です。私たちは、「日本金属に相談すれば、何とかしてくれる」と思っていただけるパートナー企業でありたいと強く願っています。ものづくりを強力にサポートする存在を目指します。ぜひ、さまざまな形で私たちにコンタクトしていただければ幸いです。
編集後記
30年にわたる営業の第一線で培った顧客との深い関係構築力。そして、管理部門で発揮された緻密な制度改革。下川氏の経営スタイルの根幹は、この両輪の経験に支えられている。「どうすればできるか」を問い続ける真摯な姿勢と、「変革せよ、変革を迫られる前に」という強い信念は、長期経営計画や多様な人事制度として結実した。顧客と社員の双方と真摯に向き合い、未来に向けて着実に布石を打つ同社の今後の展開に、大きな期待が寄せられる。

下川康志/1957年山口県生まれ。1980年早稲田大学政治経済学部卒業後、日本金属株式会社に入社。30年以上を営業畑で過ごし、東京・大阪・名古屋で勤務。2013年からは管理部門に移り、総務部長、管理部門長、常務取締役などを経て、2017年に取締役社長(代表取締役)に就任。現在、2020年からスタートした第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」(10カ年計画)を推進中。