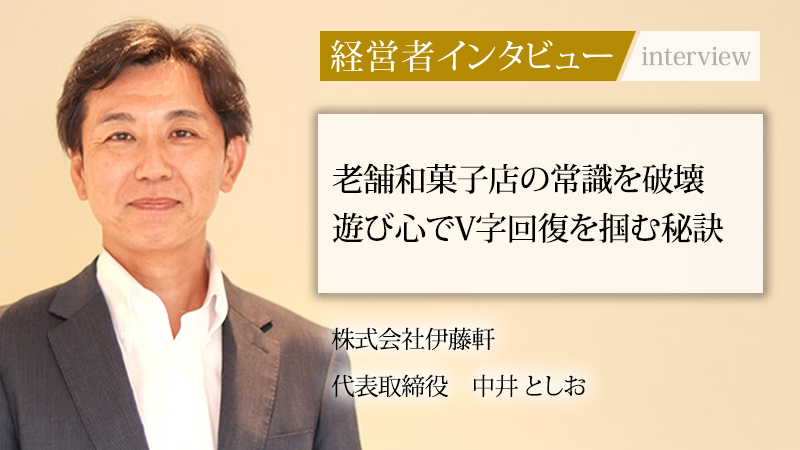
京都に本社を構える株式会社伊藤軒は、伝統的な和菓子を基盤としつつ、時代に合わせた新たな菓子づくりに挑む企業である。代表取締役である中井としお氏は、赤字経営からのV字回復や、コロナ禍を逆手にとった柔軟な経営戦略で同社を牽引してきた。特に、多様な価値観を持つ社員が「遊び心」を大切にしながらものづくりに励む企業風土は、同社の最大の強みといえる。本記事では、中井氏のこれまでの歩みや未来の展望に迫る。
商いの原点を叩き込んだ問屋時代と赤字からの脱却
ーー貴社に入社されるまでの経歴について教えてください。
中井としお:
新卒で、菓子の卸問屋である株式会社サンエス(現・三菱食品株式会社)に入社しました。当時、メーカーが販路を広げるためには、まず問屋さんとの関係性を築くことが重要でした。そこで、いわば修業として問屋に入りました。現場で働きながら人間関係を築き、自社の商品を扱っていただく慣例があったのです。
ーー伊藤軒に入社されてから、どのようなお仕事を担当されましたか。
中井としお:
入社後、最初の3年間は東京で勤務しました。当時の会社の赤字状況を打開するため、大手のスーパーマーケットの販路開拓と業務改革に注力したのです。京都に戻ってからも2〜3年かけて業務改革を続け、ようやく会社が利益を出せる土台を構築。次にパッケージの見直しが必要だと感じ、勢いのあるデザイン会社に依頼して全面的に刷新したところ、売上は大きく伸長しました。
和菓子の概念を打ち破る「遊び心」ある商品開発
ーー事業が軌道に乗った後、次なる一手としてどのようなことをお考えでしたか?
中井としお:
会社の成長と共に、自分たちの手で直接お客様にお菓子を届けられる路面店を出したいという思いは募る一方でした。しかし、その夢の実現には大きなハードルがあったのです。それは、私の頭の中にある「つくりたいお菓子」を形にするための製造能力が、当時の会社には不十分だったことです。特に、現場の技術力や組織力が私の構想に追いついていませんでした。
ですから、まずは製造基盤の強化を最優先しました。何よりも、新しいアイデアをすぐに試せる「実験的な工場」が必要だと考えたのです。同時に、それまでバラバラだった拠点を一ヶ所に集約し、社員全員が一体感を持って仕事に取り組める環境を整えることで、会社全体の力を高めることも目指しました。この場所は、私たちの新たな挑戦の土台となるべき場所でした。
ーー新しい本店をオープンされるにあたり、どのようなお店づくりを目指されたのでしょうか?
中井としお:
お菓子を手に取ってくださる主な層である中高年の女性に喜んでいただきたい、という思いが原点です。そこで、体に優しくヘルシーな食事を提供するため、私たちの原点である和菓子の考え方を応用することにしました。
和菓子は、バターやゼラチンのような動物性の素材を基本的に使いません。その植物性の素材を活かすという考え方をヒントに、「肉と魚を使うのをやめよう」と決断しました。その結果、コンセプトが「野菜と穀物だけを使ったランチ」という非常に明確なものになりました。お客様にも一言で分かりやすく説明できる、それがお店の強みになったと感じています。
ーーお店が人気となる中で、さらに会社が進化するきっかけとなった出来事はありましたか?
中井としお:
おかげさまで「ランチが美味しい和菓子屋さん」として、多くのお客様に足を運んでいただけるようになりました。しかし、それは同時に新たな課題の始まりでもありました。ランチが好評なのは嬉しいものの、お昼時以外にもお客様を惹きつける、店の「顔」となるような名物菓子がないと痛感したのです。
そんな時、地元のぶどう農園の方との出会いが転機となりました。当時まだ珍しかったシャインマスカットを見せていただき、「これだ」と直感したのです。そこから生まれたシャインマスカットの大福やパフェは大変な人気を博し、店の看板となる大ヒット商品に育ちました。
この成功を機に、私たちの考え方は大きく変わりました。「和菓子」という枠にとらわれる必要はないのだと。以前ある方からいただいた「お客様は和菓子屋や洋菓子屋ではなく、美味しい『お菓子屋』に来ている」という言葉が、すとんと腑に落ちた瞬間でした。
また、現代の生活ではコーヒーや紅茶が飲み物の主流です。そうした文化に寄り添うお菓子をつくる必要性も感じていました。これらの経験と思いが一つになり、現在ではシュークリームやロールケーキなども含め、和洋の垣根なく、ただお客様に喜んでいただけるお菓子づくりに邁進しています。
ーー商品開発を手がける中で、特にこだわってきたことはありますか。
中井としお:
私には、「1個500円で売れる和菓子をつくりたい」という強い思いがずっとありました。かつて百貨店の催事に出店した時、私たちの隣で生チョコのお店が大行列をつくり、100万円以上を売り上げていました。一方の私たちは、1日に5万円ほどの売上だったのです。
1個100円程度の和菓子と、500円以上の洋菓子。両者の間にある価値の違いを痛感し、「この差は何だろう」とずっと考えていました。この経験から、「お客様に感動を与えられる1個500円の価値があるお菓子をつくりたい」という野心が、私の中に強く芽生えたのです。後にSOU・SOUさんとコラボレーションした、4種類の菓子を串に刺した「串和菓子」。これは、まさにその長年の思いが形になった商品です。
逆境を乗り越える経営戦略と「和える」お菓子の真髄

ーーコロナ禍はどのように乗り越えたのですか。
中井としお:
2018年の伊勢丹出店直後にコロナ禍に突入し、百貨店は苦戦しました。しかし、本店は過去最高の売り上げを記録したのです。多くの企業が守りに入る中、私たちはこの逆境をチャンスと捉えました。コロナ禍で観光客が激減し、京都の観光地の好立地に空きテナントが出始めたからです。通常では考えられないことでした。
そこで、2021年9月に京都の観光地である清水の産寧坂に新店舗をオープンし、これが成功を収めています。この成功を足がかりに、観光地の好立地へ積極的に出店しています。伏見稲荷や宇治平等院、京都タワーなどがその一例です。
同時に、工場の手狭さを解消するため物流センターを外部委託しました。そして空いたスペースを工場に改装し、店舗や卸売への安定供給体制を強化しています。
ーーお客様と関わる中で、印象的だったエピソードはありますか。
中井としお:
昔、百貨店の催事で、弊社の代表的なお菓子の一つ「遊び菓」を販売していた時のことです。一人のおばあ様がそのお菓子を10個もお買い求めくださいました。不思議に思って理由を尋ねると、こう教えてくれたのです。「体の悪い主人が、他のものはもう食べられないの。でも、このお菓子だけは『懐かしい』と言って喜んでくれるんです」。
さらに、「人間、年をとって弱ってくると、最後に食べるのは思い出なんですよ」という言葉に、私は心を打たれました。この経験から、強く思うようになったことがあります。「ただ美味しいだけでない、誰かの大切な思い出になるお菓子をつくりたい」と。
この考えは、和菓子の「和(わ)」の字が持つ「和える」という意味にも通じます。異なるものを合わせて新しい価値を生むように、一つひとつは弱くても集まれば強くなる。この「全員集合で強くなる」という考えと「遊び心」が、私たちのお菓子に込めた思いです。
ーー今後の注力テーマについてお聞かせください。
中井としお:
新規の取引先開拓や新商品開発は常に行いますが、今最も注力しているのは工場の生産品質改善と若手社員の育成です。工場が手一杯の状況で、若手社員の育成が急務だと考えています。彼らが活躍できる場を増やせば、工場の生産能力は向上します。そして、より良い商品を効率的につくれるようになるのです。これにより新規開拓も円滑に進み、将来的には海外展開の基盤も築けるはず。この1年から2年は、設備投資を含め、工場の生産体制と人材育成に力を入れていきます。
編集後記
インタビューを通して菓子づくりへの深い愛情と、常に挑戦を続ける姿勢がひしひしと伝わってきた。特に印象的だったのは、和菓子の「和」を「和える=足す」と解釈する点だ。多様な素材やアイデアを融合させ、新たな価値を創造する「遊び心」という考え方である。常に現状に満足せず未来を見据え、生産体制の強化や若手社員の育成に力を注ぐ姿勢から、今後の伊藤軒のさらなる飛躍に期待される。

中井としお/1972年京都府生まれ。関西大学を卒業後、株式会社サンエス(現・三菱食品株式会社)に入社し3年間勤務。1998年に株式会社伊藤軒に入社。2014年に同社代表取締役に就任。














