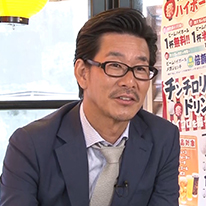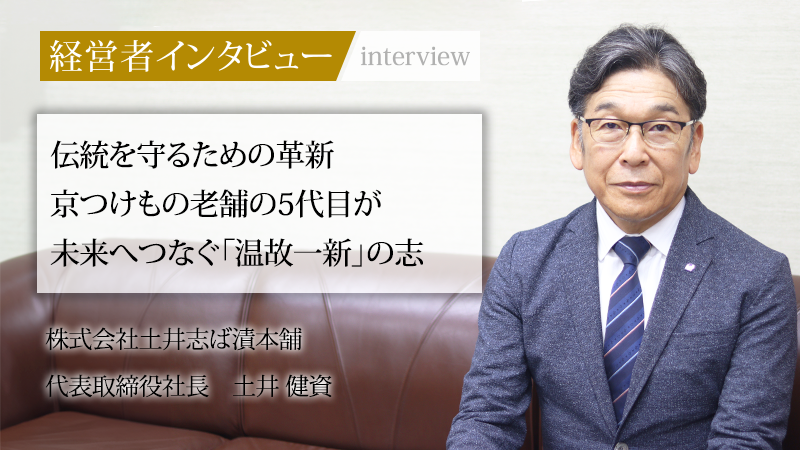
京都・大原の地で800年以上前に生まれたとされる「しば漬」。その伝統の味を明治34年の創業以来、120年以上にわたって守り続けるのが株式会社土井志ば漬本舗だ。同社はしば漬をはじめ、京つけものの製造から販売までを一貫して手掛ける。時代のニーズに応える商品づくりで、多くの人々に愛され続けている。5代目として暖簾を継いだ代表取締役社長の土井健資氏。同氏は先人たちの教えを胸に、革新への挑戦を続ける。今回は東京での修行時代から社長就任に至るまでの道のりを辿る。そして、事業へのこだわり、次世代へ託す未来像について、話をうかがった。
事業承継を見据えて歩んだ若き日の道のり
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。
土井健資:
1986年に大学を卒業後、弊社に入社しました。しかしすぐに出向となり、東京の日本橋三越で約3年間勤務しました。いわば武者修行です。配属されたのは弊社の売り場ではなく、さまざまな老舗の品が集まる売り場でした。自社の商品だけでなく、他社の商品も扱いながら、商売の仕組みを学習。お客様との接し方も現場で学びました。この経験が、後の経営に大きく活きています。
ーー東京での経験で、特に印象に残っていることは何でしょうか。
土井健資:
東京だからといって無理に関東の文化に合わせることはしませんでした。あえて京都の人間らしさを出そうと考え、お客様には京言葉で接客を継続。すると「その話し方が面白いね」と興味を持ってくださるお客様も多く、大変可愛がっていただきました。また、他社の商品を扱うことで各社のこだわりや歴史を知ることができました。視野が大きく広がったことも事実です。この3年間で得た知識と人とのつながりは、私にとってかけがえのない財産となりました。
ーー社長に就任されるまでの経緯についておうかがいできますか。
土井健資:
京都に戻って間もなく、私が28歳の時に先代である父が他界しました。その後、叔父が社長を務めることになり、私はその下で10年間働き、会社の全部署を経験しました。しば漬を漬ける製造現場から、営業、総務まで。文字通り会社の隅から隅まで見て回りました。私は父から直接事業を教わることは叶いませんでした。だからこそこの10年間は、会社の伝統や歴史、課題を自分自身の目で確かめ、それらを深く理解するための貴重な時間でした。
ーー社長就任まで、どのような思いで業務に取り組まれていましたか。
土井健資:
現場で働きながら、弊社が守り続けるべきものと未来のために変えていくべきものを考え、その構想をじっくりと練りました。弊社には、創業者である曽祖父・土井清太郎の時代から代々伝わる家訓のような教えがあります。そこには商売の心構えや、ものづくりへの姿勢が記されており、私の経営哲学の根幹となっています。このブレない軸足を大切にしながら、会社をさらに発展させる方法を模索。そして、創業100年という節目の2001年に、社長へ就任しました。
経営理念「温故一新」に込めた思い
ーー貴社の事業内容とこだわりについてお聞かせください。
土井健資:
弊社の事業の核は、京つけものの製造と販売です。看板商品である「志ば漬」。契約農家で栽培したちりめん赤紫蘇と茄子を使い、昔ながらの製法で乳酸発酵させてつくります。創業以来、素材の栽培から販売までを一貫して行う姿勢を貫いています。自分たちの目の届く範囲で丁寧なものづくりをすること。それがお客様の信頼に応える唯一の方法だと考えています。

ーー伝統と革新を両立させるために、どのような考え方を軸にされていますか。
土井健資:
私が社長就任した際、「十五の志」という社是を定めました。この社是は「ものづくり」「人づくり」「組織づくり」の3分野で構成されています。そしてそれぞれに5項目あり、計15項目が私たちの行動指針です。そして、「組織づくり」第一項の「温故一新」は、弊社の経営理念でもあります。これは「古き良きものを大切にしながら、新しいことに挑戦する」という思いを表す言葉です。
「温故」、つまり軸となる伝統は、経営の根幹として捉えています。「実力以上に手を広げない」「本業を疎かにしない」。この軸があるからこそ、時代が変化しても進むべき道を見誤ることがありません。
一方で、時代の流れに対応しなければ伝統を守り続けることすら難しくなります。人口減少やライフスタイルの変化がその背景にあります。そこで、「伝統」という軸を揺るがさない範囲で、新しい挑戦「一新」を続けています。
例えば、漬物を食べる機会が減っている若者にも興味を持ってもらえるよう、紫蘇を使ったジュースやゼリーを開発。漬物を活用したタルタルソースの素などをつくりました。また、お漬け物をより美味しく味わっていただくための飲食店「かまど炊きごはん」の展開も、革新的な取り組みの一つです。

ーー京都で商売を続ける上で、大切にされていることはありますか。
土井健資:
京都には、老舗の経営者が集まる会合が数多くあります。そうした場で先輩経営者の方々と交流する中で、今でも学ぶことは非常に多いです。企業の歴史や文化は違えど、長く商売を続けてこられた方々の言葉には重みがあります。人間として、経営者として成長させてもらっています。こうしたつながりを大切にし、私自身も京都の文化全体を盛り上げていく一翼を担いたいと常に思っています。
次の100年を見据えバトンをつなぐ未来への展望

ーー今後の事業展開について、どのようにお考えですか。
土井健資:
いたずらに規模を拡大するのではなく、品質をさらに高めていくことに注力したいと考えています。工場の生産体制や品質管理を常に改善し続けることが最優先です。「やっぱり土井さんの漬物は美味しいね」と言っていただけるよう、努力を重ねます。その上で、私たちの味をより多くの人に届けるための新しい店舗展開や、時代のニーズに合わせた新商品の開発にも挑戦。お客様に愛され続ける会社でありたいと考えています。
また、私自身が父から事業を十分に教わらないまま会社を継いだ経験があります。そのため、後を継ぐ息子には時間をかけて経営のすべてを伝えていく所存です。幸い、息子も弊社で働き、未来の土井志ば漬本舗を担うべく日々励んでいます。私が守り育ててきたものを引き継ぎつつ、新しい風を吹き込んでくれることを期待しています。彼の若い感性が、会社に変化をもたらしてくれるでしょう。伝統を守ることと、新しいことに挑戦すること。その両輪をうまく回しながら、次の100年へとバトンをつないでいくのが私の最後の仕事です。
ーー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
土井健資:
弊社は120年以上続く古い会社ですが、決して過去の伝統に安住しているわけではありません。むしろ、伝統を守り続けるためには、常に新しい挑戦が不可欠です。私たちが守り継いできた漬物づくりの技や歴史。それは若い皆さんにとって、非常に「新しい」ものに映るかもしれません。伝統を学び、そこに皆さんの新しい発想を掛け合わせることで、未来の食文化を創造していく。そんな面白さが私たちの仕事にはあります。変化を恐れず、何事にも興味を持って挑戦する気概のある方と、一緒に働けることを楽しみにしています。
編集後記
「伝統とは革新の連続である」。土井氏の言葉の端々からその強い信念が伝わってきた。東京での修行時代に培った広い視野、父の急逝後に現場で流した汗。そして、先人たちの教えを道しるべに会社を導いてきた経営者としての覚悟。そのすべてが、温和な表情の中に深く刻まれている。伝統の味を守るという使命感と、次世代に新しい価値をつなごうとする愛情。その両方を持つリーダーがいる限り、同社はこれからも多くの人々に愛され、京都の食文化を豊かに彩り続けるだろう。

土井健資/1963年京都府生まれ。1986年京都学園大学経営学部卒業後、同年4月、株式会社 土井志ば漬本舗に入社。日本橋三越での3年間の勤務を経て、本社に戻る。創業100周年を迎えた2001年に、代表取締役社長に就任。社外では、京都府漬物協同組合 理事長、京都広告協会 理事長、京都老舗会 世話人、2025年度京都ライオンズクラブ会長なども務める。