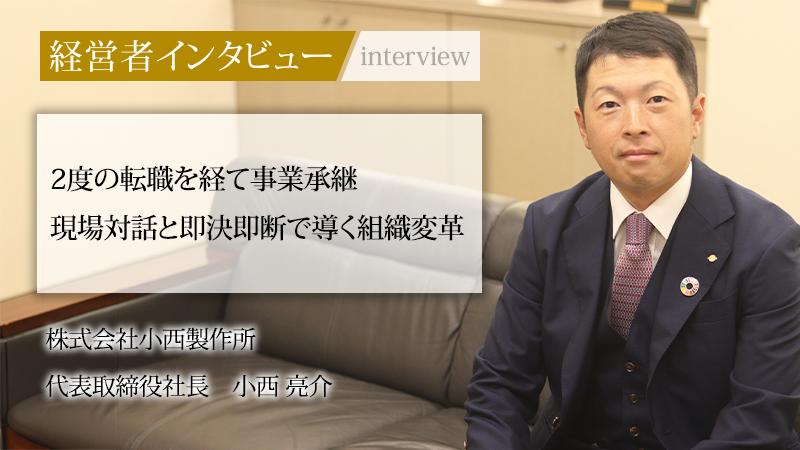
大阪府に拠点を置く、機械器具製造業の株式会社小西製作所。同社を率いるのは、代表取締役社長の小西亮介氏だ。大手商社のトップセールス、そして製薬会社の凄腕営業マン。輝かしいキャリアを歩んできた小西氏が、どのような経緯で祖父が創業した製造会社を継ぐことを決意したのか。事業継承に至った経緯と、中小企業の成長に不可欠な組織づくりの哲学をうかがった。
同期に負けない一心でがむしゃらに駆け抜けた新卒時代
ーー社長のキャリアの原点についてお聞かせいただけますでしょうか。
小西亮介:
当時は家業を継ぐつもりは全くなく、就職活動をしていました。祖父や父が経営者でしたが、私たち兄弟には「自分の道を進んでほしい」という考えでしたので、人と接することが好きだった自身の強みを活かせる商社を志望しました。「同期に負けない、誰より早く出世する」という目標を掲げ、がむしゃらに働いていました。
ーーファーストキャリアで得た経験で、現在の経営に活きていることがあれば教えてください。
小西亮介:
「デスク周りを綺麗にすること」「誰よりも早く動くこと」「数字を徹底的に管理すること」の3点です。前職時代に叩き込まれたこの3つの経験が、現在の経営の土台になっています。特に、頭の中を整理するように机の上を整頓し、誰が見ても分かるように資料を管理する習慣は、思考の整理と作業効率の向上に直結する、大きな財産です。
異業種で培った“数字”と“対話”の視点
ーーその後、どのような経緯で現在のキャリアに至りましたか。
小西亮介:
「営業としてより明確に数字で勝負したい」「医療や薬を学ぶことは自分の健康、家族、私が関わる全ての人にも役立つ」という思いが芽生え、商社から製薬業界に転職しました。厳しい数字目標があることは覚悟の上でしたが、実際に働くと、達成率が100%と99.9%では天と地ほどの差があると言われるほどの厳しい世界でした。高学歴ばかりが集う組織の中で日々レベルの高さに圧倒される毎日で、休みの日も含め毎日勉強していました。
ーーそうした厳しい環境で成果を出すために、どのような工夫をされたのでしょうか。
小西亮介:
「即時行動」です。会社から方針が示されたら、誰よりも早く実行することを徹底しました。最初に一気に実績を上げることで、全国会議でも注目される存在になる事を意識しておりました。私は大阪の中心部でエリアを持っていた為、常に全国から見られる支店でした。若いうちは経験がない分、圧倒的な行動スピードで勝負し、成功と失敗の体験を積み重ね、最速でPDCAサイクルを回しました。
ーー製薬業界でのご経験は、現在の経営にどのような形で活かされていますか。
小西亮介:
「数字は嘘をつかない」という、徹底的な数字管理の重要性を学びました。これは現在の経営でも常に意識しています。もう一つは、相手の目線に立って、その人に合った伝え方をすること。医師は専門外でも患者に説明しなければなりません。私たち製薬会社の営業マンは医師が患者に短時間で正確に説明できるように情報共有をします。医師も多忙で、貴重な時間を頂いて私達は面会しているので、短時間で最大のインパクトを伝えられるように何度もシミュレーションを行います。今の立場でも、社員に対してできるだけ同じ目線で、噛み砕いて説明するように心がけています。
父への恩返しと使命感 2度の辞退を経て継いだ家業

ーー順調にキャリアを積まれる中、なぜ家業を継ぐことを選ばれたのでしょうか。
小西亮介:
2018年に転勤で大阪に戻り、父と頻繁に話す機会が生まれたことがきっかけです。その中で会社が後継者問題に直面していることを知り、「会社を継いでくれないか」と打診されました。しかし、当時は製薬業界の仕事が本当に楽しく、キャリアを手放すつもりはなかったので2度断りました。
しかし、父からの誘いが続いたため、家族で半年ほどかけて会社の事、私のキャリアについて深く話し合いました。ある日は夜遅く数時間に及ぶまで話し合いをした事もありました。その中で、自分がここまで成長できたのは祖父が創業した会社の存在があったからだと改めて気づきました。祖父や父に恩返しをするため、そしてこの会社を存続させることが自分の使命だと感じ、決心しました。
経営の根幹 社員と組織を動かす3つの行動指針
ーー社長に就任されてから、組織づくりにおいて特に大切にされている指針はございますか。
小西亮介:
大切にしていることは3つあります。1つ目は、毎朝全従業員に挨拶をして回ることです。1時間半ほどかけて現場を回り、一人ひとりと顔を合わせてコミュニケーションをとります。毎日話していると、現場の雰囲気や個人の様子のわずかな変化にも気づきます。トラブルの芽を早期に摘むためにも、この対話の時間は欠かせません。
2つ目は、社員には「ミスを恐れずにトライしてほしい」と伝えています。製造業の現場は、お客様からの厳しい要求に応えなければなりません。だからこそ、萎縮せずに挑戦してほしい。その代わり、失敗したときの責任はすべて私が取ると公言しています。それが社長の役割だと考えているからです。
最後に「即決即断」です。前職時代、上司への相談が滞り、動きが止まってしまうことへのもどかしさを常に感じていました。その経験から、社員からの提案にはその場で判断し、すぐにボールを返すようにしています。社員がすぐに次のアクションに移れるようにすることで、組織全体の仕事のスピードを上げていきたいと考えています。
ーー社員の意見を尊重し、経営に反映された具体例がありましたら、ぜひお聞かせください。
小西亮介:
90周年という節目を迎え“MRK”という当社の自社ブランドロゴを刷新したのが好例です。当初刷新するにあたり、役員間のみで検討していましたが、従業員と100年企業にしていく為に社内公募を実施しました。従業員から多くの意見が出され公募した中の意見には過去の実績と未来への可能性と大きく2つの内容に分かれました。
100年企業にしていく為には未来に向けて方向性を出さなければなりません。全てのアンケートに目を通し、素晴らしい内容を挙げて頂いた従業員もいました。その案も反映させて頂き、「MRK(Memoriable Radiance Keep trying company):記憶に残る輝かしい挑戦を続ける会社」と位置づけました。今後は100年企業にできるように従業員と共に歩んでいきます。
ーー採用面では、どのような人材を求めていらっしゃいますか。
小西亮介:
現在は中途採用が中心ですが、応募者のほとんどが未経験です。私たちは経験よりも意欲を重視しており、未経験からでも着実に技術を習得できる研修体制を整えています。挑戦したいという気持ちさえあれば、誰もが活躍できる環境です。
100周年に向けて 未来を創る投資フェーズへ

ーーそれでは最後に、貴社の未来に向けた今後の展望をお聞かせください。
小西亮介:
当社は創業90周年を迎え、100周年企業を目指しております。次なる100年に向けて、現在は会社の基盤をさらに強化するための“投資フェーズ”と位置づけています。設備投資はもちろん、社員が安心して挑戦できるよう、人材育成にも積極的に投資していきたいと考えています。
編集後記
大手商社と製薬会社、2つの業界でトップセールスとして活躍した経験。小西社長の経営スタイルの根幹には、そこで培われた“数字への意識”と“徹底した現場主義”がある。社員の意見から生まれた新しいロゴに象徴されるように、地道な対話を信頼関係の礎とし、組織に変革をもたらそうとする同氏の挑戦。100周年に向けた投資フェーズへと舵を切った今、その挑戦は多くの中小企業経営者にとって、勇気と示唆を与えるものとなるだろう。

小西亮介/1989年8月12日大阪府富田林市生まれ。関西学院大学理工学部卒業。半導体を扱う大手商社に入社し、3年間の営業活動を行い最年少で社長賞を受賞。ステップアップのため2016年に製薬業界へ転職。製薬会社2社にて更なる営業活動を行い数多くの賞を受賞し、全国No.1に。その後満身創痍で2021年同社入社、2022年代表取締役社長に就任。ベアリング製造を中心に研削加工と自社MRKブランドの販売に注力している。














