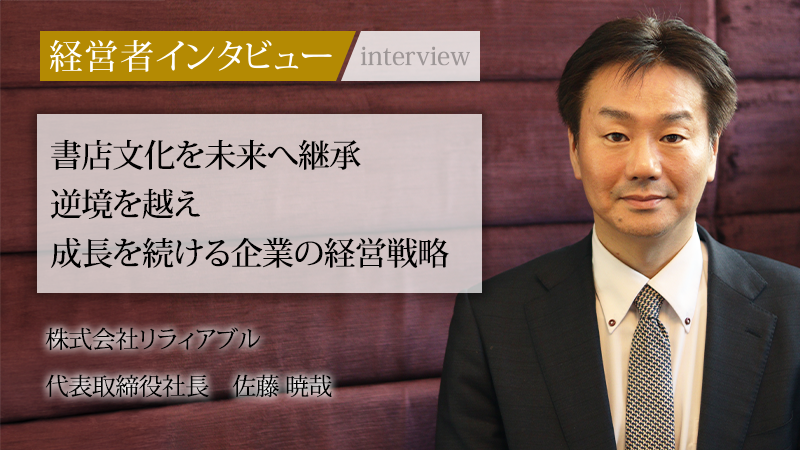
北海道釧路市に本社を構え、大型複合店「コーチャンフォー」を展開する株式会社リラィアブル。書籍、文具、CD、飲食などを融合させた店舗を運営しているのが特徴だ。平均2000坪という圧倒的な店舗面積と豊富な在庫量を武器に、「ない本がない」という顧客の期待に応えている。その結果、出版不況という逆境の中でも着実な成長を遂げている。
創業者である父が築いた礎を受け継いだのは、代表取締役社長の佐藤暁哉氏。異業種での経験を経て家業に戻り、経営方針の転換と時代に即した多角化経営を推進してきた。自らを厳しく律し、人との繋がりを力に変えて会社を牽引する佐藤氏の経営哲学、その先に描く未来像を明らかにする。
父が築いた礎と経営の形 後継者が見出した次なる一手
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせいただけますでしょうか。
佐藤暁哉:
青山学院大学を卒業した後、アメリカへ留学しました。将来のことを熱心に考えていた訳ではないですが、青学の姉妹校でMBAに強い大学があったので、そこで学ぼうと思っていました。しかし留学中の2001年にはアメリカ同時多発テロ事件があり、大学の編入条件が厳しくなり、帰国して就職することになりました。帰国後は大手電機機器メーカーのカタログやマニュアルを制作する会社で社会人経験を積み、29歳で父が創業した弊社へ入社したという経緯です。
ーーご入社当時、会社に対してどのような印象を持たれましたか。
佐藤暁哉:
第一印象は、非常に仕事のスピード感がある会社だということでした。ただ、当時はまだ父が社長として経営の全てを担う、トップダウン、悪く言えばワンマン経営体制だったのです。良くも悪くも、創業者の判断一つで全てが決まる組織でした。父が「やるぞ」と号令をかければ物事が一気に進む強みがある一方、トップ以外の人間から意思決定が生まれにくいという課題も感じました。
常識を覆した直接交渉 逆境を切り拓いた外部連携の力

ーー社長就任後、どのようなことから着手されたのでしょうか。
佐藤暁哉:
就任にあたり、まず自身の役割を明確にすることから始めました。社内の実務、たとえば店舗運営や発注業務においては、ベテラン社員たちには敵いません。彼らは20年来努めてくれており、その知識や経験は非常に豊富です。
幸い、創業者である父が、人が育つための強固な組織の土台を築いてくれていました。一例として、書店事業を始めた当初に設けた「売れ筋ランキング」コーナーが挙げられます。スタッフは毎週売り場を更新する中で、自然と作家や作品名を覚えていきます。こうした自立的な成長を促す仕組みが、既に社内に根付いていました。
その一方で、社内の仕組みが強固な分、社外との関係構築は課題だと感じていました。出版社や作家の方々、文具メーカーといった外部との連携です。そこで、将来を見据えた体制を構築するため、ベテランの知見はもちろん、若手社員の意見も積極的に取り入れながら、社員たちと討議を重ねています。店舗運営については、経験豊富な社員たちに安心して任せることにしました。私は社長という立場でしかできない外部との人脈構築や交渉に重きを置くという方針を明確にしたのです。それが会社の成長にとって最も重要だと考えました。
ーーこれまでで、特に印象深いエピソードはどんなものですか。
佐藤暁哉:
CD事業の責任者を務めていた頃のことです。当時、業界全体が厳しい状況にありましたが、中でも「嵐」のCDは絶大な人気でした。初回限定盤などは入荷と同時に完売する状態だったのです。メーカーに増産を交渉しても「前回の販売実績に基づきます」の一点張りで、完売しているので実績も伸びようがありません。そこで私は「プロデューサーと直接交渉しよう」と考え、あらゆる手を尽くしましたが、さすがに実現しませんでした。
しかし、そこで諦めるのではなく、視点を切り替えました。当時、嵐に次いで売れていたのが「AKB48」です。そこでも「プロデューサーと面識を持とう」と考えました。幸運なことに、ある経営者の集まりでスピーチをする機会がありました。その場で「『会いに行けるアイドル』を掲げるなら、ファンが大勢いる釧路にも来るべきだ」と話したところ、その思いがご本人に届いたのです。そこからAKB48のCDも安定して確保できるようになり、店舗でのイベントも50回以上開催する関係に発展しました。この経験から、目標を決めて行動すれば、道は拓けると強く実感しました。
父を超えるための自己規律 経営の原動力となる目標達成力
ーー経営者として、大切にされていることは何ですか。
佐藤暁哉:
先ほどのような成功体験もそうですが、自分自身に課した目標を達成していくことも大きな原動力です。社長に就任した際、まずは読書家だった父を超えようと決めました。計算したところ、年間200冊の本を読み続ければ、私が50歳になる頃に父の生涯読書量を上回れると分かりました。読書量を増やせば経営者としても尊敬する父に近づける可能性があると考え、それ以来、毎年200冊の読書を続けています。
私はもともと怠け者な性格なので、何かを決めないと動けません。読書だけでなく、体重管理もその一つです。今年に入ってから半年で10kg痩せるという目標を立て、7月のはじめにはちょうど10kg減量できていました。これも、月ごと、週ごとの目標に細分化し、逆算して計画を立てた結果です。達成するためにジムに通う時間を捻出するなど、計画的に行動しました。このことから、自分で管理できる目標は、達成しようと思えば必ずできると考えています。
圧倒的な在庫量が育む信頼 逆境を乗り越える多角化戦略
ーー貴社の事業の強みについて教えてください。
佐藤暁哉:
最大の強みは、1店舗あたり平均2000坪という広大な店舗面積です。そこから生まれる豊富な在庫量も強みと言えます。お客様が「この本が欲しい」と思って来店された際、その本が棚にない状況は最もがっかりさせてしまいます。その体験が、お客様をネット書店へと向かわせてしまうでしょう。そうならないよう、「コーチャンフォーに行けば必ずある」という期待に応え続けることが、弊社の信頼の源泉です。
ーー事業の多角化を進める中で、特に注力されていることは何ですか。
佐藤暁哉:
書籍コーナーの売り場面積は縮小しないようにしていますが、近年は食品事業にも注力しています。弊社では「書籍の売上構成比を50%にする」という経営の軸を長年貫いてきました。市場が縮小したCD事業に代わる新たな柱として、この食品事業を育ててきたのです。
本格的に拡大するきっかけは、コロナ禍での人々の購買行動の変化でした。「一つの店舗で買い物を済ませたい」というニーズを捉えました。このニーズに対応した戦略が功を奏し、理想的な構成比になりました。現在では書籍50%、文房具25%、それ以外のCD売上や食品事業、カプセルトイ、飲食事業などの売上合計が25%です。おかげさまで、CD事業の売上減少分を補って余りあるほどの成長を遂げています。また、文具事業も好調で、幅広いジャンルの文具を取り揃えているため、入学・進学祝いの贈答品としても多くの方にご利用いただいています。
「釧路の企業」としてのプライド 北海道の魅力を発信する地域貢献

ーー創業の地である、釧路への思いについてお聞かせください。
佐藤暁哉:
釧路は人口減少が続くなど、決して明るい話題ばかりではありません。だからこそ、「釧路の企業」として地元を元気づける存在でありたいという強い思いがあります。北海道出身の作家や漫画家の方々を積極的に応援し、大きくコーナー展開するのもその一環です。地元の方々が「この人、釧路出身なんだ」と知ることで、作品を手に取るきっかけになります。それが作家の方々の誇りにもつながることを願っています。
ーーその他、地域貢献のために取り組まれていることはありますか。
佐藤暁哉:
釧路市にある文化会館のネーミングライツを取得したことも、その一つです。これも、もともと利益を考えて始めたことではありませんでした。10年ほど前、文化会館のイベントに子どもと参加しました。その際、1500人規模のホールにもかかわらず和式トイレしかなく、子どもが使えずに困ってしまったのです。
市に改修を要望しても予算がないとのことでした。そこで弊社が取得したネーミングライツの契約金を活用し、トイレを洋式に改修してもらったという経緯があります。みんなが少しでも便利になれば、という思いでしたが、結果的に会社のイメージ向上にもつながっていると感じます。
1000人の心を繋ぐ仕掛け 一体感を醸成する独自の組織文化
ーー組織の一体感は、どのように生み出していますか。
佐藤暁哉:
社員やパート・アルバイトを含めると約1000名のスタッフがいますが、全員が顔を合わせる機会はなかなかありません。そこで、毎年250名規模で温泉旅行を実施し、会社全体の一体感を高めています。コロナ禍で規模は縮小しましたが、入社年次別の海外研修なども行い、店舗間のコミュニケーションを促進しています。こうした場で生まれたつながりが、将来的な転勤などの際にも心理的な支えになると考えています。
ーー人事評価制度については、どのように取り組まれていますか。
佐藤暁哉:
社員のライフスタイルが多様化する中で、様々な事情に配慮が必要だと考えています。たとえば、転勤が難しい社員や、ご家族の介護をされている方といった事情に配慮できる制度が必要です。そこで、評価の「見える化」と「数値化」を進めています。これまでは上司の主観に左右される部分もありました。しかし、客観的な数値基準を設けることで、どの店舗、どの上司の下でも公平な評価が受けられる仕組みを構築している最中です。ワークライフバランスを重視し、誰もが安心して長く働ける環境を整えていきたいです。
書店文化と小説家を守る使命 未来へ繋ぐための成長戦略
ーー今後の展望についてお聞かせください。
佐藤暁哉:
大前提として、「書店文化を守る」という思いは、これからも絶対に揺らぎません。その大切な場所を未来に残していくためにも、会社の成長は不可欠です。具体的な出店計画としては、3年に1店舗のペースで着実に店舗数を増やしていきたいと考えています。人材確保の観点から当面は関東と北海道が中心です。しかし、将来的にはその他地域の中核都市への進出も視野に入れています。
そして、店舗拡大と並行して、事業の柱もさらに強化していく必要があります。食品事業に続く、もう一つの核となる事業を育てていきたいです。たとえば、最近では北海道の木材を使ったオリジナルの筆記具を開発しました。このように、地域性を活かした新商品の開発にも取り組んでいます。最近では社内から様々な提案が出てくるようになりました。新規事業や新商品の開発、お客様サービスなどもどんどん意見が出ています。
ーー最後に、佐藤社長が成し遂げたい目標を教えてください。
佐藤暁哉:
「書店文化を守り、小説家を支援すること」です。本が売れなくなれば、素晴らしい物語を生み出そうとする人が減ってしまいます。それは社会にとって大きな損失となり得ます。その連鎖を断ち切るために、私たちは人々が本と出会えるリアルな場所を守り抜きます。
そのために、圧倒的な品揃えでお客様の期待に応え、児童書に力を入れて未来の読者を育みます。弊社の店舗が、ただ本を買う場所ではなく、新たな発見や喜びが生まれる文化的な空間であり続けなければなりません。
同時に、物語を生み出す作家の方々への支援も欠かせません。サイン会などを通じて作家と読者が直接繋がる機会を創出します。そうすることで、創作活動の活力を生み出すお手伝いをしています。立場上小説家の方にお会いする機会は多いのですが、会う前にその方の作品はできる限り全て読んでからお会いするようにしています。作家が安心して創作に打ち込み、その作品が読者の元へ届く。この大切な循環を、事業を通じて支え続けることこそが弊社の最大の使命だと考えています。
編集後記
業界に逆風が吹く中、強い信念を掲げ、成長を続ける株式会社リラィアブル。その舵を取る佐藤氏の言葉からは、創業者への敬意と、未来への冷静な洞察が感じられた。そして何より、人を大切にする温かい人柄が伝わってくる。北海道の大地から生まれたこのユニークな企業が、日本の文化にどのような新しい光を灯していくのか、その未来が楽しみでならない。

佐藤暁哉/1978年、宮崎県宮崎市生まれ。2001年青山学院大学卒業後、海外留学、一般企業への入社を経て、2007年に株式会社リラィアブルへ入社。2013年に取締役、2016年に常務取締役、2018年より代表取締役社長に就任。














