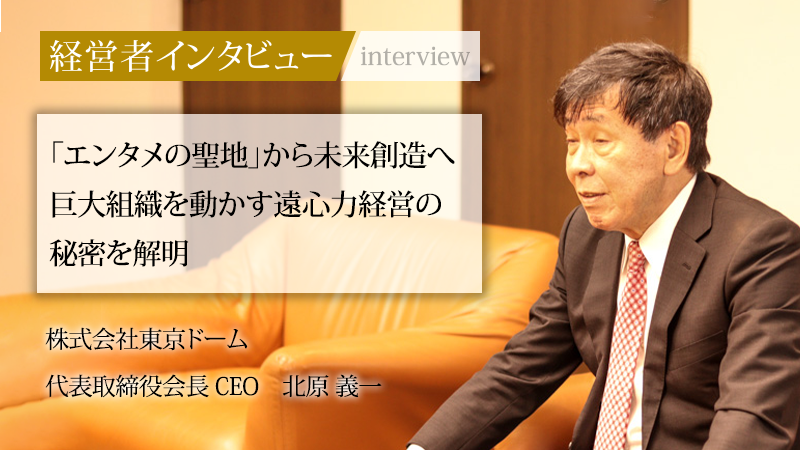
ハード、ソフト、コンテンツという三拍子が揃い、年間約4000万人(2019年度)が訪れる東京ドームシティ。この巨大施設の経営に、三井不動産で「街づくり」に情熱を注いだキャリアを経て、ホワイトナイトとして参画したのが北原義一氏だ。本記事では、北原氏の歩みと共に、同社がWeb3(※1)などの最先端技術を駆使して描く、国境を越えた未来への壮大なビジョンを明らかにする。
(※1)Web3:ブロックチェーン技術を活用した次世代の分散型インターネット。ユーザーがデータを分散的に管理し、相互に直接やり取りできることが特徴。
街づくりへの情熱から始まったキャリアと東京ドームへの道
ーーどのような経緯で三井不動産に入社されたのでしょうか。
北原義一:
大学時代メディアを志していました。しかし、たまたま訪問した三井不動産で、不動産デベロッパーの仕事について知る機会がありました。その仕事は単なる建物の建設ではなく、国づくりそのものだと感じ、心を動かされて入社を決意しました。
入社後は首都圏のニュータウン開発や広島での埋め立て事業など、一貫して街づくりに携わっています。
1993年に東京へ戻ったとき、日本はバブル崩壊の真っただ中で、銀行が企業へのお金の貸し出しを極端に絞るようになっていました。そのため、これまでのように銀行から融資を受けて開発を進めることが非常に難しくなったのです。
そこで私たちは、銀行を介さずに多くの投資家から直接資金を集めて不動産事業を行う、当時としては新しい資金調達の方法を開拓しました。この手法の導入は、日本の不動産取引の慣習も一変させました。「お互いを信頼し、細かいことは後から話し合って決めよう」という日本のやり方から、「万が一のトラブルを全て想定して、事前に契約書へ細かく書き込む」という欧米のやり方への転換が求められ、慣れない対応に大変なエネルギーを費やしました。
ーーその後、東京ドームに関わることになった経緯をお聞かせください。
北原義一:
東京ドームがアクティビストから経営要求を突きつけられていた際、三井不動産がホワイトナイトとして名乗りを上げ、私が交渉の代表を務めました。最悪の場合、このエンタメの聖地が失われる可能性もありました。それを回避すべく交渉を重ね、最終的に三井不動産の資本参加という形で円満解決に成功したのです。
ーー東京ドームに入られて、どのような印象を持たれましたか。
北原義一:
創業90年で育まれた「人に優しい」企業文化に非常に魅力を感じました。性善説に立ち、チームスピリットを重んじるメンバーシップ型の組織です。さまざまな専門性を持つ社員たちが、お客様に笑顔や感動を届けたいという強い思いで一丸となっています。この素晴らしい文化は絶対に守り、継承していかなければならないと固く心に誓いました。
多様な施設が融合する総合エンターテインメントシティ
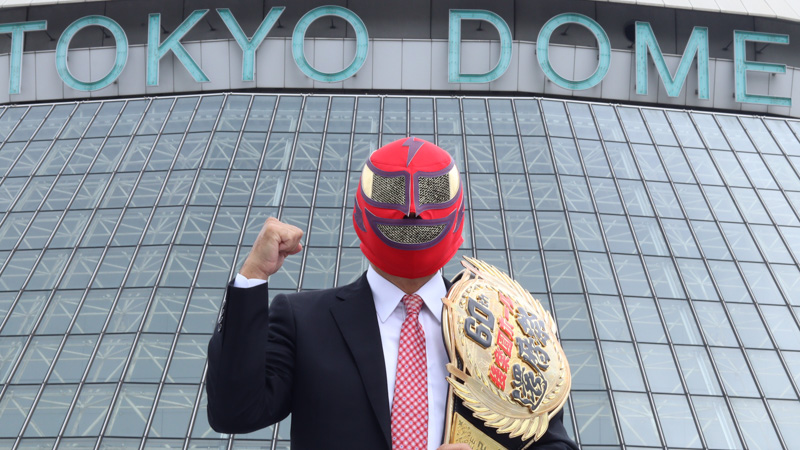
ーー改めて、東京ドームシティとはどのような事業体なのでしょうか。
北原義一:
東京ドームシティは、東京ドーム(愛称:ビッグエッグ)だけを指すのではありません。遊園地、ホテル、温浴施設などが集積する、約13ヘクタールの複合エンターテインメントゾーン全体のことです。これほど多様な施設が一箇所に集まっている場所は、世界にも類を見ません。弊社の事業は、「ハード」「ソフト」「コンテンツ」の三拍子が揃って初めて成り立ちます。
「ハード」は物理的な施設群です。そして、これを運営するのが「ソフト」。協力会社の方々も含めると1日に約6000人が働き、お客様をお迎えするオペレーション能力が私たちの貴重な財産です。最後に最も重要なのが「コンテンツ」。ビッグエッグを例に挙げると、読売ジャイアンツの公式戦を中心とした野球イベントが年間約100日、音楽コンサートが約100日。その他イベントや準備日等を含めると、ほぼ100%に近い稼働率を誇ります。
他のホールでも演劇や展示会などが日々行われ、施設全体で多種多様なエンターテインメントを提供しています。このハード、ソフト、コンテンツの掛け算こそが、年間約4000万人ものお客様を魅了する力の源泉です。
テクノロジーを駆使し世界へ飛び出していく

ーー今後のビジョンとして、まずどのような課題認識をお持ちでしょうか。
北原義一:
日本の少子高齢化を考えると、海外からのお客様もより重視する必要があります。もちろん、これまで通り国内のお客様も大切にしていきます。実際、東京ドームホテルの海外客比率は5割を超え始めており、国際化への対応は急務です。
ーー今後の展望をお聞かせください。
北原義一:
年間の来場者は約4000万人です。しかし、地球上の残り79億人以上の方々には、まだ私たちのサービスが届けられていません。そこで、AIやメタバースといった最先端技術を駆使します。そうすれば、物理的な距離やさまざまな事情で来られない方々にも、リアルに近い体験を届けられるはずです。「DXを活用して世界中に飛び出していく」をテーマに、世界中に笑顔や感動を届けたい、それが私たちの夢です。
また、Web3やDAOといった新しい概念を取り入れた挑戦も進めています。私たちはエンターテインメントをキーワードにしたDAO(自律分散型組織)をこの場所で構築しようとしています。これは規模の追求ではなく、価値観を共有する人々のための幸せな経済圏をつくる実験です。社会を変えるきっかけをエンターテインメントから生み出したいと考えています。
ーー企業文化の変革については、どのようなお考えですか。
北原義一:
これまでは内向きの求心力が強い組織でした。しかし今後は、社員一人ひとりが外に向かってフルスイングできる「遠心力」を働かせることが重要です。5年前には新規事業の創出を目的とした「mokuMOKU」という社内提案制度をスタートさせ、各自の事業アイデアを磨く支援プログラム構築のもと、定期的なピッチコンテストを実施しています。
こういったプロジェクトを皮切りに外向きの企業文化をより加速させていければ、いつかは社員が会社という傘の下で半独立的に新規事業を立ち上げ、個人としてリスクを取りリターンを得られる仕組みづくりなども実現できるかもしれません。個人の活力を最大限に引き出し、会社全体の生産性を高めていきたいと考えています。
編集後記
北原氏のキャリアは、常に大きな挑戦の連続だ。その根底には、組織が持つ「チームスピリット」への信頼と、それを守りつつ世界で勝つという強い意志がある。Web3を現代資本主義への処方箋と捉える視座の高さに驚かされる。東京ドームが仕掛ける次の一手が、日本のエンタメ、ひいては社会にどのような変革をもたらすのか期待が膨らむ。

北原義一/1957年東京都生まれ。1980年、早稲田大学政治経済学部卒業後、三井不動産株式会社に入社。ビルディング事業企画部長、常務執行役員、本部副本部長、専務執行役員 、副社長執行役員、代表取締役 副社長執行役員、取締役 グループ上席執行役員を務め、2023年には特別顧問として就任(現任)。2021年、株式会社東京ドーム 取締役。2022年に同社代表取締役会長 CEOに就任。














