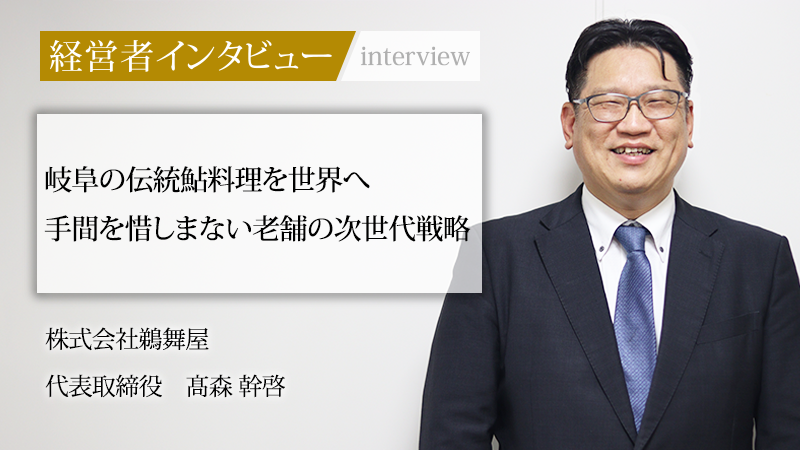
岐阜県の豊かな自然が育む鮎や地元の食材を活かし、岐阜の食文化を継承する株式会社鵜舞屋。創業明治10年、140年以上の歴史を持つ老舗メーカーとして、代々受け継がれてきた伝統の味を守り続けている。一方で、時代の変化に対応するため、常に革新を追求する同社は、長年培ってきた高い技術力を武器に、新たな挑戦を続けている。今回は、鵜舞屋の代表取締役である髙森幹啓氏に、商品へのこだわりや事業の転換期、そして日本の食文化を世界に広めるための取り組みについて、熱い思いをうかがった。
大手での経験と「つくる側」への転身
ーー社会人としてのキャリアと、鵜舞屋に入社された経緯をお聞かせください。
髙森幹啓:
人々の笑顔に直接つながる仕事がしたいと考え、食の道を志しました。社会人としてのキャリアは、新卒で入社した大手スーパーの加工食品売り場からスタートしました。当時は朝早くから夜遅くまで働くのが当たり前で、先輩からの指導も非常に厳しかったのですが、そのおかげで社会人としての基礎を築くことができたと感じています。
その後、子どもが生まれたことをきっかけに転職を決意しました。転勤が多い環境だったため、家族のためにも一つの土地に腰を据えたいと考えたのです。また、誰かがつくったものを売るのではなく、自分で何かをつくる側に回りたいという思いもあり、鵜舞屋への入社を決めました。
ーー鵜舞屋でのご経験や、社外での取り組みについてもお聞かせください。
髙森幹啓:
入社した当初は、営業を担当していました。岐阜の県魚である鮎の甘露煮は、当時はまだ全国的な知名度が低く、大手総合スーパーなどに売り込みに行くのは大変なものでした。しかし、私たちは「安かろう悪かろう」ではない、本当に良いものをつくっているという自負がありました。誰かだけが儲かるのではなく、取引先も、私たちも、そしてお客様も満足する「三方よし」の商売をしたいと常に考えていました。その思いで営業に取り組んでいたことが、今につながっていると思います。
そうした事業経験と並行して、私は2016年から県立高校で特別非常勤講師として商品開発の授業を担当しています。若い世代に食やものづくりの楽しさを伝えることで、未来の担い手を育むことにも貢献したいと考えているのです。
新たな挑戦で拓く鮎料理の未来
ーー新型コロナウイルスの影響から市場の状況は大きく変化したと思いますが、貴社にはどのような変化がありましたか。
髙森幹啓:
コロナ禍で最も大きな打撃を受けたのはギフト事業です。お中元やお歳暮といった贈答品の需要が大幅に減少し、これまでのビジネスモデルが通用しなくなりました。しかし、この危機をきっかけに私たちは自らの原点、すなわち事業の核である「鮎」そのものの価値にもう一度立ち返ることにしたのです。そして、この鮎の魅力をギフトという形に限定せず、より多様な形で世界中のお客様に届けるべきだという結論に至りました。
以前から、岐阜県の県魚である鮎を世界に広めることや、飲食店で利用してもらうことなどの構想はありましたが、コロナ禍が後押しとなり、一気に取り組みを加速させたのです。
ーー商品づくりで特に大切にされていることは何でしょうか。
髙森幹啓:
私たちは、お客様に「美味しい」と心から感じていただくため、手間を惜しまず、一つひとつ手作業で丁寧に商品をつくることにこだわっています。この丁寧な手作業は、同時に原料である鮎そのものを深く見極めることにも繋がります。だからこそ、私たちは最高の原料を仕入れることにも一切妥協しません。この「手間」と「原料へのこだわり」を突き詰めてきた結果、「鮎のことなら鵜舞屋に相談すれば良い」という評価をいただけるようになったのです。
ーーこれからの事業について、どのような新しい展開をお考えでしょうか。
髙森幹啓:
これまでのギフト事業に加え、新たな柱として海外展開と、国内の外食産業に向けたセントラルキッチン事業という、大きく二つの挑戦を始めています。
ーー海外展開について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
髙森幹啓:
私たちは単に商品を輸出するのではなく、「日本の食文化」そのものを海外に伝えたいと考えています。たとえば、ベトナムのレストランに鮎を輸出する際は、日本の職人が現地に赴き、包丁の使い方やさばき方、美しい盛り付けまでを直接指導します。食材だけでは伝わらない日本食の奥深さを知ってもらうことで、その価値を世界で高めていきたいのです。
ーーもう一つの柱である「セントラルキッチン事業」とは、どのようなものでしょうか。
髙森幹啓:
これは、人手不足に悩む外食産業をサポートするための取り組みです。私たちの工場で食材の9割を調理・加工し、お店では簡単な最終仕上げをするだけで料理が完成する状態で提供します。これにより、調理の手間を大幅に削減し、店舗の負担を軽減することに貢献しています。
歴史に安住せず、常に変革し続ける伝統

ーー工場での生産や品質管理で注力していることはありますか。
髙森幹啓:
安心安全は当たり前ですが、私たちはさらに国際基準に沿った生産管理を目指しています。認証を取得することが目的ではなく、取得する過程で世界基準の工場へと変革することが重要です。たとえば、工場内にダンボールを持ち込まないようにすることで、生産性は一時的に落ちますが、異物混入のリスクを低減することができます。
ーー140年以上続く老舗として、伝統をどのように捉えていらっしゃいますか。
髙森幹啓:
伝統とは、ただ歴史が長いということではありません。昔からやってきたから大丈夫、と安住するのではなく、その時代に合わせてしっかりと学び、検証し、次の世代に伝えていくことが伝統だと思っています。時代に合わせて基準を変え、常に変革し続けることが、私たちの使命だと考えています。
ーー最後に、今後の展望や、求職者に向けたメッセージがあればお聞かせください。
髙森幹啓:
何が正解か分からない時代だからこそ、「挑戦し続ける姿勢」が何よりも大切だと考えています。私たちの仕事は、日本の食文化を通じて人々の心を豊かにすること。そのために、学歴や肩書きではなく、仕事にどう向き合うかが重要です。
私たちのような中小企業には、一人ひとりの力で会社を動かし、世の中に貢献できる大きな可能性があります。一時的なブームではなく本物の価値を届けたい、そんな思いに共感してくださる方と、ぜひ一緒に未来をつくっていきたいです。
編集後記
今回お話をうかがった髙森氏の言葉からは、鵜舞屋が140年以上も愛され続ける理由がひしひしと伝わってきた。単に良いものをつくっているだけでなく、その裏側にある手間や生産者の思いを大切にする姿勢、そして「日本の食文化を未来につなぐ」という使命感が、同社の事業の軸になっていると感じる。特に、伝統を「歴史の長さ」ではなく「時代に合わせた変革」と定義する考え方に感銘を受けた。安易な安売りをせず、本物の価値を伝え続ける同社の今後の活躍に、目が離せない。

髙森幹啓/1976年三重県で生まれ、高校卒業後に株式会社ニチイに入社、2000年に鵜舞屋に転職をし、2013年6月に代表取締役に就任。2016年より県立高校の特別非常勤講師を拝命され、商品開発の授業に参加。














