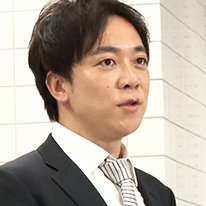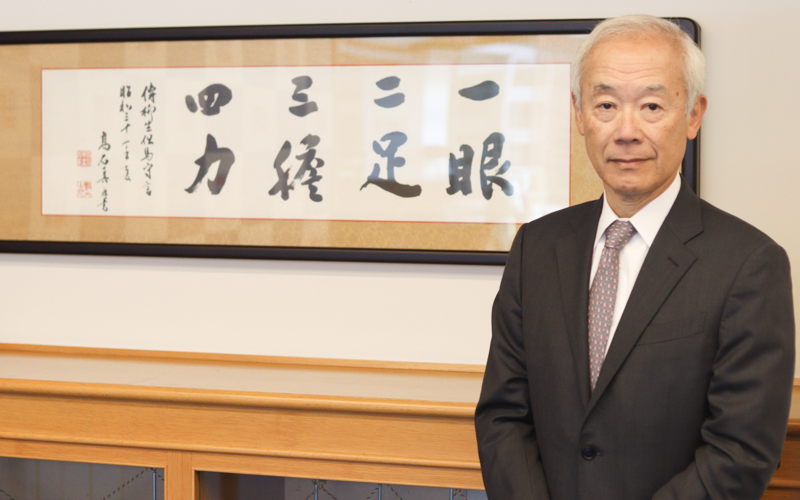新型コロナウイルスの影響で人々の生活様式が大きく変化し、広告業界もデジタル化の加速に直面した。特に、OOH(※1)広告は、データを活用した精緻なデジタルOOHメディアへと進化しつつある。そうした潮流の中で、注目を集めるのが株式会社 LIVE BOARDの取り組みだ。同社はNTTドコモと電通グループ、博報堂の合弁会社である。2025年に代表取締役社長へ就任した髙木智広氏に、事業の特徴や今後の展望をうかがった。
(※1)Out of Homeの略。交通広告や屋外広告、商業施設での広告など、家庭以外の場所で接触する広告媒体の総称
「TVer」「AbemaTV」の事業推進の経験を現在の事業に活かす
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせいただけますか。
髙木智広:
2003年に電通に入社しました。学生時代に野球をしていたこともあり、スポーツコンテンツに関わりたいと考えていたためです。当時はテレビ局に憧れていて、特にスポーツ番組の持つ力に魅了されていました。
入社後は全国100以上の地方テレビ局を担当し、広告ビジネスや企画開発に従事。自ら企画して実現した番組もあります。たとえば、広島出身の芸人さんの東京進出に密着したドキュメンタリー番組という企画を立てました。広島テレビが「制作費をしっかり取ってくれればうちで流します」と企画に乗ってくれたおかげで番組制作が進み、放送が実現したのです。テレビ番組をつくることはずっと夢でしたし、自分が考えたサブタイトルを使ってもらえたこともあって、大きな達成感につながりました。
ーー電通での経験は現在の貴社の事業にどのように影響していますか。
髙木智広:
電通では地方局担当の後、TBSの担当を経てメディアコンテンツプランニング局に異動しました。ここで世界的なスポーツ大会のセールスを手がけ、本格的にスポーツビジネスに携わるようになったのです。
ただ、デジタル領域の勢いが増している中で、今後のメディアのあり方について考えるようになりました。そんな中、2016年に新設された動画ビジネス推進部門への異動を命じられました。「TVer」「AbemaTV」の事業推進のためです。当時、動画サービスが始まったばかりの時期で、テレビでもデジタルでもない新領域を開拓する必要がありました。私は初期メンバーの一人として、テレビとデジタルの間をつなぐビジネスを推進しました。
この挑戦を通じて、私はOOHのデジタル化に可能性を感じました。従来のアナログのOOHがなくなることはないでしょう。しかしデジタルOOHマーケットの伸びしろはとても大きく、事業として取り組む価値は十分にあります。当時のそんな可能性を感じたことが今の事業と深くつながっています。
その後、2019年にテレビ朝日系列のビジネス開発全般を推進し、2025年に弊社の代表取締役社長に就任しました。
日本初のインプレッションベースによるプログラマティックOOHで広告主に貢献

ーー貴社の事業について教えてください。
髙木智広:
弊社はNTTドコモ・電通グループ・博報堂の合弁会社です。事業内容としては、デジタルOOH広告プラットフォーム「LIVE BOARDマーケットプレイス」の運営、デジタルOOH広告媒体の開拓、デジタルOOH広告枠の販売を行っています。
LIVE BOARDの最大の特徴は、NTTドコモの位置情報データ等により、広告がどれだけ見られたかを数値で可視化できる点にあります。OOHは長年、大きな課題を抱えてきました。「実際に何人の人が広告を見たのか分からない」「広告効果を数値で示せない」という2点です。
テレビやデジタルでは視聴者数や効果をデータで検証できますが、OOHはどうしても曖昧な評価しかできませんでした。こうした課題を解決するために、私たちLIVE BOARDは2019年2月1日に設立され、日本で初めてインプレッションベースのOOH広告取引を実現しています。
ーー他にも特徴はありますか。
髙木智広:
弊社は設立当初からインプレッション計測の国際基準の中で最も厳しい基準である「VAC(Visibility Adjusted Contact )/のべ広告視認者数」(※2)を採用しています。これはNTTドコモのビックデータ等を用いて計測しています。これによりOOHを単なる通行量ではなく、広告が実際に届いた人数をより正確に評価できるようになりました。
またコロナ禍で人流が大きく減少した際には、改めて広告主や広告代理店から「屋外広告の価値は何か」が問われることとなり、データを用いた計測は出稿を検討する判断材料として活用されました。
(※2)LIVE BOARD は、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション(VAC=Visibility Adjusted Contact/のべ広告視認者数)を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数(OTS=Opportunity to See)のうち、OOH広告に接触する可能性のある、のべ人数(OTC=Opportunity to Contact/視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮)を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろう、のべ人数(VAC)を推計しています。
売上100億円の達成には「見えない壁に挑む力」を持った人材が不可欠
ーー今後の事業成長に向けた戦略と組織づくりの方針について教えてください。
髙木智広:
弊社は2025年9月18日に設立された「一般社団法人日本OOHメジャメント協会」に、設立準備段階から参画しています。本協会は広告主・広告会社・媒体事業社など広告業界全体を対象とした業界横断組織で、OOH広告の価値を可視化する業界共通指標を提供し業界の発展に寄与することを目的としています。これにより、OOH広告の価値がより明確になり、市場全体の成長がさらに加速すると期待されます。弊社も協会の一員として、OOH広告業界の発展に貢献できるよう尽力してまいります。
業界全体に貢献する活動を推進する一方で、社内の組織面では、出向社員と直接雇用の社員は契約社員が中心だったところから、無期雇用制度を導入し、社員が長く働きキャリアを築いていける環境を整えています。将来的には新卒採用も検討しており、経験以上に「見えない壁に挑む力」を持った人材を求めています。
「LIVE BOARD」のある街を明るく活気ある空間にしたい
ーー「LIVE BOARD」のメディアとしての将来像をどう描いていますか。
髙木智広:
弊社の自社媒体は、単なる広告枠の提供にとどまらず、生活者にとってワクワクするようなコンテンツを配信するメディアにすることが目標です。天気やニュースといった生活に役立つ情報に加え、思いがけない情報との偶然の出会いを演出することで、スクリーンを見ること自体が楽しい体験となるような機会を創出し、街に新しい価値をもたらしていきます。
最終的には「LIVE BOARD」のある街が、明るく活気ある空間になることに貢献したいです。また、広告業界における弊社の目標もあります。それは、テレビとデジタルに次ぐ「第三のメディア」としてデジタルOOHの価値を確立することです。これら3つのメディアを合わせた「トリプルメディアプランニング」の一角として、業界の中核を担いたいと考えています。
編集後記
今回のインタビューを通じて感じたのは、髙木氏の挑戦を楽しむ姿勢だ。テレビとデジタルの狭間での新規事業の推進経験や、OOH業界のデジタル化を推進した実績。そうした未踏の領域を切り拓いてきた経験が、言葉の端々からにじみ出る。今後、生活者の身近にある屋外広告がどう進化するのか。「LIVE BOARD」の動きに注目したい。

髙木智広/2003年、株式会社電通に入社。テレビ局で放送局担当として広告ビジネスを中心に番組コンテンツ、企画開発などに従事。2011年からMCプランニング局でメディア・コンテンツのプランニングとバイイングに携わる。その後、国内動画配信サービスの黎明期に、テレビとデジタルの融合である動画ビジネスを担当。2019年からテレビ朝日系列のビジネス開発全般を推進。2025年、株式会社LIVE BOARD代表取締役社長に就任。