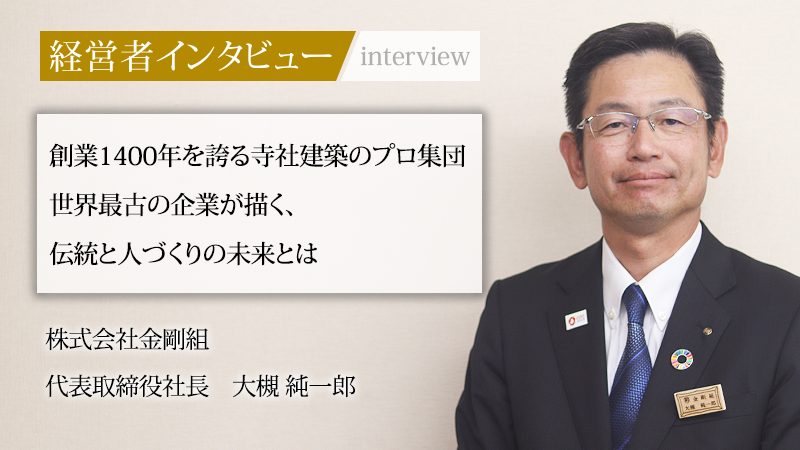
西暦578年創業の株式会社金剛組。聖徳太子の時代から1400年以上にわたり、日本の寺社建築を専門に手掛け、「世界最古の企業」と言われているが、その歴史は、幾多の時代の荒波を乗り越えてきた挑戦の連続でもあった。代表取締役社長の大槻純一郎氏は、長年銀行員として数多くの経営者に接してきた経験を持つ。外から見てきた経営者の世界と、自らがトップとして立つ場所から見える景色は、どう違うのか。歴史の重圧、幾多の危機を乗り越えた秘訣、そして日本の宝ともいえる伝統建築技術を未来へつなぐための人づくりまで、その思いに迫る。
銀行員から経営者へ、見えてきた景色の違い
ーー社長のこれまでのご経歴についてお聞かせください。
大槻純一郎:
私のキャリアの出発点は銀行員です。当時は企業の経営者や役員の方々と直接お話しし、経営上のさまざまな課題についてのご相談を受け、一緒に解決策を模索してきました。数多くの経営者の方々の視点や考え方に触れることができたことは、現在の職責を果たす上で非常に大きな財産となっています。
やがて、キャリアの転機が訪れます。銀行では当時、50代前半で第二のキャリアを歩み始めるのが一般的で、私もその慣例に沿って、銀行員時代に接点があった髙松建設に出向しました。半年後に正式に籍を移し、管理部門や関連会社の役員として3年ほど経験を積んだのち、弊社の社長に就任しました。
銀行員時代、経営者の方々が重圧に耐えながら日々判断し、前進しておられる姿を見てきました。その重圧を理解しているつもりでしたが、いざ自分が経営者の立場に立つと、想像以上の重みを痛感しました。
ーー仕事をする上で、指針とされている考え方はありますか。
大槻純一郎:
銀行員時代にお客様からいただいた「心戒十訓」は、今の私の指針です。今でも机のマットの下に置き、自らを省みる際に立ち返るべき教えとして大切にしています。神社仏閣の仕事に携わっているため、素晴らしいお話に触れる機会も多く、大変恵まれたことだと感じています。
1400年以上の歴史と幾多の危機
ーー貴社のこれまでの長い歴史の中で、語り継がれているエピソードはありますか。
大槻純一郎:
創業から1447年という長い歴史を紡いできましたが、その道のりは決して順風満帆だったわけではありません。特に歴史の大きな転換点では、常に存続の岐路に立たされてきました。
最初の危機は明治維新です。それまで金剛組は四天王寺さまのお抱え大工でした。しかし、「廃仏毀釈」によって仏教が弾圧を受け、寺院の力が弱まっていきます。その大きな波の中で弊社も、約1300年間お世話になってきた四天王寺さまの他にも、開拓営業で新たに仕事を得なければならないという大きな試練を迎えました。
昭和の時代にも、再び危機が訪れます。腕利きではあるものの職人気質の当主が経営に苦しみ、昭和恐慌も相まって会社は存続の危機に。しかし、その妻が当主として後を継ぎ、倒壊した四天王寺五重塔の再建を見事に成し遂げ、会社を立て直しました。また、戦時中は政府による「企業統廃合政策」によって、またも廃業の危機に見舞われます。この時も軍に掛け合い軍事用の木箱を製造することでその命脈を保ちました。
さらに戦後にも、社寺建築に加え、時代の流れに乗って一般建築分野へも業容を拡大したのですが、これが裏目に出ます。不慣れな一般建築の対応に苦労して経営が傾き、その窮地を救ったのが、同じ大阪の企業である髙松建設でした。「金剛組を潰したら大阪の恥だ」と、私たちの技術と人を守るために支援の手を差し伸べてくださったのです。そのおかげで、それまでと同じ形で再スタートすることができました。
ーー事業を長く続けてこられた秘訣はどこにあるとお考えですか。
大槻純一郎:
「能力主義」を貫いてきたことだと思います。代々の当主は、家系の長男が自動的に継ぐのではなく、当主にふさわしい能力や信念、リーダーシップを兼ね備えた人物が、分家や婿養子なども含めて選ばれてきました。能力にこだわり、会社をしっかりと率いていける人物を据え続けたことが、金剛組の技術と施工品質を守り続け、幾多の危機を乗り越える力になったと考えています。
伝統を未来へ、人づくりという使命

ーー技術を次世代へ継承するために、どのような取り組みをされていますか。
大槻純一郎:
宮大工の世界は、一人前になるのに10年はかかるといわれる厳しい世界です。残念ながら、高齢化とともに担い手は減っています。仕事をいただいても、それに応える職人がいなければ、技術の伝承はできません。次世代を育てなければ、この国の宝ともいえる技術が途絶えてしまうという強い危機感を持っています。
そこで弊社では、宮大工の登竜門として20歳前後の若い希望者を対象に、「匠育成塾」を開講しています。ここでは6カ月にわたり、棟梁が直接指導して技術の基礎を伝えます。これは単に技術を教えるだけでなく、本人の本気度や適性を見極める場でもあります。6ヶ月後、棟梁と塾生双方の合意が得られれば、金剛組専属宮大工の一員として宮大工の道を歩み始めることになります。彼らに活躍の場を提供し続けることも、私たちの重要な使命だと考えています。
ーー会社の未来、そして日本の文化についてどのような思いをお持ちですか。
大槻純一郎:
近年、海外からも多くの方が日本の伝統文化に触れるため、お寺や神社を訪れます。日本の寺社建築が持つ造形美は、国を越えて人々の心を癒やす力があると信じています。私たちの仕事は、単に建物を建てることだけではありません。建てた後、その歴史的建造物を何百年・何千年という単位で後世に残すため、維持管理することも非常に重要な仕事です。日本の魅力的な文化を、世界中の人々に触れてもらうため、これからも技術を継承し、守り続けていきたいと思います。
編集後記
1400年という時間の重みを一身に背負い、大槻社長は静かに、しかし力強く未来を見据えていた。銀行員として多くの企業を見てきた外部の視点を持つからこそ、伝統の価値を再認識し、現代の課題に柔軟に対応できるのだろう。次代を担う職人を育てる「匠育成塾」の話からは、単に企業を存続させるだけでなく、日本の文化そのものを未来へつなぐという強い意志が感じられた。同社の挑戦は、文化の守り手としての使命をかけた、壮大な物語の続きといえる。

大槻純一郎/1966年生まれ。大阪府出身。1989年関西大学経済学部卒業後、株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)に入行。2017年みずほ銀行名古屋中央支店長に就任。2020年6月、髙松建設株式会社に出向、同年10月に同社に入社。同社で執行役員本社管理本部長などを経て、2024年4月に株式会社金剛組の代表取締役社長に就任。「人を大切にする人は人から大切にされる」(『心戒十訓』)をモットーとして社業に邁進。














