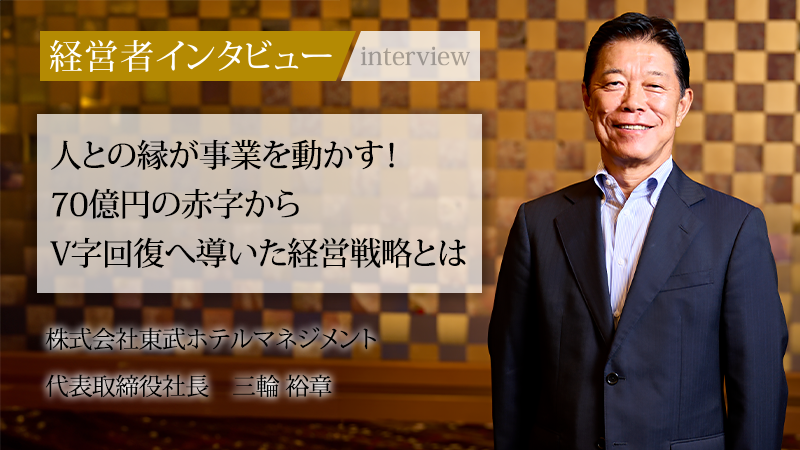
東武グループの一翼を担い、沿線価値向上に貢献する株式会社東武ホテルマネジメント。同社は厳しい経営状況からの回復を目指し、地域との連携を深める独自の取り組みを進めている。数々の困難な交渉を乗り越え、東武鉄道株式会社で多岐にわたる経験を積んできた代表取締役社長の三輪裕章氏。畑違いと語るホテル業界で、いかにして改革の糸口を見つけ、社員と共に未来を描いているのか。その経営哲学の根底にある「人との縁」と、地域に必要とされるホテルが目指す姿について話をうかがった。
労使交渉の最前線で培われた「対話」の流儀
ーー東武鉄道へ入社された経緯と、キャリア初期のご経験についてお聞かせください。
三輪裕章:
父が国鉄勤めだった影響もありますが、私自身「二本の鉄路の先には夢がある」という思いを抱いていました。なかでも東武鉄道は通勤、貨物、観光と輸送サービスの裾野が広く、その点に魅力を感じたのです。もともと天邪鬼な性格でして、華やかな場所よりは、少し落ち着いた環境のほうが自分には合っていると感じていました。入社後は1年間の現場研修を経て、希望とは異なる人事部へ。そこで労働条件や人件費などを扱う労務の仕事に携わることになりました。
ーー労務担当として、どのようにして数々の交渉を乗り越えてこられたのでしょうか。
三輪裕章:
とにかく、徹底して話すことです。そして、その場で答えを出す。会社の案をただ説明するのではなく、組合からの指摘に対してどうすればいいのかを自分の言葉で語る必要があります。ダイヤ改正などの交渉では、毎回3、4日は徹夜が続きました。そうした経験を通じて、鉄道事業の全てを学び、現場の人たちとの繋がりもできました。特に大変だったのは、約1,700人規模のバス事業の分社化です。組合とは4年ほどかけて話し合い、一時はホテルに泊まり込みで交渉を続けました。このまま鉄道事業の中で縮小していくより、バス事業として独立し、自分たちの仕事を守れるようにしようと訴え続け、最終的に合意に至りました。
人との縁が不可能を可能にしたSL復活事業
ーー経営者としての信念は、どのようなご経験から培われたのでしょうか。
三輪裕章:
やはり「人」ですね。自分の人生を振り返ると、人に恵まれてきたと感じます。40年以上も同じ上司と仕事をしてきましたし、交渉相手の労働組合の方々からも多くのことを教えてもらいました。また、これはあまり公にしてこなかった話ですが、中学時代に旅先で出会った方が、のちにJR西日本の社長に就任された来島達夫さんでした。そうした方々との出会いに助けられて、今の私を形づくっています。
ーーこれまでに手がけられたお仕事の中で、特に印象深いプロジェクトは何でしょうか。
三輪裕章:
やはりSLの復活事業ですね。これも、来島さんとの繋がりがなければ決して実現しなかったでしょう。そもそもSL復活を検討し始めた際、弊社には肝心の機関車がありませんでした。来島さんにご相談したところ、「応援するよ」と力強いお言葉をいただけたのです。その言葉を支えに、まずは社内で説得を続けました。
もちろん、事業である以上、採算性の課題は避けて通れません。私たちは、新しい特急の二次交通としてSLを位置づけることで「時空を超える旅」という新たな価値を創造するコンセプトを打ち出し、東武博物館が機関車を保有して、それを鉄道会社が借りて運行するという、前例のない仕組みを考案することで、なんとか実現への道を拓いたのです。
振り返りますと、来島さんや鉄道8社をはじめとする社内外からの支援、現場で地元の方々との信頼関係を築き上げてくれた営業・運輸の社員の頑張りなど、多くの人との縁と力添えがあったからこそ、不可能が可能になったのだと感じています。
「敵が来る」からの挑戦 ホテル事業再建にかける思い

ーーホテル事業の社長にご就任された当初、どのような印象をお持ちでしたか。
三輪裕章:
率直に申し上げて、事業性が悪いとの印象でした。私が労務を担当して、グループ全体の収支を組合に説明する時、赤字というイメージがホテル事業でした。事業に対する収支という側面と事業に対する主体性について、ずっと厳しい意見を述べていましたから、「それならお前がやってみろ」という形で送り込まれたのだと思います。就任当時は70数億円の負債と40数億円の債務超過で、社内は“敵が来る”という雰囲気だったと思いますよ。
ーー厳しい状況の中、どのようにして改革の糸口を見つけたのでしょうか。
三輪裕章:
就任当初の本社は狭く、従業員食堂の裏にある休憩所に身を置くことが多かったのです。そこにいたのが、調理部門のスタッフでした。彼らは得意の料理があっても、お客様に毎日自分の料理を食べてほしいと、常に新しい変化を求めていくアンテナが高く、話していて面白い。やもすると前例踏襲に陥りがちな本社の社員とは対照的でした。彼らとの会話が精神的な拠り所になり、統括総料理長と共に「竹あかり」や「国産メンマ」づくりなど、自家製、手作りにこだわる取り組みを始めるきっかけになりました。これもやはり、「人」との出会いだと思います。
地域と共に未来をつくる 東武ホテルが描く成長戦略

ーー東武ホテルマネジメントの、5年後、10年後の理想の姿をお聞かせください。
三輪裕章:
地域に必要とされ、社員が「東武ホテルならではだ」と誇れるセールスポイントを持つ会社になってほしいです。ホテルは運営を請け負う立場ですが、蓄積したノウハウを元に、出店の提案などができる主体性を持ったオペレーターにならなければいけません。将来的には東武グループ外からでもオペレーションを託したいと言ってもらえる会社になれと、社内では話しています。
ーー理想の姿を実現するため、現在どのようなことに注力されていますか。
三輪裕章:
誰もが「一緒に働きたい」と思ってくれる会社にすることです。業務改善プロジェクトを立ち上げ、DX(デジタルトランスフォーメーション)や効率化を進めています。宇都宮では、東武グループが進める生体認証システムの導入に手を挙げ、先進的な取り組みを地域の活性化にもつなげていきたいと考えています。また、人事制度の改善や職層別の分科会などを通じて、風通しの良い組織をつくっています。特に調理の実務教育を重視し、技術教育によって「東武の味」を守り伝え、私たちのホテルならではの売りとして目指すメゾン(手作り)の基盤を確固たるものとしていきたいです。
編集後記
労働組合とのタフな交渉、前例のない事業の実現、そして赤字事業の再建。三輪氏のキャリアは、常に困難な状況下で「人」と向き合い、対話と信頼によって道を切り拓いてきた歴史そのものである。その信念は、畑違いのホテル経営においても、調理人との出会いを改革の原動力に変えた。地域に根ざし、社員が誇れるホテルへ。その着実な一歩は、多くのビジネスパーソンに、人を信じ、縁を紡ぐことの重要性を教えてくれるだろう。同社の挑戦から目が離せない。

三輪裕章/1958年11月23日 東京都生まれ、日本大学卒。1981年4月に東武鉄道株式会社へ入社。同社取締役人事部長、常務取締役 生活サービス創造本部長、取締役専務執行役員等を歴任。2023年6月より株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長に就任、現在に至る。














