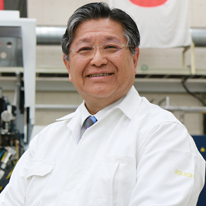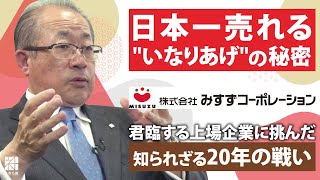インタビュー内容
―「たれ」事業への転換期と『椒房庵』誕生の裏側―
【ナレーター】
当初の予測通り、醤油の市場が伸び悩み、このままでは事業の成長は難しいと次の道の模索を始めた河邉。そこで着目したのは、スーパーマーケットの台頭により生まれた「惣菜」だった。
【河邉】
餃子などは、昔は家でつくるものでした。それがスーパーの惣菜コーナーで売られるようになったのです。そうするとそこに餃子のたれがつきますよね。ここに着目したのです。「この餃子のたれをつくろう」ということで、つくって売るようになったわけです。
納豆も当然スーパーで売られます。そしてその中に「たれ」が入る。それからラーメンにもラーメンスープという「たれ」が一緒に添付されます。そういう状況になってきたわけです。ですから、「たれ」という市場が伸びていきました。
そこに後発ではありましたが、少し乗ることによって我々でも成長することができたのです。
【ナレーター】
「たれ」という新たな道を拓き、事業が軌道に乗り始めた久原本家グループ。しかし、ある従業員の一言が、後の自社ブランドを立ち上げるきっかけになったという。
【河邉】
私どもの工場で働く、ある女性の従業員から、今これほど順調にいっているという状況の中で、私に対して「これはいつまでも続くのでしょうか」とズバッと言ってきたわけです。
実は、私はいつまで続くか分からない今の状況がとても怖かったのです。OEMで成長しているというのは、いつそれが切れるかわからない。危ないことをしているという認識が私の中にもありました。しかし、何もしていない自分がいたのです。その時に私は目が覚めました。
「そうだよね。このままじゃいかんよね。やはり自社ブランドをつくろう」と。例えばドレッシングや「たれ」、それは「久原のものがおいしいから買う」という行動になるわけです。ここにもっていかないとやはり怖いと思ったのです。
【ナレーター】
その後、福岡の経営者が集う青年会議所に入会。そこで出会った大手百貨店の経営者に師事し、掴んだチャンスが明太子事業への参入だった。
【河邉】
その当時、明太子のブランドが非常に弱かったというか、博多辛子明太子というくくりの中で売れているという状況がありました。もちろんブランド力があったところもありましたが、ほとんどがそうでした。
そうではなく、私は店の裏側にあっても売れるような明太子、「絶対このブランドでないとだめだ」と言われるような、ブランド力がある明太子をつくったら良いのではないかという想いに至りました。
卵も北海道の卵、そして名前も『椒房庵』という独特の名前にし、パッケージも山笠とかどんたくではなくて、きちんとお土産にしてもおかしくないようなパッケージにしよういうことでスタートしたのが、この『椒房庵』という明太子事業でした。
滋賀県の大津に本社があるお菓子の「叶 匠壽庵」、それから新潟の水産でさけ茶漬けが有名な「加島屋」、この2つが非常に素晴らしいブランドでして、私の中での目標でした。
ですから、そういうブランドがある会社というか、ブランドをつくりたいという想いがものすごくありました。それをこの明太子で実現しようとしたというのが、明太子事業立ち上げの経緯ですね。

 経営者プロフィール
経営者プロフィール

| 氏名 | 河邉 哲司 |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役社長 |
| 生年月日 | 1955年4月17日 |
| 出身地 | 福岡県 |
四代目社主を継いでからは、たれや調味料のOEM事業に着手。1990年には明太子で初の自社ブランド「椒房庵」を立ち上げ、直営店舗・通信販売を通じて全国で認知度向上に努めた。2005年、自然食レストラン『御料理茅乃舎』を開業。その後、化学調味料・保存料無添加のブランド「茅乃舎」を立ち上げ、福岡の百貨店を皮切りに、東京ミッドタウンなどへ直営店を拡大。現在は全国に29店舗を展開している。2019年には北海道アイを設立。今年6月には久原本家グループ北海道工場を竣工し、食を通じた地域貢献に積極的に取り組む。
創業から130年目を迎えた今、社内では「ありがとう」の気持ちを何より大事にする企業文化の醸成に注力している。
(その他)
1994年 福岡青年会議所理事長
2016年 第43回経営者賞受賞
2018年 在福岡ラオス人民共和国名誉領事
会社概要
| 社名 | 株式会社久原本家グループ本社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福岡県糟屋郡久山町大字猪野1442 |
| 設立 | 1893 |
| 業種分類 | 食料品・飲料製造業 |
| 代表者名 |
河邉 哲司
|
| 従業員数 | 1,319名(2024年2月末時点) |
| WEBサイト | https://kubarahonke.com/ |
| 事業概要 | グループ全体の経営管理業務、マーケティング業務、パッケージ・広告等のデザイン業務、商品開発業務、品質保証業務 |