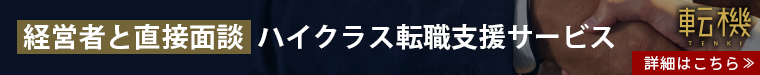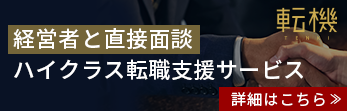インタビュー内容
-事業承継秘話-
【河邉】
絶対に家業は継がないと小さな時から言ってきましたので、本当に仕方なく入ったというのが本心です。最近はよく、「お前は家業を継いだ時に大きな夢があって継いだのだろう」と言われますが、全然。本当に、夢も希望もなく、家業を無理やりに継がされたというのが、最初だったのです。
基本的にその時代は従業員が6名しかいませんでしたから。しかも、私どもの会社は醤油屋で、事務所とガラス1枚を隔てて、われわれの家のダイニングがあったほどです。ですから、基本的に会社も仕事も一体という形で、小さい時からずっと仕事の話を聞きながら生活してきましたので、ギャップとかではなくて、そういう意味では、なんとなく入れたわけです。本当に企業と言える状況じゃなかったので、まさしく家業ですよね。小さな田舎の小さな醤油屋に、大学を卒業して、自然に仕方なしに入れられたというわけです。
従業員が6名しかいない醤油屋で、ましてやその当時、福岡県に醤油屋は150社あった。今でも実は107社もあるんです。ということは、1つの町に1社とか、多いところでは2社あるわけです。そしてそれが、ほとんどが宅配です。1軒1軒家を訪ねて、醤油を補充するわけですよ。配置薬みたいな世界なんですね。それで何とか生計を立てるという形でした。しかも、元々醤油というのは、その当時はほとんどが家庭では煮つけなんですよね。ですから、たくさん使っていたんです。ところがだんだん醤油の需要が減ってくるということで、このビジネスモデルが成り立たなくなってきた。業界として右肩下がりで、全然将来性がないということで、会社を継ぎたくなかったという側面もありました。
とはいえ、後継者は基本的に私と姉しかいませんし、もう姉は嫁いでいました。そこで、父に強く言われて、長男でもあるし、仕方なく家業を継いだという流れなんですよ。もし弟か、ほかの誰かがいたら、一番に逃げ出しただろうと思います。とにかく、仕方なく家業を継がされたということです。
結局私が社長になったのは、父が亡くなったあとです。41歳の時でした。実際には、私が家業を継いだ時から、あとはお前に任せたということで、実質的には社長業みたいなことをやっていたのですが、信用がなかったので、社長にしてもらえなかった。たしか34歳の時に、もう代わろうと言ったことがあるのですが、お金のない人間は社長になれないと言われ、その時は社長になりませんでした。
そういう流れがありまして、父が死んでしまって、初めて本当の意味での社長業をしました。最初の仕事で一番印象的だったのが、銀行さんとのやりとりでした。最初はお祝いに来たのかと思ったのですが、実際は実印を押して、保証人にも印鑑を押してもらうという作業でした。それまではどちらかというと、イケイケでやっていましたが、初めて社長業の厳しさといいますか、責任の大きさが分かりました。要するに、下手をしたら全財産がなくなるのですから。 その時、社長にはなれない父が言っていた理由が初めて分かりました。ですから、まず本当に実印を押したということが、忘れもしない、最初の社長業でした。ただ、ほかの作業はもうやっていましたので、別に社長になって特別な何かをしたということはなかったと思います。
小さな会社でしたから、人事改革も何もないですよ。それより、私の右腕として働ける優秀な人間や、左腕になる友人や後輩をいかに連れてくるかということが重要でした。ですから、そういう目星をつけた人を口説いて、引っぱってくることが、実質的には最初の仕事でした。とはいっても、自分でさえ入りたくないと言っていた会社です。それを説得しなければいけないわけです。自分が進んで入りたい会社だったら分かるんですが、自分が入りたくない会社なのに、後輩たちを口説いて、「私と一緒に働いて、明るい将来を」なんていうことは、なかなか言えなかったわけです。そうするうちに、醤油からだんだん脱皮して、タレに入っていきまして、会社もだんだん成長してきた。そうなってから、やっと後輩たちも入社してきて、一緒にやるようになった。こうして、だんだんいい人材が集まるようになり、成長できたということです。ですから、何か特別に改革したという次元の話ではなくて、いかに思いを一つにしてくれるメンバーを誘うかが、私の何よりも大事な仕事でした。
醤油ではどう考えたって飯を食えないわけですから、それはもう学生時代からよく分かっていました。家庭の料理も間違いなく洋風化するわけですから。そうすると、醤油の需要はどんどん減っていく。これはもう明白でした。そこで、醤油を原料にタレをつくったらいいんじゃないか考えるようになりました。たまたま、私がまだ学生だった頃、タレや醤油を入れる小袋の充填機を導入したんです。その機械を私が、1、2カ月に1回ぐらいほとんど営業力がなかったので、売ることができなかったんですが、機械は遊んだままでした。そこで、この充填機を活用するためにも、なんとかタレをつくりたいということから、まず餃子のタレを業務用で売りだして、そこからタレ業界に参入し、おかげさまで醤油専業を脱皮することができました。当時はスーパーマーケットが普及し始めていました。それまでは、例えば餃子も家でつくるものだったんですよ。皮ぐらいは売っていましたが、中のミンチは家でやって、玉ねぎを入れて、自分でつくっていたんですね。当然、タレの酢醤油も自家製だったわけです。ところが、スーパーで餃子を売るようになると、そのパックに餃子のタレが入る。納豆にもタレが入る。ラーメンだったらラーメンスープが入る。そうやって、タレの需要が一気に伸びたのです。ということで、われわれはそこに参入して、後発だったんですが、だからこそ市場の発展に合わせて変化に対応し、チャレンジできたということなんですね。
-企業理念-
【河邉】
私どもが最も大事にしている言葉に「モノ言わぬモノに、モノ言わすモノづくり」というものがあります。例えば明太子。決しておしゃべりしませんよね。でも、食べておいしいと思ったら、それを他人に伝えたくなるじゃないですか。「あんた知ってる?」と。「あんた『椒房庵』の明太子って知ってる?」みたいに。やっぱり、宣伝に頼って売り上げを伸ばそうとするのではなく、本当においしいもの、手間隙かけたおいしいものをつくる。そうやってつくったものに、モノを言わせようと。そういう会社でありたいということを、一番の理念として挙げております。
また、われわれにとって一番大事な物差しというのは、永続することです。永続が何よりも優先されます。決してお金ではない。では、お金は要らないのかというと、そんなことはありません。当然、永続のためにお金は必要ですが、何かあった時、一番重要ではないということです。
例えば、いろいろな偽装事件。偽装が発覚すると、賞味期限が切れてしまってはもったいないから変えたとか、これを捨てたら会社に莫大な損害を与えるから改ざんしたとか言い訳をする。でも、そこに永続という物差しを当てはめれば、どうすればいいか、簡単に答えが出るわけです。でも、残念ながら、ほとんどの会社では、永続ではなくお金がスタート。だから「逆送り」なんですね。私はそれだけは絶対まかりならない、とにかく常に永続なんだ、迷うことがあったら常に永続ということを物差しに判断しなさいということを基本にしています。「モノ言わぬモノに、モノ言わすモノづくり」ということに粛々と挑戦しながら、より良いものをつくっていく。それがひいては永続につながるという信念で、頑張っております。
永続が何よりも大事な物差しだと言いましたが、具体的に従業員がどういうことをしていくかが重要です。一つは、いかに手間隙をかけた本物をつくるかということ。もう一つは地方旗です。例えば、博多という旗を立てると、大手さんがなかなかこれませんので、この二つがものづくりとしてはあるんです。一方、接客職や本社の管理本部などは「ものづくりに携われないが、どうすればいいのか」という話になるので、こちらには「いかにしてお客さんに喜んでいただくか、いかにお客さんに感動を与えるかを考えよう」と話しています。手間隙をかけた商品をつくる、その結果おいしかったと思って買いに来ていただける。そうやって永続に向かうのです。接客チームも同様で、レストランなどでは「あなたに会いたいから食べに来た」というケースも多いですよね。物販も同じです。「あなたに会いたいから買いに来た」だったら、まさしく永続の理念にかなう。ということで、ものづくりと接客。この両輪でわれわれはいかに永続するかということを考え、日々努力しているわけです。
私どもは永続が一番大事だという信念の下、元々の『久原醤油』からタレの『くばら』ブランドまで。そして25年前にスタートした博多で最後発の明太子『椒房庵』の二つを展開しています。ありがたいことに、両方とも成長しているわけですが、でもやはり二つでいいのかという思いはあります。われわれの121年の歴史を見た時に、戦前は今でいう中国や韓国で醤油の需要が拡大しました。ところが、終戦で激しい反動があった。たかだか120年の歴史の中で、そういうことがありました。こういうことは二度とあってはならない。そこで、ではわれわれはこれからどうするかと考えた時、『くばら』『椒房庵』だけでは、やはりいろいろ問題点がある。それで3本目の、毛利元就の「三本の矢」ですね。これを考えた時に、やはりもう一つないといけないということで、『茅乃屋』という無添加のブランドをつくりました。こうして、現在は『くばら』『椒房庵』『茅乃屋』の3本柱ができましたが、現代は移り変わりがすごく速いわけです。しかも、この2本目の柱である明太子は、北海道産の卵しか使わない上級品なのですが、自然のものなので、いつどうなるか、いつ枯渇するか分からない。そこで、明太子は特別な高級品と位置づけて、柱はまだ2本しかないと思っています。そして、新しい3本目の柱を作らなければいけないと思いながら、今は事業を組み立てています。そうやって3本の矢をきちんとつくることで、永続を実現させようというのがわれわれの考えです。
われわれ、元々は醤油屋です。そして、現在は『茅乃屋』ブランドの中で、だしが注目を浴びています。この醤油とだしというのは、まさしく日本食のど真ん中じゃないですか、二つとも。このど真ん中を持っている会社としては、日本食が世界に広がっていく今の状況を考えた時、当然海外にも進出しないといけないと思っています。そこで、ここ数年はニューヨークやハワイなどに、少しずつ流通させているのですが、まだ現実的に直営店はありません。卸として流すのであれば簡単なのですが、われわれは直営店を出したいんです。ただ、単純に直営店に日本の調味料を置いて売れるかと言われると売れるわけがないんですよ。なので、日本の料理や、その周りのしつらえなどの日本の食文化、そういったことも一緒に提案をしていって。ただ調味料を広めるのではなく、日本の食文化自体を世界に広めていきたいと考えています。
-商品について-
【河邉】
現在ある3ブランドそれぞれに、例えば『くばら』だったら野菜に力を入れています。『やきとり屋さんのキャベツのうまたれ』からスタートしましたので、特に青果コーナーで販売する「野菜をおいしく食べる」ドレッシングやたれなどです。『椒房庵』はそういうことでは新製品は多くありませんが、もう一つは『茅乃屋』ですね。『茅乃屋』では『茅乃屋だし』を中心にいろいろな無添加の調味群を、数多くのアイテムをそろえて展開しています。ただ、今後もいろいろな面白い、こういうものがあったらいいと思える商品を続々と開発していますので、それらをどんどん投入しようと思っていますし、通信販売もあります。通信販売については、通信販売ならではの商品も、今後開発していきたいと思っています。
我々は大手と違いますから、例えば『くばら』の商品に『鍋つゆ』というのがあります。これはよせ鍋などではなくて、『キャベツのうま鍋』など、野菜コーナーに特化したものです。最初は「なんかなあ」と言われていましたが、こういうものに特化しながら、他社と違うネーミングで、なおかつ値段も他社よりちょっと高め、その代わりおいしいものというコンセプトです。『茅乃屋』も同様で、やはりちょっと高い価格設定にしています。われわれは手間隙をかけておいしいものをつくろうとしているわけですから、たくさん出回っている大衆的な商品より当然高くなる。その代わり絶対おいしいよというようなことを目指しながら、今商品開発しているところです。
大手のようなコスト重視の大量生産という方法では、われわれは生き残れません。ですから、徹底的に手間隙をかけて、大手だったら絶対こんな面倒くさいことはしないということをやりながら、品質勝負で売っていくという戦略ですね。地方の小企業が生き残るには、もうこの方法しかないと思っています。逆に、大手はそういうことをしたくないはずですから、そこに徹底的に特化するのです。当然、現場は嫌がります。やはり大変ですから。しかし、そのひと手間、ふた手間をかけることによって、絶対的に差別化された商品が生まれると確信しています。
これも先ほど言いましたように、手間隙かかるぶんだけ上質になるということで、やっぱりちょっと高めになる。これもある程度は仕方ないので、それでも上質なものを求めていきます。大手企業の商品と比べて少し金額が上の商品という形が『くばら』の大きな戦略と思っています。
例えばこの『やきとり屋さんのキャベツのうまだれ』です。博多の焼き鳥屋さんに行くと、まずざく切りのキャベツが出てきて、それを食べながら、そしてビールを飲みながら焼き鳥を待つという食文化があるのですが、これを商品化して売りました。当初、私は売れると思っていなかったのですが、発売したらびっくりするぐらいヒットしたのです。なぜこれだけ売れたのかを考えたのですが、結局潜在的なニーズがあったのですね。「焼き鳥屋さんのあのタレ、おいしいよね。でもスーパーには売っていないし、家でつくろうとしてもできないし」というニーズです。そこにこの商品がポーンと入った。そしてボーンと爆発的に売れた。
なおかつ、その当時、これは地調味料の代表的な存在として、マスコミにも取り上げられました。「ありそうでなかったもの」そういう意味で、ヒット商品というものは、実際はものすごく難しいものではなくて、実はこのような商品は全国に転がっているのかもしれません。 ですから、われわれもそれを見つけて、商品化しようとしていますが、二匹目のドジョウはなかなか難しいです。逆に、この商品はそれだけヒットしたということではないかと思います。
年商6300万円、月の売り上げ500万円の醤油屋だった時に、私は自分で醤油をつくってそれを軽トラックに載せ、前掛けをして運転しながら一軒一軒配達していました。それも決まったお宅に持っていくわけです。知り合いや近所の奥様も、なかなか買ってくれない。マイ醤油があるんですね。ところが、ある人に声をかけたところ、「あんたが家を継いだのなら、1本取ってやろう」と言っていただいたことがあります。この感激、うれしさというのが、とにかく忘れられません。それが骨身にしみているのでしょう。今では毎日、大きなトラックでタレを食品工場に納品して、何千万円という売り上げがあります。でも売り上げだけじゃないと思っているんです。100円の商品でも、何千万円の商品でも、買っていただいたお客さまは一緒なのです。本当にうれしいこと、ありがたいことで、それが私のバネになっているのです。
今はこの心をどうやって従業員に伝えるかということを、日々考えて実践しているところです。
-人材について-
【河邉】
昔、本当に醤油だけだった頃ですが、募集しても誰も来てくれない時代がありました。でも、ようやく一人来てくれたら、たくさん応募があったふりをして、その中でもあなたが一番いいと言って口説くわけですね。そして、「来週月曜日から来なさい」「分かりました」という会話があって、うれしいから従業員に「今度の月曜日から新人が来るよ」と言って、月曜日になると、その人は来ないんですよ。何回もこれを繰り返しました。
確かに、3Kとは言わないまでも、相手が醤油ですから、大変な職場でしたよ。ですから、何かの縁で来た人でも、当時、新たに入社した方は だれも『久原』が成長すると思っていなかったと思うんです。だから、そういう人たちに良かったと言わせようと思って、それが私の原動力になっているのです。その過程で、例えばほとんどの従業員が海外旅行に行ったことがなかったので、「よし、パスポートをつくって、毎年海外に行くぞ」とか、そういうことをみんなで楽しく、わいわい言いながらやってきた。従業員に感謝。そしてお客さまに感謝。これが社長としての私の原動力です。
ありがたいことに、当社は成長を続けておりますので、とてもではありませんが、既存の従業員だけでは手が足りません。従って、社長の一番の仕事は、いい人材を確保することだと思っています。会社の方向を示すのと、いい人材を確保すること。この2つが社長業で最も重要な仕事です。ですから、人材確保は必死に取り組んでいます。新卒の面接も担当しますし、2014年4月から海外事業推進部をつくるのですが、そのための人材も確保しなければなりません。人が増えると、それを管理するメンバーも要りますよね。このように、いろいろなところで新しい人材が必要になってきます。本当に『久原』に入りたいとか、この会社で夢をみたいという人には、是非一緒にやりませんかと声を掛けています。『久原』に興味を持った方には、是非訪ねていただければと思います。
-経営哲学-
【河邉】
私は北海道の『六花亭』の小田社長(役職は2014年3月当時)を大変尊敬しております。ですから、『久原』の目標は『六花亭』になります。小田社長とは、社長業としての目標も話をしましたが、やはり北海道限定で、ブランド価値を高められて、なおかつ文化的な事業をたくさんされている。われわれも同様で、商品を売ればそれでいいという考えではなくて、いろいろな意味での文化活動をしたいと思います。われわれは食品産業ですから、先ほども日本の食文化という話をしましたが、そういう活動も是非やっていきたいと考えています。そのためには、ブランド価値をいかに高めるかですね。やはり、目指せ『六花亭』ではないですが、やはりあのようにブランドイメージが高い企業を目指していきたいと思います。
小田社長の話に戻りますと、いただいたお手紙の中に「わが家」という言葉がありまして、何なのかなと思ったら、会社のことなのですね。また、小田社長は全従業員1200人の顔と名前が分かるとおっしゃった。たしかに、分かるのなら「わが家」と言っていいですよね。私も家族と言っていましたが、残念ながら全員の名前を言えないという状況があって、これはいかんということで、今必死で名前を覚えています。われわれも「わが家」と言いたいので。いいところは真似したいですから。そういう意味で、目標にしながら、北海道の『六花亭』に対する九州の『久原』という形にできれば素敵だなと思っています。
人生の哲学としては、自分の目標を明確に持って、それにチャレンジするということ。今の若者には夢がないという話をよく聞きますが、それでは何のために生きているのか分かりません。人生には必ず役割があると思います。役割をきちんと自覚して、自分を知る。私には家業があったので、嫌々でも役割を担わなきゃいけなかったのが、逆にラッキーだったと思います。いずれにしても、自分の夢と役割をしっかり見つけて、そしてチャレンジすること。このチャレンジすることに、人としての素晴らしさがあるのだと思います。ですから、とにかく目標を持ってチャレンジする。これが豊かな人生を過ごす上では最も重要だと思っています。
-メッセージ-
【河邉】
今の学生さんというのは、適当に「近くにコンビニがあったから」とか「近くにファーストフードの店があったから就職しました」みたいな話をよくしています。だから、就職した後、やっぱり自分の目標が分かっていない。本当にこの業種で仕事をしたかったから、就職したわけではないというケースがすごく多い。バイトでもそうですが、自分がどういうものに興味があるから、将来の仕事の訓練としてこのバイトを選んだ、というようにしなければ。興味があるものの中から、自分が目標を決めるということをしないと、すごくもったいない。就活が始まる寸前になって、初めて自分の目標は何なのかと考えるというパターンですね。そうではなく、大学の4年間というのは、自分の将来の夢や目標を見つける期間だと思うんです。そのためにも、有意義なバイトをすべきだと思っています。自分の目標に近い業種でのバイトです。もう一つは、何よりも友達です。一人でも多くの友達をつくること、これが学生時代で一番大事なことではないかなと思います。ぜひ一人でも多くの友達をつくっていただきたいですね。
やはり、人というのは必ず役割を持って生まれてくると、私は信じているんです。その役割を自分で自覚できるかどうか、そういうことだと思います。ですから、会社に入ったら、その中で一刻も早くその自分の役割を見つけてほしいと思っています。また、1年足らずで辞めたりする人もいますが、やっぱり3年間はその会社で頑張る。それで、どうしてもダメだったら仕方ないと思いますが、1年間くらいで辞める人は、次もすぐまた辞めるケースがすごく多いですからね。だから、3年間我慢してみて、ダメだったら次のステップへ行く。そのくらい我慢して、自分の人生を見つめてみるということも、非常に大事だと思います。とにかく、その会社での役割は、必ずあると思いますから、まずそれを一刻も早く見つけてほしいですね。
―「たれ」事業への転換期と『椒房庵』誕生の裏側―
【ナレーター】
当初の予測通り、醤油の市場が伸び悩み、このままでは事業の成長は難しいと次の道の模索を始めた河邉。そこで着目したのは、スーパーマーケットの台頭により生まれた「惣菜」だった。
【河邉】
餃子などは、昔は家でつくるものでした。それがスーパーの惣菜コーナーで売られるようになったのです。そうするとそこに餃子のたれがつきますよね。ここに着目したのです。「この餃子のたれをつくろう」ということで、つくって売るようになったわけです。
納豆も当然スーパーで売られます。そしてその中に「たれ」が入る。それからラーメンにもラーメンスープという「たれ」が一緒に添付されます。そういう状況になってきたわけです。ですから、「たれ」という市場が伸びていきました。
そこに後発ではありましたが、少し乗ることによって我々でも成長することができたのです。
【ナレーター】
「たれ」という新たな道を拓き、事業が軌道に乗り始めた久原本家グループ。しかし、ある従業員の一言が、後の自社ブランドを立ち上げるきっかけになったという。
【河邉】
私どもの工場で働く、ある女性の従業員から、今これほど順調にいっているという状況の中で、私に対して「これはいつまでも続くのでしょうか」とズバッと言ってきたわけです。
実は、私はいつまで続くか分からない今の状況がとても怖かったのです。OEMで成長しているというのは、いつそれが切れるかわからない。危ないことをしているという認識が私の中にもありました。しかし、何もしていない自分がいたのです。その時に私は目が覚めました。
「そうだよね。このままじゃいかんよね。やはり自社ブランドをつくろう」と。例えばドレッシングや「たれ」、それは「久原のものがおいしいから買う」という行動になるわけです。ここにもっていかないとやはり怖いと思ったのです。
【ナレーター】
その後、福岡の経営者が集う青年会議所に入会。そこで出会った大手百貨店の経営者に師事し、掴んだチャンスが明太子事業への参入だった。
【河邉】
その当時、明太子のブランドが非常に弱かったというか、博多辛子明太子というくくりの中で売れているという状況がありました。もちろんブランド力があったところもありましたが、ほとんどがそうでした。
そうではなく、私は店の裏側にあっても売れるような明太子、「絶対このブランドでないとだめだ」と言われるような、ブランド力がある明太子をつくったら良いのではないかという想いに至りました。
卵も北海道の卵、そして名前も『椒房庵』という独特の名前にし、パッケージも山笠とかどんたくではなくて、きちんとお土産にしてもおかしくないようなパッケージにしよういうことでスタートしたのが、この『椒房庵』という明太子事業でした。
滋賀県の大津に本社があるお菓子の「叶 匠壽庵」、それから新潟の水産でさけ茶漬けが有名な「加島屋」、この2つが非常に素晴らしいブランドでして、私の中での目標でした。
ですから、そういうブランドがある会社というか、ブランドをつくりたいという想いがものすごくありました。それをこの明太子で実現しようとしたというのが、明太子事業立ち上げの経緯ですね。
―『キャベツのうまたれ』開発秘話―
【ナレーター】
自社ブランドの明太子『椒房庵』を足掛かりに、中心事業であった「たれ」でも自社ブランドの製造・開発に着手。
そこで生まれたのが後の久原本家グループを代表する商品となった『キャベツのうまたれ』だ。この商品の誕生の裏側に迫った。
【河邉】
私の大学時代の友人がスーパーを経営していまして、最近よく冷凍の焼き鳥がよく売れるという話を聞きました。
福岡の家庭では、やはり博多の焼き鳥屋さんと同じように、焼き鳥を食べる時はぽん酢だれがかかっているざく切りのキャベツを食べます。
ですので、「あの『たれ』がないとだめだろう。だから河邉、お前が『たれ』をつくれ」と。「そう言うならつくるか」ということでつくった焼き鳥屋さんの『キャベツのうまたれ』がヒットしたのです。
その当時は、地方の調味料というものが脚光を浴びてきた時期でした。マスコミのみなさんもそういうものの特集をたくさんしていました。その少し前ですから、先駆けだと思います。
ただ、私は当時なぜ売れたのかよくわからなかったのです。
しかし、後々振り返ってみて冷静に考えると、「焼き鳥屋さんに行ったときに食べるあのぽん酢だれ、おいしいけれども、売ってはいない。でも自分でつくろうとしてもできない」という、潜在的な欲求があった時にその商品が出てきて、それで瞬く間に火がついたということではないか。そういう商品だったのではないかと思いました。
【ナレーター】
『キャベツのうまたれ』は、西日本では爆発的にヒットしたものの、東日本では商品そのものに馴染みがないこともあり、売り込みにいっても敬遠されることが多かったという。
しかし、この経験から得た学びが、後の久原本家グループの事業展開に大きな影響を与えることとなる。
【河邉】
要するに入り口はすごく狭く難しい。だけどそれゆえに、一回入ってもらうとなかなか抜け出しにくい。私はこれが非常に良かったのだと思います。ある種の「地方の旗」を立てる、ということです。
「博多の食文化」、これを売るということは他社ではなかなか真似できませんよね。この時、そういうことを学習できたのがこの『キャベツのうまたれ』でした。
ですからそれ以来、我々は野菜、要するに青果コーナーに着目するようになりました。その当時はまだ青果コーナーにそういった「たれ」が置いてなかったのです。それを我々はある種、先進的に取り組みました。
たまたま『キャベツのうまたれ』だったのでそういうところに置いていただきましたが、当時は大手企業さんが全然していなかったことです。そういう新しいことをどんどんやっていきました。
ある種の関連販売ですね。キャベツを買ったときに一緒に買おうという話がありますけど、そういうことで手に取っていただく。地方の弱小企業でも売れるチャンスがあるという場所が「青果コーナー」だったのです。
―『茅乃舎』立ち上げの裏にあった危機感―
【ナレーター】
その後、当時売り上げが伸びていた無添加明太子から着想を得て、無添加をキーワードにした3つ目の自社ブランド『茅乃舎』を立ち上げた河邉。立ち上げの背景について、河邉は次のように語る。
【河邉】
毛利元就ではないですが、やはり三本の矢が絶対に必要だと思いました。それで三本目の矢をつくろうということで、「何がいいかな」とアンテナを張り巡らせたときに、さきほどの無添加明太子というのに出合って、「これかな」と思ったわけです。
常に心配性ですから、「これじゃいかん」と思うわけですね。ですから1日たりとも「これでいい」とか、「もう満足」という話にはなりません。特にこういう時代は変化が速いので、まさしく変化に対応していかないと残れなくなってくるわけですね。
ですから今言っているのは、三本の矢ではまずいと。今から四本でも五本でも持っておかないと、時代のスピードが速すぎるからもたないだろうという話をしています。
我々はある種、ブランドビジネスをやるという話をしていますが、今までのノウハウはありますので、それをもとに四本目や五本目を今からつくりながら進化していくということが、私は非常に大事だと思っています。
―海外展開を加速させる一手―
【ナレーター】
数多くの自社ブランドを確立させることに成功した久原本家グループ。今後はアメリカやASEAN諸国を筆頭に海外進出を加速させていく。
【河邉】
一つはロサンゼルスに基地(拠点)を設けまして、そこから今、通信販売を全米で行なっています。それと東海岸に一人駐在していますが、将来は東海岸に何かお店をつくりたいということで、それに取り組んでいるのがアメリカ事業になります。
もうひとつはベトナムです。レストラン『KUBARA』というのをベトナムのホーチミンに出して、今秋(2019年秋)に2号店をつくります。そんな形で我々はレストランをやりながら、将来はASEANに向けての重要拠点にしていきたいと思い、色々なことを考えています。
そして香港にひとつまた新しい展開をしようと思って、先般行ってきました。香港にも一つ基地(拠点)をつくりたいなと思います。やはり「日本食=ヘルシー」というイメージがありまして、非常に和食というのが広がりつつありますね。
その中において、我々の出汁や醤油というものも、受け入れられる素地が出てきています。それが我々の強みですし、アメリカでもASEANでもオファーが非常に多いというのが現実です。
―社長業=従業員が活躍する舞台をつくること―
【ナレーター】
採用面接ではその人の目標が何かを必ず聞くという河邉。その理由について次のように語る。
【河邉】
人生は色々なことがあります。その時にぶれてしまいます。そして離脱してしまうなど、色々なことがあります。
しかし、志を高く持っていて、目標がきちんと定まっていると、少々のことがあってもぶれません。ですので、目標がある人は芯が強いのだと思います。
【ナレーター】
入社した従業員には現場研修や異動の推進など、久原本家グループでの自身の役割を見極めるための環境を整備しているという。
「自分の得意なものさしを見つけてほしい」と語る、河邉が抱く従業員への想いに迫った。
【河邉】
私は常に社長として、色々な舞台をつくってあげます。明太子の事業や『茅乃舎』もつくりました。様々なことしてきました。その時に「誰がやりたいか」という話をします。
「自分がやりたい」と言った若者に、今までずっと任せてきました。やりたい人にやってほしい、海外に出てほしいという想いがあるのです。
ですから、これからたくさん海外に出ると思います。海外もそうですし、『茅乃舎』ブランドもそうですけど、例えば『茅乃舎』から派生した新しいビジネスモデルはたくさん考えられます。
今まで非常に苦労してつくり上げた一つのブランドと信用、これを利用してみんなでもっと成長しようという想いです。アイデアと実行力さえあれば、日本では普通なかなかあり得ないような、すごく面白い仕事ができるのが我々ではないかなと思います。
―成長への考え方と今後の展望―
【ナレーター】
企業の成長にあたって、売り上げを伸ばすことが必ずしも正しいことではないと語る河邉。その真意とは。
【河邉】
私は、基本的に売り上げはお客様の喜びの数だと思っています。ですから、売り上げが上がったということは、お客さんが喜んでいただいたということです。
しかし、我々は色々な資源をもとに商売をしているので、どんどん大きくすると、やはり良いものを使えなくなってしまいます。
我々は一つひとつのブランドの位置づけと考え方があって、そのための戦略があります。ですから、決して売り上げを上げるのが良いとは思っていません。いかに永続するかということを考えながら、そのためにはやはりブランドが大事だということを言います。
そして、次なるブランドをつくりながら、そこで売り上げを上げることによって、企業全体を上げていってみんなが豊かになるというか、そういう必要があるのではないかなと思っています。
【ナレーター】
日本の食文化をさらに世界に広げるべく、地方発老舗メーカーの挑戦は続く。
【河邉】
「こんな地方の小さな会社ですら、やれるんだ」という、ある種そういうビジネスモデルです。要するに、地方の小企業に元気を与えられる、私はそんなビジネスモデルがつくれれば良いのではないかと思っています。
あまり勉強をしてこなかった私にだって、想いを、志を高く持てばなんとなる。素晴らしい学生は世の中にたくさんいらっしゃる。あなただったらもっとできます。
志さえ持てばできるということを、私を見ながら「あいつができたのなら、俺もできる」と思っていただきたい。本当にそう思いますね。
【ナレーター】
1893年創業の老舗総合食品メーカー「久原本家グループ」。
北海道産の卵にこだわった『あごだしめんたいこ』などを取り扱う『椒房庵』や化学調味料・保存料無添加の出汁や調味料を扱う『茅乃舎』など、厳選した素材と、手間暇を惜しまない味づくりを大切にしたブランドを展開し、さまざまなジャンルの商品を開発。
2019年には、新たな柱として北海道の食品や食文化を全国に届けるべく『北海道アイ』を立ち上げるなど、日本の食文化に根ざしたものづくりを行っている。
「つくること、食べることが多くの人をしあわせにするように」。その思いのもと、数々のヒット商品を生み出し続けてきた、4代目経営者が見据える未来とは。
【ナレーター】
かねてから「永続する企業づくり」を掲げ、邁進している久原本家グループ。その実現に向けて、特に注力している2つのこととは。
【河邉】
まず“味づくり”ですよね。やはりこれは長い年月をかけましてね。
「そうすると価格が…」というようなことをすぐに言ってしまって、「仕方ないか」と味を妥協するということってあるんですけれども、当社はやっぱりおいしいものをつくりたいということを考えたとき、どうしても価格が高くなるんですよね。手間暇も掛かります。
それを認めてもらうにはある種、ブランドがないと売れないということにもなるわけですね。
開発メンバーの中には、他社から入ったメンバーもいますが、彼らが一様に驚くのは、これまで勤めていた会社では「価格を安くしろ、安くしろ」と言われてつくってきたけれど、当社では「もっとおいしくしろ、おいしくしろ」と言われることだと。
また、「あなたのところの商品は間違いないもんね」とお客様からはよく言われます。そのように言っていただけることが、一番私にとって冥利に尽きることなんですね。
そしてもう一つは“感謝”です。
当社の従業員は分かってくれていると思いますが、「これは当たり前じゃないよね、当たり前じゃないよね」ということをみんなで繰り返し言い合っています。ですから、「あんたのお店の接客、気持ちいいよね」と言っていただけるわけです。
「あなたに会いたいから会いに来た」というのは確実にあるんですよ。味づくりと感謝、この2つがしっかりしていれば、私が最も大事としている永続に間違いなく向かっていけると思います。
【ナレーター】
河邉の原点は入社時に感じていた想いにある。しょうゆ醸造業を営んでいた父の会社に入社し、しょうゆの販売に従事するも、当時は洋食化が加速しており、売上が低迷していた。
「とにかく売上を上げたい」という一心で、さまざまな取り組みを行う中で辿り着いたのが「たれ」事業への進出だった。
【河邉】
その当時、スーパーがどんどん出店し始めた時代です。
たとえば、ギョーザだったらこれまで家でつくって食べるのが当たり前だったのが、スーパーにギョーザが置かれ出した。
ギョーザは、スーパーに置かれるようになったときに、タレが付き出した。さらに納豆も置かれるようになりました。すると、納豆のタレが付きだした。そのとき、(この市場は)成長しているということが分かったんですね。
当社にギョーザのたれや納豆のたれなどを小袋に充填する機械があったんです。それを使ってたれ事業に入ったらいいのではないかということで。そういうことをスタートしましたね。
【ナレーター】
時流に乗ることができた久原本家グループはその後、順調に業績を上げる。しかし、従業員からのある一言が、浮かれていた自分の目を覚ましてくれたと振り返る。
【河邉】
その従業員が「今どんどん成長して、何か調子よくいっているように見えているけれど、大丈夫なんですか?」ということを私に言ったんですよ。水をぶっかけられた気持ちでした。
でも、実はそれは、私は最も怖かったことでした。分かっていたことなんですよ。
もっとおいしいたれを大手企業が持ってきて、価格を少しでも安くしたら、たとえば納入メーカーは、すごい量を取りますから、大きなメリットがあるわけですね。ですからいつ(シェアを)取られるのかとヒヤヒヤしながら納入していて。
成長すれば成長するほど、怖くなっていった。自分でも分かっていたのに、次の手を打っていなかった。(その従業員の言葉を聞いて)自分は何だったんだろうとすごく反省したんです。
【ナレーター】
どうすれば大手企業に対抗できるのか。考え続けて出た結論は、自社ブランドをつくることだった。しかし既存事業のたれには、すでに大手が参入しておりブランド化は難しい。そこで着目したのは地元福岡の名産品である「辛子明太子」だった。
【河邉】
辛子明太子というのは、いかに売り場の中央に広く置けるかによって売上が違っていたんです。要するに、辛子明太子という括りの中で売れている。ですから、ブランドがあるメーカーが極めて少なかったということが分かったんです。
私は以前から滋賀県に本社を置く老舗製菓メーカーの叶 匠壽庵さん、それから新潟県に本社を置く食品メーカーの加島屋さんという鮭茶漬けのブランドが大好きで、勉強していたんですよね。いつの日かそういうものをしたいなというのが根底にあったんです。
ブランドというものがしっかりある。要するに、売り場の後ろ側にあっても売れるような明太子にしたらいいのではないかという発想に至ったんです。
【ナレーター】
その後、福岡の経営者への師事を経て、1990年に辛子明太子ブランド『椒房庵』が誕生。これを足掛かりに主要事業だった「たれ」でもブランドづくりに着手し、その中で生まれたのが、後のヒット商品となった『キャベツのうまたれ』だ。
【河邉】
これはたまたま私の大学時代の同級生がスーパーを経営していて、焼き鳥がよく売れると言ってきたんです。
「福岡の家庭だったら、焼き鳥を食べるときはキャベツも一緒にして食べないといけない。それには焼き鳥屋にある“酢だれ”が必要だから、お前がつくれ」という話からだったんですよね。
「そんなもの、売れんやろ」って言ったんですけれど、それがもう驚くほど爆発して売れたと。
青果コーナーで売ったものですから、その後、『きゅうりのうまたれ』や『トマトのうまたれ』などの派生商品をつくりながら、徐々に全国に『くばら』ブランドも広げていったというのがスタートです。
『くばら』もOEMのメーカーだったのが自社ブランドの商品がようやくでき始めました。

 経営者プロフィール
経営者プロフィール

| 氏名 | 河邉 哲司 |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役社長 |
| 生年月日 | 1955年4月17日 |
| 出身地 | 福岡県 |
四代目社主を継いでからは、たれや調味料のOEM事業に着手。1990年には明太子で初の自社ブランド「椒房庵」を立ち上げ、直営店舗・通信販売を通じて全国で認知度向上に努めた。2005年、自然食レストラン『御料理茅乃舎』を開業。その後、化学調味料・保存料無添加のブランド「茅乃舎」を立ち上げ、福岡の百貨店を皮切りに、東京ミッドタウンなどへ直営店を拡大。現在は全国に29店舗を展開している。2019年には北海道アイを設立。今年6月には久原本家グループ北海道工場を竣工し、食を通じた地域貢献に積極的に取り組む。
創業から130年目を迎えた今、社内では「ありがとう」の気持ちを何より大事にする企業文化の醸成に注力している。
(その他)
1994年 福岡青年会議所理事長
2016年 第43回経営者賞受賞
2018年 在福岡ラオス人民共和国名誉領事
会社概要
| 社名 | 株式会社久原本家グループ本社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福岡県糟屋郡久山町大字猪野1442 |
| 設立 | 1893 |
| 業種分類 | 食料品・飲料製造業 |
| 代表者名 |
河邉 哲司
|
| 従業員数 | 1,319名(2024年2月末時点) |
| WEBサイト | https://kubarahonke.com/ |
| 事業概要 | グループ全体の経営管理業務、マーケティング業務、パッケージ・広告等のデザイン業務、商品開発業務、品質保証業務 |