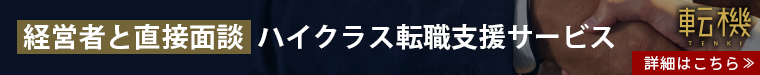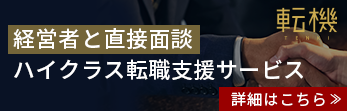【ナレーター】
純米吟醸酒国内トップシェアを誇る「旭酒造株式会社」。
品質にこだわり抜いた同社の主力商品『獺祭』は、1989年の誕生以来、売上規模で100倍以上の成長を遂げた。海外においても、現在30ヶ国以上に輸出され、国内外で根強い人気を誇っている。
また、2023年春より、アメリカ・ニューヨークに立ち上げた同社初となる海外製造拠点の稼働が開始。日本酒の新たな価値創造に向け、挑戦を続けている。
「日本酒を通じて日本の文化・風土を世界に伝える」。その実現に向けた4代目蔵元の想いに迫る。
【ナレーター】
旭酒造の強みは、おいしさを追求できる仕組みにあると、桜井は語る。
【桜井】
基本的に、おいしいという部分が一番大事で、そこで私たちは勝負していくしかないと思っています。
私たちの強みは味を追求できる製造スタイルであり、そこに人手がかけられる体制なんです。私たちは、ほかの酒蔵さんより量を多くつくっていますが、オートメーションではなく人の手をかけてつくっているんです。
さらにそれをブラッシュアップさせて、進化させています。ですから、伝統産業ではあるんですが、そこにPDCAをどんどん高速で回していくというスタイルが宿っている、新たなタイプの会社なんです。
そこが、当社の一番の強みだと思っています。
【ナレーター】
桜井の原点は、就職した後『獺祭』を初めて口にしたときの実体験にある。
当時は家業を継ぐつもりはなく、東京に本社を置くメーカーに就職した桜井。社会人になってから、『獺祭』のおいしさに感動した経験が、旭酒造へ戻ることを意識したきっかけになった。
【桜井】
当社のお酒が、非常においしいこと。それが、お客さんに対する意義になる、価値になると感じました。
当時は、まだまだ小さい規模の酒蔵でしたし、それを継ぐことに意味があるかどうかは大きいんですね。
それでいうと、酒がおいしいという点では意味があり、評価されて伸びてもいる。この部分は戻るに足る、会社に対して自分を賭けるに足ると考えて、戻ってきたというのはあります。
【ナレーター】
そして2006年に旭酒造に入社。製造現場で酒づくりの基礎を学んだ後、順調にキャリアを重ねた。2013年には取締役副社長に就任し、アメリカ、ニューヨークへの販路開拓を担当。
しかし、当初は海外展開に反対だったという。
【桜井】
旅行で海外に行っているときは、日本酒を飲む外国人を見て、日本酒がわかっているように思えなかったんです。だから本当に売れるのか、伸ばす必要があるのかと考えました。
しかしながら、実際に当社が海外に進出し始めて意識が変わってきたんです。
アメリカの人たちも、おいしいものはおいしいと言うし、おいしくないものはおいしくないと言う。国境など、そういった壁はあまりないということが分かってきたんです。
特にニューヨークのような都市部は、いろいろな国の文化が混じり合ってできているので、余計にローカルなものにしがみつく部分はなく、良いものは受け入れる風土でした。
そういった背景から、海外に軸足を置いて、大きく踏み出すようになったんです。
【ナレーター】
その後、2016年に代表取締役社長へ就任。当時の心境について、桜井は次のように振り返る。
【桜井】
当社を継いで思ったのは、獺祭は良くも悪くも注目度が高く、お客様からの認知度も高いということでした。
経営者として一番前で見ていますので、意見はストレートに受けます。お客様からの期待や、獺祭に対しての思いをとても強く感じますし、期待の大きさに圧倒されることがあります。
就任当初は、それまでの延長線でやっていく部分が大きいと思っていました。以前より今のほうが、変わっていくことが大事、変えていく必要があると思っています。
【ナレーター】
杜氏制度の廃止や数値を用いた伝統技術の見える化など、これまでの常識にとらわれない取り組みを積極的に行っているのが、旭酒造の特徴のひとつだ。
これらに取り組み始めた経緯について、桜井は次のように語る。
【桜井】
杜氏を廃止したのは、当社の業績が芳しくないときに、杜氏が蔵人を連れて他所に行ってしまったことがきっかけです。
しかしその結果、社員で酒をつくるようになったからこそ見えてきた部分が大いにあった。
技術的な部分がブラックボックス化していくのは怖いことですし、その恐怖がなくなったことで、新たなこともできるようになったんですね。
伝統というのは、どうしても昨日と同じことの繰り返しになるところがあるので、そこを超えて、昨日より良い明日をつくっていけるのは、当社の強みだと思います。
ですから、杜氏がいなくなって今のような製造スタイルになって、結果的にはよかったと思っています。
製造スタイルを変えていく中で、データを駆使し、自分たちの動きを見える化するというところに向かっていきました。その上で私たちが今やってることはしっかり進めていきました。
今は、データを使った上で、さらに職人が職人として良いものをつくっていくためには何をしたらいいのかというところへ、向かっています。


 経営者プロフィール
経営者プロフィール