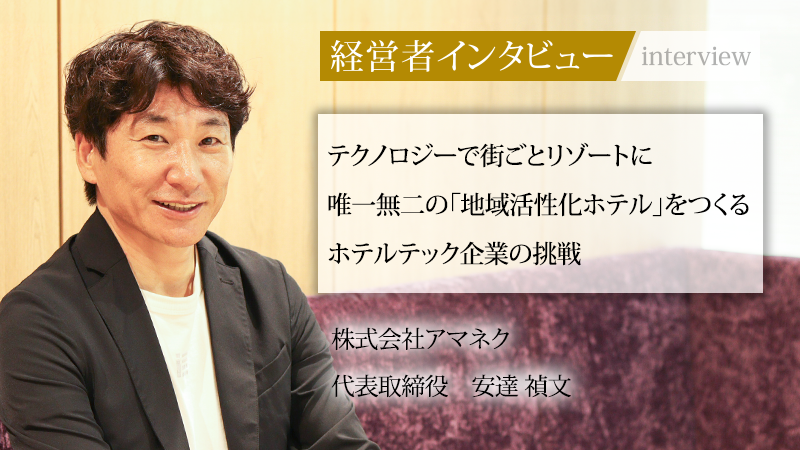
株式会社アマネクは「ホテルを核に、街全体を元気にする」をビジョンに掲げ、唯一無二のホテルを展開している。同社は、高い客室稼働率を誇り、さらに、自社開発システムを用いて宿泊客を街へと誘い、地域経済の活性化にも貢献している。この事業を牽引するのが、代表取締役の安達禎文氏だ。学生時代に起業を経験。そして、縁あって購入したホテルの稼働率を95%へと再生させた驚異の実績を持つ。失敗を恐れない挑戦の先に何を見ているのか、その軌跡と経営哲学に迫る。
偶然と必然から生まれたホテル事業
ーーこれまでのキャリアについてお聞かせください。
安達禎文:
高校卒業を機に大分から上京したのですが、個人事業の中古車販売で起業しました。車に乗りたいけど、お金がない。そこで「それなら、中古車を売買する事業をすれば、在庫として持っている間は乗れるじゃないか」と、古物商の資格を取り、個人売買情報誌に掲載して中古車の販売を始めました。今思えば安直な発想でスタートでした。
しかし「一度は会社組織というものを経験しておこう」と考えるようになり、就職活動を開始。求人情報を見て「出張でハワイに行ける」という一文に惹かれ、ハワイのリゾート不動産のタイムシェア商品を販売する会社に入社しました。
リゾート不動産販売の仕事をしている頃、通信環境が大きく変化し、大容量のデータ通信が可能なインターネット常時接続サービスが普及し始めました。そのような状況で「インターネットを使って中古車を販売できるのではないか」と思いつき、タイムシェアの仕事を続けながら、副業として夜間や土日を使ってインターネット上での中古車販売を開始しました。
当時、私の周りにはイランやパキスタン出身の中古車ブローカーの知人が多くいました。彼らは日本のオークションで中古車を仕入れ、海外へ輸出していたのですが、仕入れから船に乗せるまで2ヶ月ほどのタイムラグがあったのです。私はその期間を利用させてもらい、彼らが仕入れた車の写真を撮影し、さも自分の在庫であるかのようにウェブサイトに掲載しました。買い手がついたらその車を買い取って販売する、という手法です。当時はネットで車を売ること自体が珍しく、先駆的な試みだったと思います。
ーー中古車販売を本業へ切り替えるきっかけは何だったのでしょうか。
安達禎文:
中古車販売は、自分でも驚くほど軌道に乗りました。月に十数台も売れるようになり、本業の傍らでは到底手が回らない状況になってしまったのです。当時は年間365日、ほとんど休みなく働いていました。タイムシェアの仕事にもやりがいを感じていました。しかし、収入面で何倍もの差があったため、会社を辞めて事業に専念することを決意し、2002年に有限会社イープロジェクトを設立しました。
ーーそこから、どのようにして現在の事業へと繋がったのですか。
安達禎文:
ネット中古車販売は、大手の参入などで競争が激化しました。新たな事業を探していたところ、マンションディベロッパーに転職したリゾート不動産の同僚の勧めでポスティング事業を始めたのです。最初は「チラシをポストに入れて商売になるのか?」と半信半疑でしたが、しかし不動産業界やスポーツクラブ等の「狭いエリアに集中的に販促したい」というニーズと合致して急成長しました。このご縁で不動産事業も始めることになったのですが、直後にリーマンショックが起こり、大変苦労をしました。
そんな時、友人が小さいホテルを取得しようとしていたのですが、銀行融資がつかなくて買えない、代わりに買ってくれないかと話がありました。なかば強引に説得される形で、そのホテルを購入することになったのです。全く予期しない出来事でしたが、これが弊社のホテル事業の始まりです。
失敗を恐れない挑戦が生んだV字回復

ーーホテル事業をスタートされた頃のことをおうかがいできますか。
安達禎文:
本当に、何から手をつけていいか分からない状態からのスタートでした。しかし、やるしかない。手探りでリノベーション計画を立て、考えうる限りの施策を試しました。すると、当初40%程度で低迷していた客室稼働率は、取得からわずか1年半ほどでコンスタントに95%を超えるまでになりました。高い投資利回りも確保でき、「これは面白い事業になる」と確信しました。この成功体験が、ホテル事業を本格的に拡大していく大きな原動力となったのです。
ーーその後の展開についてもお聞かせください。
安達禎文:
2軒目は湯布院という大分県の山奥の温泉地にある旅館でした。商談の場で私が「大分出身なんです」と話すと、「それはご縁ですね、ぜひ買ってください」という流れで取得が決まりました。その旅館は昭和30年代に建てられた非常に古いもので、ここでもリノベーションに力を入れました。特に庭園は、世界的に有名なランドスケープデザイナーに手掛けてもらうことができ、見違えるように生まれ変わりました。
そして、当時としてはまだ珍しかった海外からのお客様をいち早く積極的に受け入れたのです。この戦略が功を奏し、こちらも稼働率が当初の50%台から99%にまで跳ね上がり、売上は2.6倍になりました。何より嬉しかったのは、収益が改善したことで、社員の待遇を大幅に改善でき、心から喜んでもらえたことですね。
ーー挑戦の裏には失敗もあったかと思いますが、それをどう捉えていますか。
安達禎文:
「失敗を恐れないこと」を大切にしています。以前、お寺さんが使う檀家さんの故人台帳である「過去帳」をデジタル化した「過去帳アプリ」を開発したことがありました。しかし、事前のマーケティングを怠ったため、完成してから強力な競合サービスがあることに気づき、全く売れませんでした。そういった失敗は山ほどしています。
ですが、私は社員に「失敗してもいいから挑戦しろ」と常に言っています。挑戦するからこそ失敗があるのであり、何もしない人間よりも、挑戦して失敗した人間の方がはるかに価値があります。小さな失敗はむしろ積極的に経験すべきだと考えています。
金太郎飴ではない唯一無二の「アマネク流」ホテルづくり
ーー宿泊事業での直近の取り組みについて、詳しく教えてください。
安達禎文:
当初は、古いホテルや旅館を安く購入し、リノベーションと運営改善によって価値を高める「バリューアップ」という手法を採っていました。価値が上がったホテルは売却し、運営だけを弊社が継続する手法を採りました。これは「セール・アンド・リースバック」というものです。この手法で限られた資金を効率的に回転させながら、施設数を増やしていきました。
しかし、インバウンド需要の高まりと共に、ホテルが不動産として注目されるようになりました。その結果、中古ホテルの市場価格が信じられないほど高騰してしまったのです。専門用語で「再調達価格」というのですが、新たに土地を取得してホテルを建てる金額を上回る価格で取引される事例も出てきましたので「それならば、土地の仕入れから自分たちで手がけよう」と方針転換し、2016年に初めて自社で企画した新築ホテルを銀座につくりました。
ーー自社で企画されたホテルでは、どのような点を大切にされましたか。
安達禎文:
これまで中古物件の再生では実現できなかった、私たちの「やりたかったこと」をすべて表現しました。こだわったのは、「上質な和のテクスチャー」です。過度に日本を押し付けるのではなく、海外のお客様が自然に心地よいと感じる空間を目指しました。また、客室の機能性にも徹底的にこだわりました。客室は連結・分離が可能なベッドで多様な客層に対応し、洗い場付きの広い浴室で快適性を追求しました。
このホテルは非常に高い評価を受け、近隣の競合ホテルと比較して、平米あたりの客室単価が際立って高い数値を記録したのです。この成功が、弊社のホテルづくりのコンセプトを示すショーケース(※1)となり、その後の展開に繋がっていきました。
弊社でホテルを企画する際、「金太郎飴のようなホテルは作らない」という考えを大切にしています。どこに行っても同じようなチェーンホテルを1つ増やすだけでは、弊社が手がける意味がない。手間はかかりますが、その土地の特色を最大限に活かし、常に新しいもの、マーケットに合ったものをつくりたいのです。
たとえば、旭川のホテルでは現地の旭川家具を使い、別府では屋上にインフィニティ温泉プールを設置しました。また、ハード面だけでなくソフト面の体験も重視しています。たとえば、海外の方に人気のお弁当づくり体験「アマネクアカデミー」や、小学生向けの職業体験プランもその一環です。アマネクアカデミーは入社2~3年目の若手社員のアイデアから生まれました。「泊まって良かった」と思ってもらえる新しい仕掛けを常に考え続けています。
(※1)ショーケース:企業や団体が自社の商品、サービス、技術、才能を広く一般に披露するための展示や発表の場
ホテルを核に街全体をリゾートへ変える地域活性策

ーー「地域活性化ホテル」というコンセプトについて詳しくお聞かせください。
安達禎文:
弊社が企画・運営するホテルは、お客様がホテルの中だけで楽しんで完結する施設を目指していません。むしろ、ホテルを拠点として積極的に街へ出ていただき、街全体を一つの大きなリゾートのように楽しんでいただく。それによってホテルだけでなく地域全体が活性化することこそ、私たちの理想とする姿です。特に別府のホテルでは、あえて館内に夕食レストランを設けていません。お客様に街の多様な飲食店へ足を運んでもらう取り組みを積極的に行っています。
ーーコンセプトを実現するための、具体的な施策について教えてください。
安達禎文:
中核を担うのが、自社で開発した「部屋付けシステム」です。これは、ホテルのルームキーを使って、提携している地域の飲食店・カラオケ・スナックなどをあたかもホテルの付帯施設のように「部屋付け」ができる仕組みです。お客様は滞在中の支払いをすべて宿泊費とまとめてチェックアウト時に精算できるため、手ぶらで街歩きを楽しめます。特に現金を持ち歩かない訪日外国人観光客にとっては、非常に便利なキャッシュレス決済手段となります。このシステムは、お客様の利便性を高めると同時に、地域経済へ貢献する流れを生み出し、街の皆さんからも大変喜ばれています。
また、冊子とGoogleマイマップで提携店の情報を皆様に展開しています。お客様は魅力的なお店の場所を簡単に知ることができ、より気軽に街へ出かけるきっかけになります。この「部屋付けシステム」によりお客様の体験価値を高めながら、地域に貢献しているのです。
3本の柱で未来を拓くホテルテック企業としての展望
ーー今後の事業で特に注力していくテーマは何でしょうか。
安達禎文:
今後は、採用、管理体制、ソフトウェア開発の3点を強化していきます。事業拡大に伴う人材の採用・育成は非常に重要です。特に弊社は新卒からじっくり人材を育てていく文化を大切にしており、昨年には初めて、新卒で入社した社員が支配人に昇格しました。こうした循環が社内に生まれてきたのは、会社として大きな喜びであり、財産です。また、株式上場を視野に入れており、そのための強固な管理体制の構築も急務となっています。
先ほどお話しした「部屋付けシステム」もそうですが、弊社はホテルの基幹業務システムも自社で開発しています。これまでの世の中にはなかった、非常に画期的な仕組みを盛り込んでいく予定です。完成後は、外部のホテルにもサービスとして販売していく計画です。弊社は単なるホテル運営会社に留まるつもりはありません。テクノロジーでホテル業界全体、そして地域社会に新しい価値を提供する「ホテルテックカンパニー」へと進化していく。それが私たちの目指す姿です。
ーー最後に、5年後、10年後の会社のビジョンをお聞かせください。
安達禎文:
現在は、リアルな場を提供する「宿泊運営」と「不動産開発」が事業の二本柱です。これに、今まさに注力している「システム開発」という第3の柱をしっかりと確立させたい。そして、この3本の柱で会社を力強く成長させていきたいです。客室数として5000室体制を一つの目標としていますが、やみくもに出店するつもりはありません。デベロッパー、物件の保有会社、そして運営を担う弊社、プロジェクトに関わるすべての関係者がきちんと収益を上げ、皆が笑顔になれる。そんな事業を、これからも一つひとつ大切につくり上げていきたいと考えています。
編集後記
学生時代の中古車販売から始まり、ポスティング、不動産、そしてホテル事業へ。安達氏のキャリアは、予測不能な挑戦の連続だ。しかし、その実行力の裏側には、自身の経験に裏打ちされた「失敗を恐れず、挑戦する」という確固たる哲学がある。既成概念に捉われず、道を切り拓いてきた者の力強さを感じさせる。アマネクの挑戦は、「未来は自らの手でつくり出せる」ということを示していくだろう。

安達禎文/1975年大分県生まれ。明治大学政治経済学部政治学科卒業。リゾート不動産会社勤務を経て、2002年株式会社イープロジェクトを設立し、同社代表取締役就任。2006年株式会社エスタックスを設立し、同社代表取締役に就任。2010年コンフェスタイン河辺を開業し、ホテル事業を開始。2018年に組織再編・会社名称を変更し、株式会社アマネク代表取締役就任。本年開業施設を含め全国で11棟のホテルを運営。














