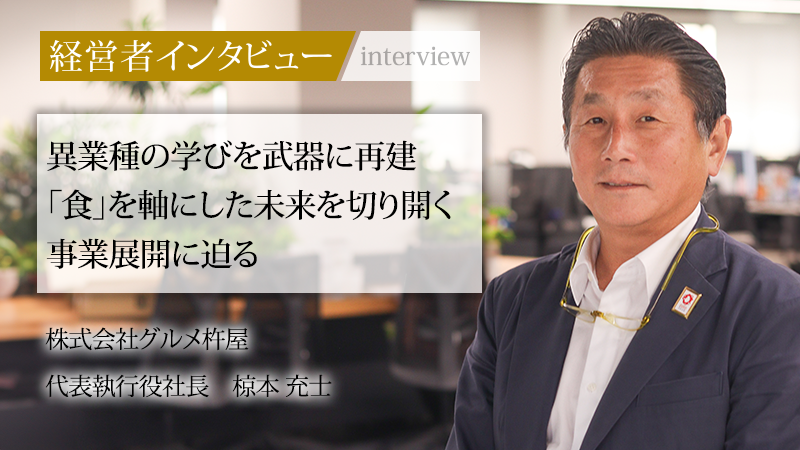
うどん店「杵屋」で知られる株式会社グルメ杵屋は、多角的な「食」の総合企業である。レストラン事業に加え、機内食や冷凍食品、さらに海外人材を育成する日本語学校まで運営している。20年間続いた低迷をV字回復させたのが、代表執行役社長の椋本充士氏だ。異業種での経験を活かした「教育」への投資がその原動力となった。逆境を乗り越えた独自の経営哲学と、会社の未来を切り拓く挑戦について話を聞いた。
給料の高さで選んだキャリアの原点 異業種での経験が変革の礎に
ーーまずは、椋本社長のご経歴についてお聞かせください。
椋本充士:
大学3年生の終わり頃、父に就職の相談をしたところ「人生は楽しいぞ。好きなように決めたらいい」と背中を押され、就職活動を始めました。当初はアパレル業界を志望していましたが、活動を進める中で外食産業にも興味を持つようになり、最終的には当時最も初任給が高かった大和実業株式会社への入社を決めました。
大和実業は人材教育に非常に力を入れている会社で、入社後は4ヶ月の研修を経て店舗の副店長である「主任」に就任。その後、店長として勤務していたある日、本社の副社長から突然「実家に戻らなくていいのか」と尋ねられたのです。実はその頃、私の実家であるうどん店を展開していた会社と、洋食系の「株式会社グルメ」との合併話が進んでいました。副社長はその状況を知ったうえで、私の身を案じて声をかけてくださったのです。しかし、私自身は実家に戻ることをまったく考えていなかったため、その時はお断りしました。
それから数年後、再び副社長から今度は「業務命令だから帰れ」と強く促されました。その際に「あと何年いたいか決めろ。その間、俺が教えられることはできるだけ教える」と言ってくださったのです。その言葉通り、まず財務部に配属され、銀行の仕組みや資金繰りをイチから学びました。次にシステム開発部でプログラミングの基礎、その後は新規事業の開発も経験させていただき、経営に必要な知識とスキルを叩き込んでいただきました。これらの貴重な期間を経て、グルメ杵屋へ入社することになったのです。
赤字からのV字回復を導いた「教育」への逆張り投資
ーー社長就任時、貴社はどのような状況でしたか。
椋本充士:
私が社長に就任したのはリーマンショックの後で、会社の業績は非常に厳しい状況でした。実は1990年の「花の万博」以降、約20年間にわたって既存店の来客数が毎年少しずつ減り続けていたのです。その結果、会社は赤字に転落してしまいました。
赤字回復のため、人員整理や経費の見直しといったリストラも断行しました。しかし、一つだけ全く逆の施策を実行しています。それが「教育」への投資です。これは、私が大和実業で学んだ経験が大きく影響しています。大和実業では商品での差別化が困難でした。そのため、接客レベルといった営業努力でお客様に選んでいただく戦略をとっていたのです。だからこそ、教育に非常に力を入れていました。
その経験から、グルメ杵屋でも教育が不可欠だと判断したのです。店長たちが自ら考え、今日の営業を明日の営業につなげる意識を育むため、社外研修も積極的に導入し、経費を投じました。
ーー教育への投資は、どのような成果につながりましたか。
椋本充士:
最初は戸惑いもあったと思います。しかし研修を重ねるうちに店長たちの意識が変わり始めました。「お客様から『美味しかったよ、また来るね』と言ってもらえるようになった」という報告が次々と挙がるようになり、社内の雰囲気が明らかに変わったのです。結果、業績は驚くほどの速さで回復しました。教育への注力が、V字回復の大きな原動力になったと確信しています。
「食」を軸に社会課題へ挑む多角化戦略
ーー現在の事業構成について教えていただけますか。
椋本充士:
私が社長に就任した当時はレストラン事業が売上の9割以上を占めていました。しかし今では6割を下回っています。現在は機内食事業と冷凍食品事業が大きく成長しており、利益で言えば機内食事業はレストラン事業とほぼ同規模になりました。「食」を軸としながらも、事業の多角化を進めている状況です。
ーー人材確保についてはどのような取り組みをされていますか。
椋本充士:
3年前に自社で日本語学校を設立しました。コロナ禍以前から、来日した留学生が生活に困窮し、不法滞在者になってしまうという社会問題に関心がありました。そこで、安心して日本で学び、働ける環境を提供できないかと考えたのがきっかけです。
留学生が法律の範囲内(週28時間)の労働で安定した生活を送れるように配慮しました。弊社の機内食工場で働く技能実習生の給与水準を参考に、時給1,500円を保証。弊社グループのレストランでアルバイトできる仕組みをつくりました。
ーー注力されている海外人材事業について、詳しく教えていただけますか。
椋本充士:
自社で設立した日本語学校は非常に順調で、卒業生の出席率はほぼ100%です。今後は定員を増やし、300名体制を目指します。そして、この仕組みを自社だけでなく、人手不足に悩む他の企業にも展開していきたいと考えています。昨年からは、特定技能一号の資格を持つ外国人を社外の企業へご紹介する事業も準備中です。これは人材を育て供給する、海外人材のプラットフォーム事業です。将来的に、大きく発展する可能性を秘めていると考えています。
ロンドンでの成功から見据える海外展開とDXが拓く未来

ーー海外展開に対するお考えをお聞かせください。
椋本充士:
コロナ禍にロンドンの企業からフランチャイズのオファーを受け、うどん店を出店しました。これが非常に好調です。これを足がかりに、ヨーロッパでの展開を広げていきたいですね。ミラノ万博をきっかけに「出汁」の文化が広がりました。これをきっかけに、ヨーロッパでは和食への関心が非常に高く、大きな可能性を感じています。
ーーDXについては、どのような取り組みを進めていらっしゃるのでしょうか。
椋本充士:
弊社は創業から55年経ちますが、いまだに個店の努力や経験則に頼る旧来の「飲食業」の段階にあり、テクノロジーを活用して生産性を追求する「外食産業」へと進化できていないという課題感があります。この変革の鍵となるのがDXです。ここ数年は、DXに取り組むための前提となる会社の情報整理を進めてきました。今年を「DX元年」と位置づけ、あらゆる業務を見直し、生産性を高めていく考えです。バックオフィスの業務からレストランのオペレーションまで、全てが対象となります。
人口減少社会において、お客様に選んでいただける店づくりと生産性の向上は不可欠です。たとえば、配膳ロボットも、それを前提として設計された店舗でなければ本当の効率は生まれません。弊社も既存のやり方にとらわれず、ビジネスモデルそのものを根本的に見直す必要があります。DXを通じて、新しい時代の外食産業を創造していく覚悟です。
ーー最後にこれからの時代を担う方々へメッセージをお願いします。
椋本充士:
日本は今、人口が毎年数十万人単位で減少するなど、世の中が大きく変化しています。一方で、大阪では万博やIR(※1)の計画が進むなど、新しい動きも活発です。世の中が大きく動く時は、チャンスがたくさん生まれる時でもあります。このチャンスを誰がものにしていくのか。これから先の10年は、非常に面白い時代になるのではないでしょうか。ぜひ、この変化を前向きに捉え、新しい挑戦をしていってほしいと思います。
(※1)IR:日本初のカジノを含んだ統合型リゾート。
編集後記
キャリアの原点を「給料の高さ」と率直に語る椋本氏。20年続いた低迷を「教育」への投資で断ち切り、V字回復を実現した手腕は見事である。現在は日本語学校の運営を通じて、人手不足という社会課題にも挑む。変化を恐れず未来への種をまき続ける姿は、これからの時代を生きる私たちに多くの示唆を与える。

椋本充士/1961年大阪府生まれ、近畿大学卒業。大学卒業後、大和実業株式会社に入社し、1990年にグルメ杵屋へ入社。2010年に同社代表取締役社長(現・代表執行役社長)に就任。














