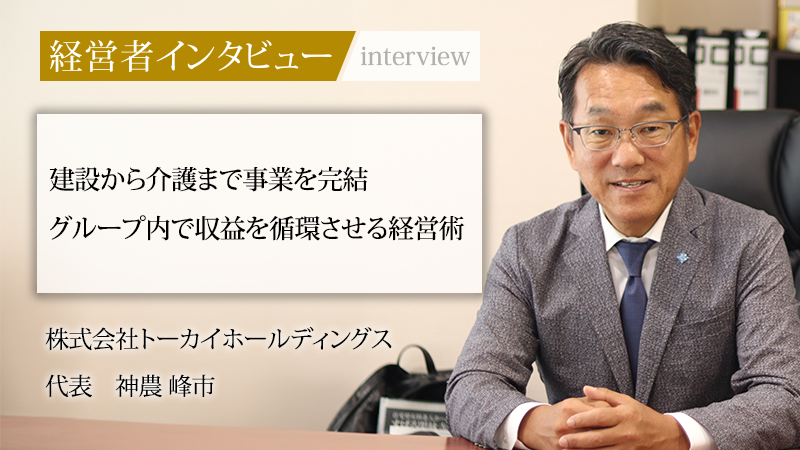
京都を拠点に、建設資材、生コンクリート、建設、不動産、そして「環境」と「介護」という、多岐にわたる事業を展開する株式会社トーカイホールディングス。各事業会社が独立性を保ちながら組織的に連携し、グループ全体で相乗効果を生み出す独自の経営モデルを確立している。この多角的な事業ポートフォリオを一代で築き上げたのが、代表の神農峰市氏だ。父親から事業を継承後、次々と新規事業を立ち上げ、時には大きな挫折を経験しながらも、その情熱で挑戦を続けてきた。数々の事業を成功に導いてきた同氏の経営哲学と、グループの未来を支える事業の展望に迫る。
20代で4事業を兼務 休みなき挑戦の日々
ーーこれまでのご経歴についておうかがいできますか。
神農峰市:
もともと「20代で何かを創業したい」という思いがあり、学生時代にレンタルビデオ屋を始めました。しかし1988年の大学卒業を控えた頃、転機が訪れます。当時父が率いていた丸神商事から「早く手伝え」と促される形で、同社に入社することになったのです。他社で修業するような時間的なゆとりもありませんでした。当時の丸神商事では生コンを生産していましたが、国が定める品質基準(JIS規格)を満たした正規の工場ではなく、規模も通常の10分の1ほどしかない古い設備からのスタートでした。
1990年頃には、現在の「トーカイ建設」の前身となる建設会社やチケットショップも手がけており、20代は休んだ記憶がありません。まさに、やらざるを得ない背水の陣でした。
結核での闘病が生んだ転機 我流経営からの脱却
ーー経営者人生におけるターニングポイントを教えてください。
神農峰市:
一度目の転機は、2000年に結核を患い、約半年間入院したことです。当時、仕事での失敗が重なり精神的に追い込まれ、自分はうつ病ではないかと思い込んでいました。そのため、病名が結核だと分かったとき、「精神的な病ではなかった、まだ死なずに済む」と、心から安堵したのを覚えています。その経験が吹っ切れるきっかけとなり、退院後は堰を切ったように仕事に没頭しました。
二度目の転機は、ある研修会社と出会ったことです。それまでは経験と勘と度胸だけで経営していましたが、自分のやり方の限界を痛感しました。そこで初めて本格的に経営の勉強を始めたのです。この経験を通じて、人の大切さや社員に対する思いが固まり、ビジネスにおける本当のターニングポイントになりました。
ーー異業種である介護事業は、どのような経緯で始められたのですか。
神農峰市:
大きなきっかけは2008年のリーマンショックです。不動産事業の縮小を余儀なくされ、社員を活かすために何か新しい事業はないかと考えました。また、父が3年間闘病した際に家族だけでの介護に大変苦労した経験から、介護事業にはもともと思いがありました。そして、2010年にデイサービス事業をスタートさせたのです。
多角化でシナジーを生む トーカイグループの全体像
ーー改めて、トーカイグループ全体の事業概要について教えていただけますか。
神農峰市:
中核の一つである丸神商事は、住友大阪セメントの特約代理店として建設・建築資材を販売しています。それに加え、事業用不動産、資源リサイクルの環境事業という合計3つの柱を持っています。
その他、グループはそれぞれ専門分野を持つ会社で構成されています。生コン製造の「トーカイコンクリート」、土木中心の「トーカイ建設」、不動産開発の「トーカイアセット」、介護事業の「トーカイライフサポート」などです。現在はホールディングス体制への移行を進めています。
ーーグループ内ではどのように連携し、強みを発揮しているのでしょうか。
神農峰市:
グループ内で事業が完結する仕組みがあることが弊社の強みです。たとえば、不動産会社の「トーカイアセット」が土地を購入して老人ホームを建てる際、土木が中心の「トーカイ建設」が工事を担います。そして、その施設の運営は介護事業を手がける「トーカイライフサポート」が行います。このように、グループ内で収益が循環する構造を構築しているのです。
環境事業の具体的な取り組みも進めています。廃プラスチックをセメント工場の燃料や原料として再利用する事業はその一例です。また、生コン工場から出るセメント系スラッジケーキを地盤改良剤などに再利用する新商品を関西大学と共同開発しました。常に「環境」というテーマを軸に、循環型社会に対応できる事業を発想しています。
10年で社長を5人つくる 人に光を当てる経営と未来への展望

ーー今後の注力分野である事業について、展望をお聞かせください。
神農峰市:
現在、注力しているのが「介護」事業です。「スバル」というブランドで住宅型有料老人ホームを展開しており、今後10年で10棟まで増やす計画です。この計画が進めば、グループ全体で売上100億円という目標も見えてきます。
さらに、この介護事業をある程度の規模になったら上場させることも考えています。主な目的は、事業拡大に必要な人材の獲得とグループ全体のブランディングです。介護事業であれば、有料老人ホームを増やしていくという成長戦略を市場に問いかけることができます。また、他の事業に比べて上場がしやすいと考えているため、一つの核として成長させていきたいです。
ーー今後、グループ全体としてどのような状態を目指していますか。
神農峰市:
現在5つある事業会社がそれぞれ自立し、中小企業から中堅企業へと成長していくこと。それが私の夢です。その中には上場する会社もあれば、非上場のまま着実に成長していく会社もあるでしょう。大切なのは、各社がしっかりと自走できる力をつけることです。
ーーその夢の実現には、どのような人材が必要だとお考えですか。
神農峰市:
各社の成長の舵取りを担える人材、つまり社長を任せられる人材です。今後10年かけて、そのような人材を5人育てたいと考えています。ただ、人材の獲得は簡単ではありません。今いる人材を育てつつ、採用も強化していきたいです。
かつて飲食店や物流会社なども手がけていましたが、最終的には信頼できる人間に会社ごと渡してきました。私の管理下にあるうちは、どこかで甘えが出てしまい、本当の意味で会社は伸びません。自己責任でリスクを背負って、「やってみろ」と任せた方が本人のモチベーションも上がり、会社の成長へとつながるのです。
編集後記
次々と事業を立ち上げては、軌道に乗ると惜しげもなく手放していく。取材を通して見えてきたのは、事業家というよりも、人を育て、挑戦の「場」をつくり続けるプロデューサーとしての神農氏の姿であった。数々の失敗や病という逆境さえも、次なる飛躍へのバネに変えてしまう圧倒的なエネルギーの源泉は、「人への信頼」にあるのかもしれない。「私の管理下にあるうちは伸びない」と語る言葉は、社員一人ひとりの可能性を信じ抜く覚悟の表れだろう。人に光を当て、未来を託す。同社の挑戦は、これからも多くの経営者を生み出していくに違いない。

神農峰市/1965年生まれ。1988年大学卒業後、丸神商事に入社。1995年に同社代表取締役社長に就任。現在に至る。














