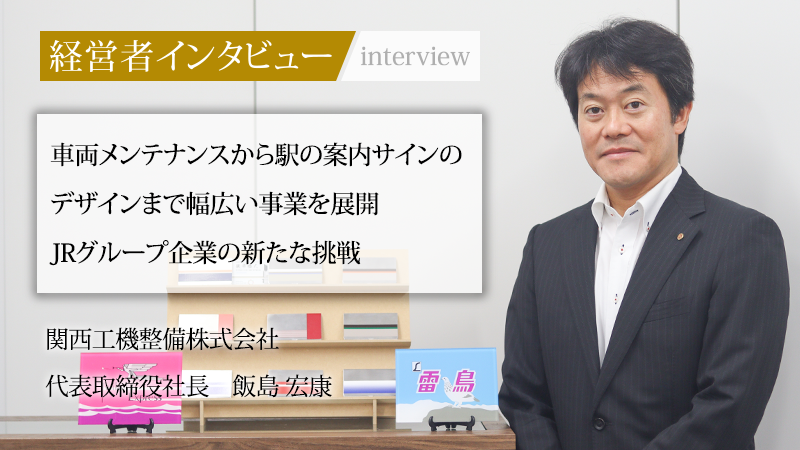
JR西日本グループの一員として、鉄道車両のメンテナンス事業を基盤に発展を遂げてきた関西工機整備株式会社。同社が礎にするのは長年培った安全・品質への信頼だ。そして、デザイン力を融合させた印刷事業を新たな成長の柱として確立しようとしている。2025年7月に代表取締役社長に就任したのは飯島宏康氏。JR西日本での運転士や現場責任者を経験し、中小企業への出向というキャリアを持つ。現場の肌感覚を何よりも大切にする同氏に、会社の強みと未来への展望を聞いた。
本社と現場の乖離から学んだマネジメントの原点
ーーこれまでのご経歴についてお聞かせください。
飯島宏康:
大学卒業後、JR西日本へ入社しました。私が就職活動をしていた1997年はいわゆる就職氷河期でした。大学で学んでいた金属材料の分野は、特に求人が少ない状況だったと言えます。そのため、専門分野を超えてさまざまな会社を勉強しており、その中で最も早く内定を出してくれたのがJR西日本です。当時は500系新幹線のデビューが近づいていました。高速鉄道の技術開発が盛んな時期でもあったので、工学系の知識を生かせる場所があるだろうと考えました。
ーー入社後は、どのようなことに取り組まれていたのでしょうか。
飯島宏康:
入社して5年間は、金沢で鉄道の基礎を学ぶ期間を過ごしました。そのうち2年半ほどは「雷鳥」や「しらさぎ」といった特急列車の運転士も務めています。その後、本社勤務を経て、岡山の現場で責任者として3年間働きました。このとき、本社で考えていることと現場の実態との間に、ズレがあることを痛感します。この経験から現場の社員の「意見」を大切にするという思いを、強く持つようになりました。
大企業から中小企業へ 価値観を揺るがした出向経験

ーーキャリアの転機となった出来事はありますか。
飯島宏康:
JR西日本のグループ会社がM&Aをした従業員100人弱の小さな会社への出向が転機となりました。この会社は、主に鉄道車両のモーターをメンテナンスしている会社です。そこではまず、JRという大組織から中小企業へ移ったことで、カルチャーショックを受けます。これまでの価値観が崩れるような感覚で、大企業の論理が全く通用しない世界でした。当時の営業部長から「文句を言ったら仕事をもらえませんよ」と言われるほどです。これまでとは全く違う立ち位置を痛感しました。
そこでの経験から、本当の意味での競争とは何かを学びました。コロナ禍において仕事が急激になくなり、ライバル企業と激しい仕事の奪い合いが始まりました。JRの事業は、基本的に他社に領域を侵されることはありません。しかし、そこでは常に全力で走り続けないと仕事を取られてしまう、止まることが許されない厳しい環境でした。この切迫した経験は、経営を考える上で非常に大きな財産です。
ーーどのようなご経験や実績が、今回の社長就任につながったと思われますか。
飯島宏康:
現場での経験と、組織を改革する力が評価されたのだと考えています。たとえば、以前責任者を務めた岡山の現場は、職場環境にさまざまな課題がありました。しかし、社員とのコミュニケーション機会を増やし、仕事の仕組みやルールを見直すことで、3年間で大きく改善させることができました。こうした実績があったからこそ、事業承継という難しい課題を抱えた中小企業への出向も任されたのだと思います。現場に根ざし、組織をより良い方向に変化させてきたこと。その点を評価いただき、社長という大役を任せていただけたのではないでしょうか。
安全・品質への信頼とデザイン力を掛け合わせた独自の価値

ーー貴社の事業内容についてお聞かせください。
飯島宏康:
弊社の事業は3つの柱で成り立っています。1つ目の柱は、JR西日本の車両メンテナンス工場内での業務です。鉄道車両部品のメンテナンスや、資材の管理・積み下ろし・運搬など、車両メンテナンス工場内の多岐にわたる業務を担っています。
2つ目の柱は、印刷事業です。もともと国鉄時代に車両の形式番号などを手で書いていた塗装部門が起源となります。時代の変化とともに印刷へとシフトし、今では業務内容も多様になりました。車両側面のラインカラーや優先座席のマークといった各種サイン、さらには駅に掲示される路線図のデザインまで、幅広く手掛けています。この印刷事業が順調に拡大し、現在では会社全体の売上の4割を超えるまでに成長しました。今後も印刷事業を会社の成長の柱として、さらに伸ばしたいと考えています。
3つ目の柱は、物販事業です。これまでの車両部品のメンテナンスでお付き合いのあった化学メーカーと共同開発して、もみ殻を原料にした「シリカ」という素材を使った「遮熱コーティング剤」を販売しています。服や日傘、作業用ヘルメットなどに直接塗布することにより太陽等の輻射熱を反射する商品です。その他にも、実際の鉄道車両で使用されている車両側面ラインカラーを用いた「ステンレス製名刺入れ」なども販売中です。
ーー貴社ならではの強みは、どのような点にあるとお考えですか。
飯島宏康:
弊社の基盤は、JR西日本の車両メンテナンスで培った「信頼」です。安全・品質に対して高い評価をいただいています。その上で、印刷事業で培ってきたデザイン力や技術力が新たな価値となり、融合できる点が強みです。たとえば、車両のラッピングは、ただ貼るだけではありません。古いシールを効率的に剥がす「剥離」の技術を徹底的に研究しています。他社がやらないような地道な部分を突き詰めることで、信頼をさらに高めていきたいです。
事業の未来を拓くブランディング戦略と組織改革
ーー現在、どんな課題を感じられていますか。
飯島宏康:
弊社の鉄道車両のメンテナンス事業は、女性や高齢の社員が主力であり、人材確保が課題です。洗浄作業など、機械化できるところは積極的に進め、省力化を図る必要があると考えています。
一方の印刷事業では、確固たる品質とデザイン力が武器です。しかし、「関西工機整備」という社名は、どうしても「鉄道のメンテナンス会社」というイメージが強すぎます。新しい業界の顧客からは、専門性を感じにくいかもしれません。「なぜ鉄道の会社がデザインを?」と不思議に思われる可能性もあります。会社の見せ方、つまりブランディングを戦略的に変えていく必要性を感じています。
直近では「TRANGIS←」というブランド名を立ち上げました。このブランドをもって、「デザインのプロ集団」と認知いただくことで、スムーズに商談を進めたいと考えています。

ーー今後の事業展開についてはどのようにお考えですか。
飯島宏康:
「TRANGIS←」は、逆から読むと「SIGNART(サインアート)」と読むように、ブランド名にも遊び心を持たせています。ともすると、無味乾燥になりがちなサインや標識をお客様との大切な「コミュニケーションの機会」と捉え、お客様がご覧になって楽しんでいただける、ワクワクするようなデザインを常に提供し続けることが私共の使命であると考えています。
また、このようなデザインを鉄道以外の様々な分野でご活用いただけるよう、新たなターゲット層への訴求も図っていきたいと思います。これからも、JR西日本グループが大切にしている「地域共生」の想いを共有し、デザインを通じて地域や社会との絆を深めてまいります。
編集後記
JR西日本という大組織での現場と本社、そして中小企業での熾烈な競争。飯島氏のキャリアは、その両極を深く知ることで形づくられてきた。伝統的なメンテナンス事業の基盤を守りつつ、デザインという新たな価値を創造している。その複眼的な視点が、事業を牽引する原動力なのだろう。鉄道の安全を支える「信頼」を武器に、今後は社会のさまざまな場面をデザインで彩っていく。同社の挑戦は、まだ始まったばかりだ。

飯島宏康/1971年愛知県生まれ、東北大学工学研究科卒。1997年西日本旅客鉄道株式会社に入社し、金沢支社で約5年間、車両メンテナンス、運転士、指令員といった現場業務を経験し、車両の技術者として主に本社で勤務。2019年、株式会社JR西日本テクノスの子会社である株式会社富士電機製作所の取締役に就任。約3年間、コロナ禍の厳しい外部環境下で会社経営を学ぶ。JR西日本本社勤務を経て、2025年同社代表取締役社長に就任。














