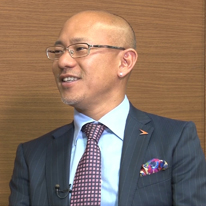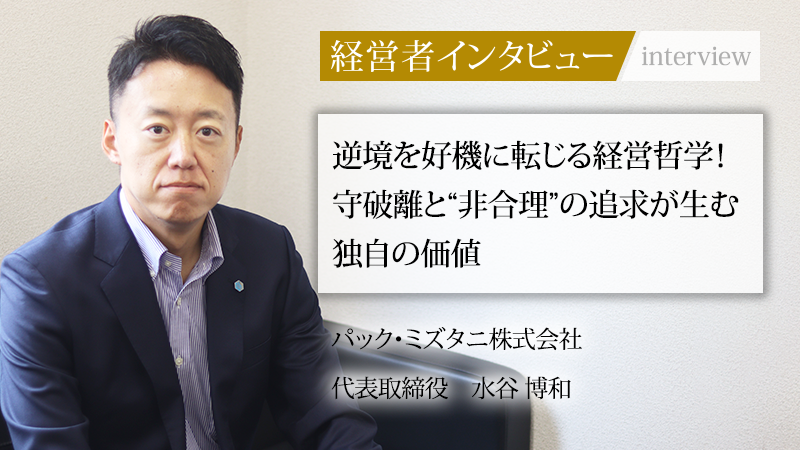
段ボール梱包資材を製造する「メーカー」と、顧客の物流を担う「3PL(サードパーティー・ロジスティクス)」、2つの顔を持つパック・ミズタニ株式会社。同社を率いる代表取締役の水谷博和氏は、26歳で事業を継承後、主要取引の半減やコロナ禍といった幾多の逆境を、卓越した経営手腕で乗り越えてきた。その原動力である長期構想「守破離」と、「“非合理”の追求」という独自の経営哲学に迫る。
異業種で培った俯瞰の視点と「守破離」の経営
ーーまずは水谷社長のご経歴からお聞かせください。
水谷博和:
幼い頃から家業を継ぐことは意識していましたが、父の「同業で働くのではなく、一度外から俯瞰して見てきなさい」という助言を受け、最初はヤマト運輸株式会社の門を叩きました。
会社の都合で1年足らずで家業に戻ることにはなりましたが、この経験は私にとって非常に大きな財産です。お客様の課題解決に寄り添う「コトづくり」の視点、そして“サービスが先、利益は後”の考え方とその実践の重要性を学びました。何より、現場で汗を流す仲間たちの生の声に触れる中で、経営と現場の間に存在する温度差を埋める「対話」こそが、組織を動かすうえで不可欠だと痛感したのです。
ーー家業に戻られてから社長に就任されるまでは、どういったお仕事をされていましたか。
水谷博和:
家業に戻った後、自動車大手メーカーへ1年3ヶ月ほど出向し、改善プロジェクトに参加させていただく機会に恵まれました。お客様の、さらにその先にいらっしゃるお客様まで見据えるという、広範な視野を養うことができました。
その後、父が急逝し、26歳で祖父から会社を託されることになったのです。当時はメーカー経営の知識も経験もありませんでしたから、まずは先人の教えに倣う「守破離」の考え方で経営に臨むことにしました。最初の3年で会社を知り尽くす「守」、次の3年で自分なりの変化を加える「破」、そして最後の3年で新たな事業を確立する「離」。この9カ年計画が、私の経営の羅針盤となりました。
取引半減とコロナ禍、二度の逆境を飛躍の好機に変えた一手
ーー社長就任後の変化や出来事はございましたか。
水谷博和:
2013年のことでした。主要顧客であった自動車メーカー様の作業が内製化され、仕事が半分以下に激減したのです。当時、現場には50名以上の従業員がいましたが、会社に残ってくれた40数名の社員を何としても守り抜かねばならない。その一心で、一部の社員には伊丹事業部へ異動してもらうという決断をしました。
仲間は守れても固定費は変わらず、収益は悪化の一途を辿る。まさに絶体絶命の状況を打開すべく、段ボール事業で取引のあった約200社のお客様に物流サービスを提案する「クロスセル」に舵を切ったのです。倉庫業の経験はありませんでしたから、外部倉庫を借りるところからのスタートでした。外部から営業部長を招聘し、自動車メーカーで培った品質管理能力と、中小企業ならではの意思決定の速さを武器に提案を重ねました。その結果、物流事業は現在7センター、7000坪を超える規模にまで成長を遂げることができました。
ーーそのご経験は、その後の経営にどのような影響を与えましたか。
水谷博和:
コロナ禍という未曾有の危機に直面した際、その経験が活かされました。2013年の苦境から「厳しい時こそ、新しい成長のきっかけが生まれる」という確信を得ていたのです。
ちょうど新規で倉庫を増やす計画の最中にコロナ禍となり、予定していた需要が白紙になってしまいました。しかし、そこで立ち止まるのではなく「どうせ転ぶなら、しっかり前に転ぼう」と決意し、「2カ月限定、倉庫200坪無償提供」という大胆なキャンペーンを打ち出したのです。物流が寸断され、行き場のない製品を抱えるお客様のニーズが必ずあるはずだ、という仮説からでした。
この取り組みで何より嬉しかったのは、多くのお客様から「パック・ミズタニが段ボールだけでなく物流もやっていると初めて知った」というお声をいただけたことです。これが大きな反響を呼び、多くのお客様との新たなご縁につながりました。
「非合理の追求」が生む価値。製造と物流を掛け合わせた独自の強み
ーー幾多の困難を乗り越え成長を続ける貴社の強みについて教えてください。
水谷博和:
パッケージ事業では、強化段ボールを用いた重量製品向けの特殊な梱包材を得意としています。そして物流事業では、お客様の倉庫業務を代替する3PLを展開しています。特に、兵庫県西宮市内に構える阪神流通センター内外に6つの拠点を集中させ、従業員のスキルを可視化した「多能工表」をもとに、センター間で応援体制を柔軟に組める機動力が我々の強みです。
さらに近年は、「タイミー」などを活用したスポットワーカーの皆様にも積極的にお力添えいただいています。ただ作業をお願いするだけでなく、初心者の方でも分かりやすい手順書を整備するなど、弊社のファンになっていただくための仕組みづくりにも注力しています。
ーー水谷社長の経営哲学で、特に大切にされている価値観はございますか。
水谷博和:
それは「非合理の追求」です。短期・小ロットの保管や、短納期で多くの人員が必要な作業など、他社が敬遠しがちな複雑で手間のかかる案件にこそ、私たちが積極的に飛び込んでいく。これをやり遂げることで、お客様との関係性をより深く、太いものにしていくのが我々のイズムです。
「ハコから、ハコブを変える。」未来への投資が成長の原動力

ーー今後のビジョンについてお聞かせ願います。
水谷博和:
「ハコから、ハコブを変える。」というミッションを掲げ、パッケージと物流のシナジーを極限まで追求していきます。2029年の創業120周年に向けて売上30億円という目標を掲げており、その実現のために物流倉庫の増床も積極的に進めています。特に九州市場は大きな成長が見込めると考えており、伊丹のモノづくりと西宮の物流サービスを掛け合わせ、新たな価値を創造していきます。
ーー事業拡大に向け、採用や人材育成においてはどのようなお考えをお持ちですか。
水谷博和:
新卒で入社された方には、まず現場を知っていただくことを何よりも大切にしています。特定の部署に固定するのではなく、ジョブローテーションを通じて多様な業務を経験し、ご自身の希望に限りなく沿ったキャリアパスを描ける環境を整えていきたいです。中途採用の方には、ゼロから倉庫を立ち上げるようなプロジェクトに参画いただく機会もあり、ご自身のキャリアにとって大きな飛躍の舞台になると確信しています。
ーー最後に、読者へメッセージをお願いします。
水谷博和:
弊社は変化量の多い会社です。新しいことに挑戦したい、仕組みをより良くしたいという情熱を心から歓迎します。モノづくりとサービスの両面を持ち、役職にかかわらず誰もが当事者意識を持てる風土があります。多様な分野に挑戦できる環境で、皆さんの可能性を存分に発揮してほしいと願っています。
編集後記
「どうせ転ぶなら、しっかり前に転ぼう」。取材中、水谷社長が穏やかながらも力強く語ったこの言葉に、あらゆる逆境を成長の糧へと変えた不屈の意志を感じた。「守破離」という長期的視点と、「非合理の追求」という本質を射抜く独自の価値観。変化の激しい時代を航海するための羅針盤が、同社の歩みには示されている。
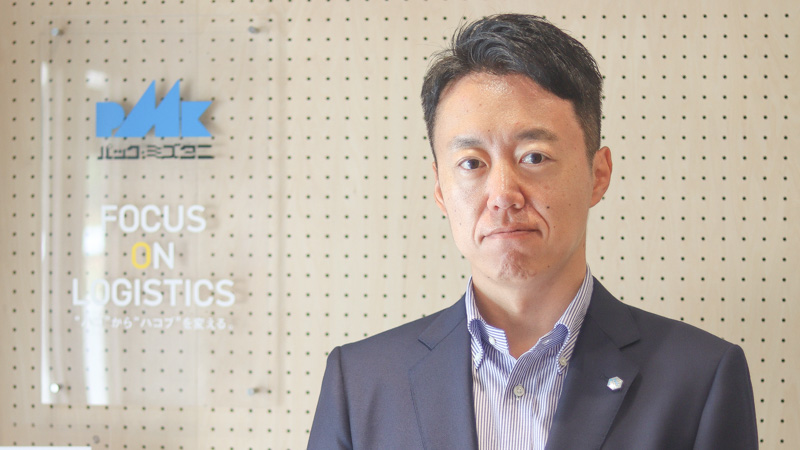
水谷博和/1983年大阪府生まれ、関西大学商学部卒。ヤマト運輸株式会社に入社し、1年後パック・ミズタニ株式会社に入社。2010年に同社代表取締役社長に就任。