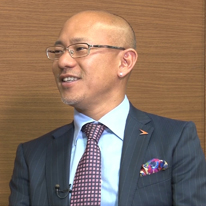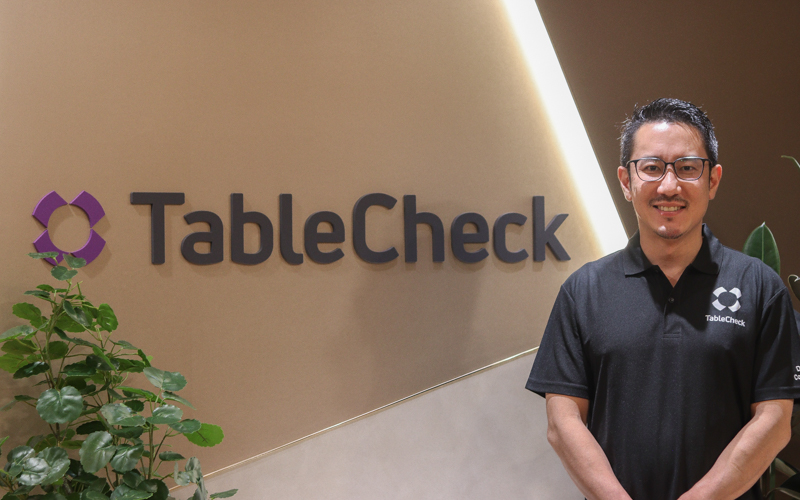うつ病や認知症といった精神・神経系疾患は、いまや社会課題の一つである。年々罹患者数が増加し、対策が急務となっている一方で、診断は医師による問診や本人のアンケートなどに頼っているのが現状だ。そんな課題を解決するのが、PST株式会社が開発する「音声バイオマーカー」技術である。同社代表取締役の大塚寛氏に、技術開発の経緯や今後の事業展望について話を聞いた。
スパコンメーカーからロボットビジネスの世界へ
ーー社長のご経歴を教えてください。
大塚寛:
幼い頃からロボットや機械、未来のことを考えるのが好きで、大学(工学部)に進学しました。大学卒業後、外資系のスーパーコンピューター(※1)メーカーに入社し、茨城つくば営業所に配属されました。クライアントは、10年、20年先を見据えた地震や宇宙に関連する研究をしている組織や企業で、未来を感じられて非常に興味深かったです。
その後、コンピューターグラフィックス(CG)を生成する世界的に有名なコンピューター会社と合併しました。そこではビッグデータを可視化することで未来を洞察する世界を目の当たりにして、充実感をおぼえていました。東京本社に戻ってからは、冷え込んでいたグラフィックス市場を再活性化させるという任務を命じられました。この時の経験が、のちのロボット事業につながります。
(※1)スーパーコンピューター:通常のパソコンよりもはるかに高速に計算できるコンピューター
ーーロボットビジネスを始めるきっかけについてお聞かせください。
大塚寛:
きっかけをつくってくださったのは、ソニーCTOの北野宏明先生です。私が在籍していた会社が、北野先生が提唱したロボカップのワールドワイドスポンサーとなったことを機に、ロボットビジネスに本気で取り組み始めました。
ーーそこから音声技術という領域に飛び込まれたのはなぜでしょうか。
大塚寛:
ロボットビジネスに携わっているうちに、ロボットが使えなくなったら捨てられてしまうということに疑問を抱くようになりました。SDGsの観点からも望ましくありません。たとえば生命が宿っていなくてもぬいぐるみを捨てるのは抵抗を感じますよね。同じようにロボットにも感情移入できれば、捨てにくい文化をつくれるのではないかと考えました。
さらに、人間が一方的にロボットに感情移入するだけでなく、ロボットの側も人間の感情を理解できたら、非常に良いパートナーになれるのではないかという発想で、感情そのものを研究することにしました。感情は声に現れます。声を解析することで感情を検知できるのではないか、さらには健康状態も測れるのではないかという流れで、音声による病態分析というテーマに行きつきました。
弊社が開発した技術では、2、3ワード発話してもらうだけでストレスを客観的に数値化することができます。さらには、メンタルの状態や認知機能低下の進行度合いを測定することも可能なのです。日常的に人の状態を捉えるために、「バイオマーカー(※2)」として採血や採尿などを採取することで客観的な健康状態を把握します。これからの時代は手軽に採取可能な「採声(さいせい)」という時代を見据え、この技術を「音声バイオマーカー」と呼んでいます。音声バイオマーカーで自身の健康状態を日常的に把握することで、より重篤な病の早期発見や予防など行動変容を社会にもたらしたいと考えています。
これまで、人の精神状態を客観的に数値化する技術はありませんでした。メンタルクリニックでの診断は、問診や本人の自己申告を中心に行われています。その結果として投薬が決まる現状があります。共同開発した東京大学とも「世の中にないものは、つくるべきだ」と意見が一致し、開発に至りました。
(※2)バイオマーカー:生物学的指標。一般的には体温や心拍数、血圧、血液、尿など、人の健康状態や、疾患の診断基準、将来的な発症リスク、現在受けている治療の効果を評価するための検査項目や生体内の物質を指す
被験者に負担をかけず精神状態を数値化する革新的な技術

ーー貴社の事業内容をお聞かせください。
大塚寛:
弊社の「音声バイオマーカー」技術は、音声から心身の状態を数値化するものです。数単語を発話していただくだけで、心のコンディションや認知機能の状態を数値化します。話すだけなので被験者に負担がかからない、優しいテクノロジーです。
医療機関と連携した研究現場では、新型コロナウイルスの中等症以上の推定や、睡眠時無呼吸症候群の推定に役立てられています。また、SOMPOケアさまと共同で、高齢者の嚥下(※3)機能低下を音声から計測する技術も開発しました。さらに、心不全状態も音声から計測できることが分かっています。
私たちは、見えなかったものを見える化することで、新しい価値をお届けしたいと考えています。この技術は言語ではなく声帯や周波数に注目しているため、日本人だけではなく世界で利用いただけます。
(※3)嚥下(えんげ):食べ物を口に取り込んでから、食道を通って胃に送り込むまでの、一連の飲み込む動作
ーー技術開発の強みについて、どうお考えですか。
大塚寛:
弊社は、先進的な「非侵襲型」アプローチとして「声」に着目して研究開発を行うことで、4つの強みを自負しています。
1つ目は、さまざまな医療機関さまや医学界の権威ある先生方との関係性が構築できていること。2つ目は、関連法規制に基づいて、医療機関さまから収集した質の高いデータ(医師の診断内容とそれに紐づく患者さまの音声データなど)を多く保有していること。3つ目は、高性能AIとの連携も含めて、そのデータを正しく検証して、科学的根拠(エビデンス)に基づいて製品開発を行うことができる優秀な研究者(画像や動物の声、音響工学の専門家など)が揃っていること。4つ目は、10年以上に渡る研究活動により、特許化された当社独自の音声解析技術を有していることです。
ヘルスケアとメディカルの両輪で事業化
ーー「音声バイオマーカー」技術を用いた事業について教えてください。
大塚寛:
法人向けサービスとして「VOISLOG® Miシリーズ」はWeb上で展開しています。従業員の皆様に、毎日の業務開始時に短い言葉を話していただき、心のコンディションを数値化します。(事前にご本人の承諾を得た上で)そのデータ傾向を産業医や人事部の責任者などが確認し、必要に応じてラインケアする仕組みです。また、オンライン会議での音声を使って心のコンディションを計測することもできます。これであれば、いちいち自ら能動的に計測しなくても、通常業務の中でチェックが可能です。
もう一つは、認知機能の数値化です。認知機能が低下していても、認知症を発症する一歩手前で手先の運動など適切な予防をすれば、機能の維持が期待できます(※4)。こちらは将来的には医療機器プログラム(SaMD)承認を目指し、医療現場で活用いただきたいと考え、新会社のPSTメディカル株式会社を設立し取り組んでいます。
先日、神奈川県と連携協定を結びました。「未病」と呼ばれる、健康と病気の間の状態を数値化する「未病指標」の取り組みにおいて、声から心のコンディションや認知機能の状態を数値化することで、社会課題の解決にも貢献したいと考えています。海外展開も見据えており、すでに約60カ国で検証を行っています。
(※4)軽度認知障害:認知症と健常な状態の「中間のような状態」を「軽度認知障害」といい、適切な予防をすることで健康な状態に戻る可能性がある
ーー今後、どのような人材を求めていらっしゃいますか。
大塚寛:
意欲と能力があれば年齢に関わらず歓迎します。「世の中にないものをつくろう」という意欲があり、応用が利く方に集まっていただきたいですね。
ーー今後の展望をお聞かせください。
大塚寛:
技術革新は進んでいますが、ロボットやAIは人に置き換わる存在ではなく、人を補う手段です。メンタルの不調や認知機能低下を早期発見するテクノロジーがあれば、人々のコミュニケーションは、よりよいものになるはずです。私たちはテクノロジーを使って人が人を助ける、相互扶助の社会実現を目指しています。現代社会を健やかに過ごすためには正しい情報を得て行動することが大切ですので、日本から世界への情報発信の担い手となれれば嬉しいですね。
編集後記
メンタルの好不調や認知症は、血液や脳波といった明確な数値では測れない。ともすれば「気の持ちよう」という曖昧な認識によって、さらに悪化するケースもあるだろう。PSTが提供する技術は、生きにくさを感じている人や家族の認知症に悩む人など、多くの人の暮らしに光が差すのではないだろうか。

大塚寛/大学卒業後、1995年に米国スーパーコンピューターメーカーの日本クレイ株式会社に入社。その後、日本SGI株式会社と合併。グラフィックスビジネス部長、執行役員戦略事業推進本部長などを歴任する。MBOを経て、2008年にセグウェイジャパン株式会社を設立し代表取締役社長に就任(現在は会長)。ロボットとの共存社会に不可欠な、音声病態分析技術を開発するPST株式会社の事業を本格的に始動させ、声から心身の状態を可視化する「音声バイオマーカー」技術を日本から世界へ展開することに挑戦している。