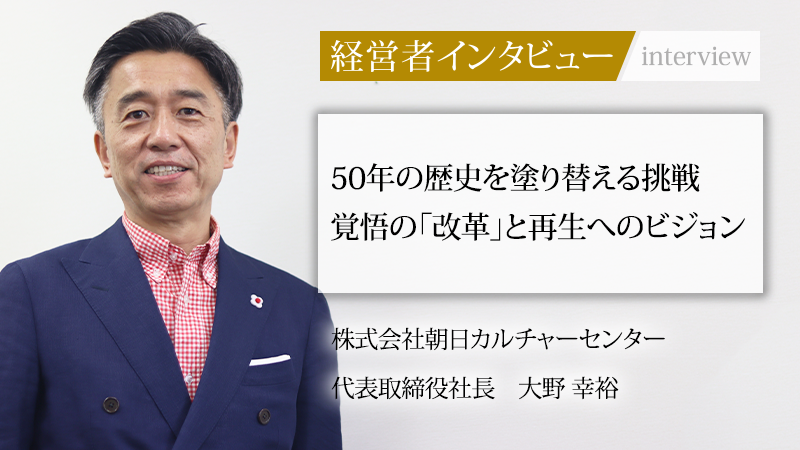
朝日新聞社の文化事業を担う株式会社朝日カルチャーセンターは、1964年の設立以来、50年以上にわたり日本の文化振興に貢献してきた。絵画や文学といった新聞社らしい硬派なジャンルから、近年ではオンライン講座や著名人を招いた特別講座まで、時代に合わせた取り組みを展開してきた。しかし、時代の変化とともに事業環境は厳しさを増し、抜本的な改革を求められる時を迎えた。その重責を担うのが、2025年4月に代表取締役社長に就任した大野幸裕氏だ。
長年、株式会社朝日新聞社(以下、朝日新聞社)で営業や経営企画室を経験し、朝日新聞社のグループ会社であるサムライト株式会社(現・4X)への出向で経営を学んだ大野氏が、どのように組織を改革し、社員一人ひとりの意識を変えようとしているのか。そして、どのような未来を描いているのか、その情熱に迫る。
「現状維持は死」を掲げた断行の裏側
ーー社長に就任されてから、どのような思いで経営改革に取り組んでいらっしゃいますか。
大野幸裕:
私は、この業界で「現状維持は死」だと考えています。日本のシニア人口が減少する一方で、カルチャーセンターの主要な顧客層はシニア世代です。もちろん、この層に向けた講座は今後も重要ですが、インターネットに慣れ親しんだ世代がこれからシニアになっていくことを考えると、これまでのやり方の延長線上では生き残ることは難しいと感じています。
変化を嫌う人は多いと思いますが、会社を変えていこうとする中で、摩擦が起きない方がむしろ不自然だと思っています。社員には、小手先の「改善」ではなく、根本から変える「手術」を伴う「改革」が必要だと伝えています。また、経営者として、赤字は社員の努力を無駄にする「犯罪」だと考えています。社員の思いを形にする責任があるからこそ、プロとしてのプライドを持って経営に当たらなければならないと思っています。
多様性を尊重し「人として謙虚」であること
ーー経営者として、社員や顧客と接する上で最も大切にされていることは何ですか。
大野幸裕:
経営者として最も大切にしているのは、「人として謙虚であること」です。これは、単に低姿勢でいることではなく、年齢や役職に関係なく、一人の人間として相手に敬意を持って接することです。私は支配型のピラミッドの頂点に立つのではなく、円の中心にいて、その周りに社員がいるような関係性を理想としています。また、相手がどう思うかを常に意識することも大切です。たとえば、相手に不快感を与える服装は、どんなに自分がいいと思っていても、その時点で交渉に負けていることになります。自分の価値観だけでなく、相手の視点に立って物事を考えることが、良い関係を築く上で不可欠だと思っています。
全社員との対話で生まれた一体感と斬新な講座企画

ーー社員の皆さんとの向き合い方で、特に意識されたことは何でしょうか。
大野幸裕:
朝日カルチャーセンターへ着任した当初、社員の皆さんは「講座も作ったことのない素人が来た」と思われていたでしょう。本社から来た人間は、現場の社員から「よそ者」として見られがちです。だからこそ、私は「私たちは」という言葉を意識し、自身もこのチームの一員であるという姿勢を示しました。
また、長年、社内にいると気づきにくくなる問題点にも目を向け、気づいた点はすぐに発言するようにしました。素人であるからこそ、現場を知る社員を頼るべきだと考え、全国の各教室すべての社員と、オンラインではなくリアルで1対1の面談を行いました。厳しい意見も多かったですが、本気の思いを伝えるためには必要なことだったと、今では本当にやってよかったと思っています。
新たな挑戦と「多様な人材が活躍できる会社」を目指す人事改革
ーーこれまでの取り組みの中で、特に印象に残っていることは何でしょうか。
大野幸裕:
これまでの主要顧客層であるシニア層以外をターゲットにした、新しいテーマの講座を積極的に展開しています。最近では、歌舞伎俳優の中村鴈治郎さんを招いた「プレミアム講座・中村鴈治郎が語る~映画『国宝』から9月新国立劇場「仮名手本忠臣蔵」まで~」が大きな話題となりました。朝日新聞社がプレスリリースを出してくれたこともあり、テレビや新聞各社から取材が殺到し、会社史上初めてテレビに取り上げられました。また、LUNA SEAのSUGIZOさんといった、これまでの朝日カルチャーセンターには来なかったであろう方々を招くことで、熱狂的なファン層を呼び込むことに成功しています。
ーー今後の展望として、どのようなビジョンをお持ちでしょうか。
大野幸裕:
私が目指すのは、朝日カルチャーセンターの社員が主体となって活躍できる会社です。つまり、経営の中核を本社の新聞社に頼らない組織体制へと移行させ、社員一人ひとりが当事者意識を持てる環境を整えたいと思っています。そういう思いも込めて私のビジョンは「働く皆さんがもっともっと活躍できる会社にしたい」というものです。
社員に自信を持って働いてもらうために、これまで開示してこなかった会社の数字を全て公開し、単月の営業利益が出た際にはAIも使いながら、動画で全社員に共有しています。今後もこうした仕掛けを一つひとつ積み重ね、社員全員が主役として輝ける組織づくりに、全力で取り組んでいきます。
編集後記
株式会社朝日カルチャーセンターの改革を牽引する大野幸裕社長に話を聞いた。長年の営業経験やグループ会社への出向で培った経営の知見を活かし、就任直後から4カ月連続の単月黒字(11年ぶり)を達成。上期営業利益を全国の拠点を集約し、1社となった2010年度以来の最高益とした手腕は目覚ましい。
「現状維持は死」という言葉を掲げ、全社員との1対1の面談や、仕事以外の接点を作る地道な取り組みを通じて、社員の意識を変えようとする情熱は、多くの人に勇気を与えるであろう。高齢化社会が進行する中、時代に合わせた多様な要素を融合させたカルチャーセンターをつくり上げていくという同社の挑戦に、今後も注目していきたい。

大野幸裕/1967年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒。バブル絶頂期に銀行に入行し、出版社を経て、1995年に朝日新聞社に転職。旧広告局を中心に、社長室、デジタル本部、メディアデザインセンター、経営企画本部の他、グループ会社「サムライト」(現・4X)にも取締役として出向。2024年6月に「朝日カルチャーセンター」の社外取締役、2025年4月に代表取締役社長に就任。














