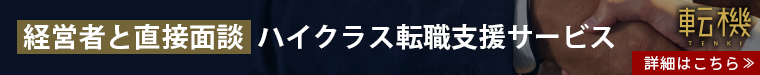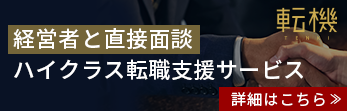【ナレーター】
官公庁、教育機関、医療、エンターテインメントなど、さまざまな業界のプロダクト開発、新規事業開発、人材・組織開発を支援する企業 「株式会社Sun Asterisk」。
2012年にベトナムで産声をあげた同社は、独自のIT・デジタル教育ノウハウを武器に、現在国内外に2000名以上の優秀なエンジニアやビジネスデザイナーなどを擁しており、世界4か国6都市で事業を展開している。
近年ではアジアの大学を中心に、ITや日本語を学べるコースの開設に注力しており、その存在感を際立たせている。
「誰もが価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げる同社の、躍動する経営者の波乱万丈の軌跡に迫る。
【ナレーター】
自社の強みについて、小林は次のように語る。
【小林】
課題解決をしていくプロセスには、いろいろなフレームワークがあり、ある程度確立されているかと思います。しかし、「今までにない未知のものを作る」「新しい価値を生み出していく」というプロセスについては、まだ十分には確立されていません。
新しい事業を立ち上げる際は、ビジネス(持続可能性の視点)、クリエイティブ(有用性の視点)、テクノロジー(実現可能性の視点)という、3つの視点が不可欠です。
その上で、どこに重点を置きながら意思決定していくかが非常に重要だと考えています。そういったフレームワークを自分たちで構築して、再現性のある事業づくりにチャレンジしていっているんですね。常に研究を重ねながら、さまざまな企業や起業家の方たちの新しい価値創造を徹底して支援し続けていることが、大きな強みだと思っています。
さらに、ベトナムでは現地のエンジニアの方たちのコミュニティを運営したり、大学との産学連携を通じて、4年間で1000時間ぐらいの授業を行っています。このように、10年間培ってきたエンジニアコミュニティへの貢献を通じて、ベトナムで優秀なエンジニアを育成し、テクノロジー人材が不足している日本においても、エンジニアを増やしていけるのが僕らの強みだと思っています。
【ナレーター】
小林のファーストキャリアは、26歳の時に就職したソフトウェア開発会社だった。それ以前はクラブなどに勤めて生計を立てており、ITエンジニアになることは全く考えていなかったという。どのようなきっかけで、志すようになったのか。
【小林】
たまたま未経験OKというプログラマーの求人を見つけました。面白い会社で、テストさえ受かればとりあえず社長面接を受けられたんです。そこでエンジニアとして採用されたのが、プログラマーの第一歩です。
プログラミングの仕事は、多分自分に合っていたのだと思います。つくったものが動いて、人の手に届くのってすごく面白いじゃないですか。熱中して取り組んで、大手企業の基幹システムのような大規模な開発にも携わりました。また、コンシューマー向けのソーシャルアプリやソーシャルゲームの開発など、本当に幅広い経験をさせてもらいました。
【ナレーター】
そして、入社から3年後の2012年、出向先のソーシャルゲーム開発プロジェクトでのある出会いが、小林の運命を変えることになる。
【小林】
クライアント側の事業責任者が、現在の弊社の共同創業者である平井だったのです。よく話をしたり、遊びに行ったりするうちに、「アジアでスタートアップを次々生み出せるような、そんなテックチームを作りたいんだけど、一緒にやらないか?」と誘ってもらいました。
当時、ゲーム開発の現場などで、ベトナムや中国の若いエンジニアの方と、リモートで一緒に仕事をする機会が多くありました。彼らは頭が良くて、若くて、めちゃめちゃ働き者で、貪欲な人たちだったんです。そういうメンバーとだったら、何かでっかいことをやれそうだというのがあったので、「ぜひやりましょう」と答えました。
僕はワクワクしちゃったら止まらないので、次の日にはもう社長に「辞めてベトナム行きます」と伝えたという流れでしたね。
【ナレーター】
その後、現Sun Asteriskを創業するためにベトナムへ移住。当時のベトナムの情勢を見て、小林の心にある思いが芽生えたという。
【小林】
道端の木陰にバイクを停めて、その上で器用に寝転がっているおじさんたちがたくさんいて 、まったく仕事なんてしていないんですよ。
ところが、ちょうどGrabとかUber(Uberは後に東南アジアから撤退)が登場した瞬間、そのおじさんたちが「稼げるぞ!」となって、スマートフォンを買って、ヘルメットをちゃんと着けて、Grabのきれいな緑のジャケットを着て、スマホでマッチングしながらお客さんを乗せて働き始めたんです。
スマートフォンの小さなアプリひとつが、こうやって街の景色を変えていくのを見て、「すげーな」と実感しましたし、社会的意義のようなものを感じました。自分たちのやっている仕事は、世界をアップデートしていくものなのだという使命感がどんどん芽生えていったのは、とても大きかったと思います。


 経営者プロフィール
経営者プロフィール